ついに圏央道が成田まで直結――。26日、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の茨城県の境古河IC-つくば中央IC間が開通。湘南海岸から成田空港まで、都心を経由せずに直結しました。湘南・藤沢・相模原・八王子・桶川・北本(上尾)・つくば・成田が結ばれ、首都圏から放射状に延びる東名、中央、関越、東北、常磐、東関東の6道路が接続しました。
利便性、交通渋滞の緩和、観光振興(成田空港から日光、那須、富岡製糸場、川越などの観光地へのアクセス向上)、さらに私が推進してきたインフラのストック効果が格段に前進します。すでに沿線には約1600件の大型物流施設等も進出し、生産性が向上しています。
また外国人観光客等にもわかりやすいように、国交省は全国の高速道路に割り振った路線番号を初めて表示(圏央道はC4、東北道はE4,東名はE1など)、高速道路のナンバリング標識が設置されました。
インフラのストック効果はめざましく、希望をもたらすと思います。
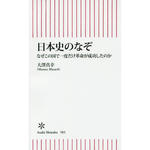 「なぜこの国で一度だけ革命が成功したのか」が副題。なぜ日本には革命がなかったのか。そのなかで唯一の例外として北条泰時がある。革命の困難、革命の不可能性を具現するのが天皇(の持続)だが、北条泰時は正面から皇室と朝廷と戦い(承久の乱)、成功した。「清盛や頼朝がなしたことは、まだ革命とはいえない。・・・・・・彼らは結局、天皇や皇室の権威に助けられ、その権威を受け入れた上で活動しているからである。日本史の上での真の断絶は、清盛や頼朝のところではなく、泰時のところで画されているのである」という。
「なぜこの国で一度だけ革命が成功したのか」が副題。なぜ日本には革命がなかったのか。そのなかで唯一の例外として北条泰時がある。革命の困難、革命の不可能性を具現するのが天皇(の持続)だが、北条泰時は正面から皇室と朝廷と戦い(承久の乱)、成功した。「清盛や頼朝がなしたことは、まだ革命とはいえない。・・・・・・彼らは結局、天皇や皇室の権威に助けられ、その権威を受け入れた上で活動しているからである。日本史の上での真の断絶は、清盛や頼朝のところではなく、泰時のところで画されているのである」という。
「天皇の機能の中核は、この"知る"ことに、執政の現実について"知る"ことにあったのではないか」「聞知してくれる天皇がいなければ、そこに帰属していた意志の"再現"という体裁を構成することができなくなってしまう」「臣下たちの欲望や願望を、ひとつの意志へと転換する装置だったのではないか。天皇の身体を通過することで、それらは政治的に有効な決定となる」・・・・・・。
中国の易姓革命(中国の皇帝の命令は、天命こそ根拠)、孟子の革命思想、「中国の易姓革命は、革命を否定する革命だが、西洋の革命は、まさに革命としての革命」「天の機能が維持されるためには、天は君主にとって"他者"でなくてはならない。それゆえ、日本には易姓革命はない。その端的な現れは、天皇が姓をもたないということである」・・・・・・。
唯一の革命家とする北条泰時を通じ、「革命」の視点から「東の革命、西の革命」「権威の源泉」を剔抉する。
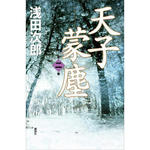 1931年9月18日、奉天の郊外、柳条湖の南満洲鉄道の線路爆破(満州事変)。その前年の1930年4月のロンドン海軍軍縮条約、11月の浜口雄幸首相の東京駅での狙撃。1月には金解禁、世界恐慌の嵐。1932年3月、満洲国建国宣言、溥儀が執政に就任。そして国際連盟はリットン調査団を派遣。この激動のなか、中国で日本で、各人の思惑が錯綜し、激突する。
1931年9月18日、奉天の郊外、柳条湖の南満洲鉄道の線路爆破(満州事変)。その前年の1930年4月のロンドン海軍軍縮条約、11月の浜口雄幸首相の東京駅での狙撃。1月には金解禁、世界恐慌の嵐。1932年3月、満洲国建国宣言、溥儀が執政に就任。そして国際連盟はリットン調査団を派遣。この激動のなか、中国で日本で、各人の思惑が錯綜し、激突する。
大清の復辟を熱望する溥儀、梁文秀。その流れに従う張景恵。それに断固として抗う馬占山は「還我河山。我に山河を返せ」と叫ぶ。一連の挑発行為の中心者・関東軍の板垣征四郎、土肥原賢二、動かす石原莞爾。土肥原の下にいた志津邦陽。そして日本国内において関東軍と見解を異にする永田鉄山、呼び寄せられる張作霖の軍事顧問であった吉永将。石原等の関東軍参謀たちが拡げた大風呂敷を、どう畳むかという使命に立つ武藤信義大将と溥儀の会談。東北軍を離れ"龍玉"を持つ李春雷と林純先生・・・・・・。
「満州国とは何か」――満州国建国をめぐり、謀略渦巻く濁流の時代を描く。





