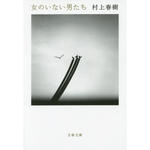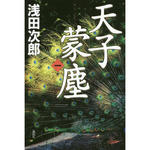 「蒼穹の昴」「珍妃の井戸」「中原の虹」「マンチュリアン・リポート」に続く第5部「天子蒙塵」の第一巻。待望の書だ。天子蒙塵とは「天子が塵をかぶって逃げ出す」こと。
「蒼穹の昴」「珍妃の井戸」「中原の虹」「マンチュリアン・リポート」に続く第5部「天子蒙塵」の第一巻。待望の書だ。天子蒙塵とは「天子が塵をかぶって逃げ出す」こと。
張作霖爆破事件をはさみ、宣統帝溥儀と皇后・婉容、淑妃・文繡、そしてその側近たち、更には張学良らが何を思い、どう動いたか。溥儀と文繡の離婚劇の真相から、日本がかかわった天津から満洲建国への道のりを、文繡姉妹の静かな語りによって描いている。
巨大な時代の荒波に吞み込まれながらも、自由をめざした女性の物語でもあり、同じ荒波のなかで大清の復辟を秘めつつも楽園的日常に浸るラストエンペラー・溥儀の姿など、悲哀が滲む。1930年代の中国大陸への序章がこの第1巻だ。
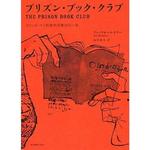 「わたしは、老眼鏡をはずし、フランクの日記帳を脇のテーブルに置いた。この世界には、なんとさまざまな囚われびとがいることだろう。監獄の囚人、宗教の囚人、暴力の囚人。かつての私のような恐怖の囚人もいる。ただし、読書会への参加を重ねるたびに、その恐怖からも徐々に解放されてきた」――。
「わたしは、老眼鏡をはずし、フランクの日記帳を脇のテーブルに置いた。この世界には、なんとさまざまな囚われびとがいることだろう。監獄の囚人、宗教の囚人、暴力の囚人。かつての私のような恐怖の囚人もいる。ただし、読書会への参加を重ねるたびに、その恐怖からも徐々に解放されてきた」――。
副題に「コリンズ・ベイ刑務所読書会の一年」とあるが、2011年から12年にかけて、2か所の刑務所読書会を友人のキャロル・フィンレイに誘われて務めたアン・ウォームズリーが、受刑者の生の声を交えて、小説風にまとめたもの。トロント在住。イギリスで強盗に襲われ命を落としかけたという傷が常に心奥にある。
選ばれた本はかなり深く、生々しい現実と格闘するものが多い。「ガーンジー島の読書会」「怒りの葡萄」「またの名をグレイス」「ユダヤ人を救った動物園」「第三帝国の愛人」「サラエボのチェリスト」・・・・・・。欧米社会に沈潜する戦争、分断、差別、虐待、銃、暴力、テロ。脅威、迫害、強迫観念。宗教や人種の対立・・・・・・。日本の自然、人間との融和社会との差異はあるが、世界共通の人間社会の亀裂を、受刑者たちが読書を通じて考え、重い口を開いていく。人生のギリギリを生きている人たちだけに、切実な思いとリアリズムが詰まっていると感ずる。
「うしろを振り向かず、将来のことも考えない。とにかく今日一日を生きなさい」「人生がちょっとばかりつらくても、おれたちは日々の暮らしを続けるだけだ」――。希望を捨て去って、絶望のなかに生を見る。読書に選ばれた最近の本を読んでないのに悔しい思いがした。
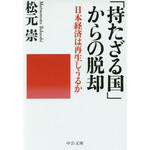 「日本経済は再生しうるか」が副題。「IT革命による世界の生産構造の激変」が、今、世界で起きている。それはIT技術による製造工程のモジュール化によってもたらされたものだという。個別企業固有ではなく、企業横断的に、しかも世界のどの地域でも可能となっている。部品のモジュール化により、製造工程を臨機応変に変え、大胆なアウトソーシングも可能となる。そして「米国の一人勝ち」となっているが、それは米国の生産の仕組みが元来、モジュール化しており、労働市場においてもレイオフは一般的だし、経営者も働く人も多くの企業を渡り歩いていく。流動性をもっている。そして、その過程でキャリアアップしていく。
「日本経済は再生しうるか」が副題。「IT革命による世界の生産構造の激変」が、今、世界で起きている。それはIT技術による製造工程のモジュール化によってもたらされたものだという。個別企業固有ではなく、企業横断的に、しかも世界のどの地域でも可能となっている。部品のモジュール化により、製造工程を臨機応変に変え、大胆なアウトソーシングも可能となる。そして「米国の一人勝ち」となっているが、それは米国の生産の仕組みが元来、モジュール化しており、労働市場においてもレイオフは一般的だし、経営者も働く人も多くの企業を渡り歩いていく。流動性をもっている。そして、その過程でキャリアアップしていく。
日本は、かつては「一人勝ち」の時代があった。終身雇用があり、企業のなかに一生があって、そのなかで経験が生かされ、生産性も上がっていた。しかし今、その成功体験が硬直的な雇用慣行に縛られることになっている。全くモジュール化していない労働市場ということだ。不採算部門をかかえ、人はその能力を発揮できず(能力が追いつかず)、余剰人員となっていても、解雇は難しい。解雇されてしまった人は次の働き口が見えないから、ワーク・ライフ・バランスを欠いてもしがみつくことになる。日本では転職は大変高いリスクを伴うわけだ。非正規社員もキャリアを積めない。生産性が上がらず、国全体の付加価値が増えなくなり、日本型格差社会ともなる――そう指摘する。
だからこそ、「一億総活躍」「子育て支援」「雇用支援」「働き方改革」が大事となる。
ドイツとスウェーデンの取り組みを紹介し、今日的状況のなかで、ワーク・ライフ・バランスを回復して日本人の能力を解き放ち、人的資源をしっかり活用し、稼ぐ力を回復すれば、発展と幸せにつながることを説く。