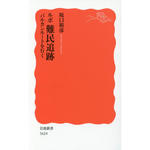 副題は「バルカンルートを行く」だ。欧州各国に押し寄せる大勢の「難民」。内戦が続くシリア、依然として政情が定まらないアフガンやイラク。大勢の難民が、トルコ、ギリシャからマケドニア、セルビア、クロアチア、スロベニアと旧ユーゴスラビアを縦断、オーストリアを経て、ドイツをめざす。ハンガリーが越境防止フェンスでセルビア国境を封鎖(2015.9.14)、クロアチアとの国境でもフェンスで封鎖(2015.10.17)、人道危機を食い止めようという理念はあっても、欧州各国は圧倒的な人波を抱え込めない現実に直面している。その生々しい実情を、坂口記者がドイツをめざすアフガン人一家に寄り添って同行した渾身のルポ。
副題は「バルカンルートを行く」だ。欧州各国に押し寄せる大勢の「難民」。内戦が続くシリア、依然として政情が定まらないアフガンやイラク。大勢の難民が、トルコ、ギリシャからマケドニア、セルビア、クロアチア、スロベニアと旧ユーゴスラビアを縦断、オーストリアを経て、ドイツをめざす。ハンガリーが越境防止フェンスでセルビア国境を封鎖(2015.9.14)、クロアチアとの国境でもフェンスで封鎖(2015.10.17)、人道危機を食い止めようという理念はあっても、欧州各国は圧倒的な人波を抱え込めない現実に直面している。その生々しい実情を、坂口記者がドイツをめざすアフガン人一家に寄り添って同行した渾身のルポ。
押し寄せる難民・移民、苦悩する欧州――ともに必死。かつこれは世界に広がる深刻な課題として進行中のものだ。あの穏やかで温かい坂口記者が、なんと厳しく激しい排戦ルポを断行したかと思うとともに、「あとがき」を読んで胸が詰まった。どんな思いで・・・・・・。
 本日12月1日、朝5時から中央環状線内回りの中野長者橋付近の渋滞解消対策として「エスコートライト」の運用が始まりました。これは、11月7日に首都高速の渋滞解消・老朽化対策を視察した際に、首都高側と打ち合わせしたことです。
本日12月1日、朝5時から中央環状線内回りの中野長者橋付近の渋滞解消対策として「エスコートライト」の運用が始まりました。これは、11月7日に首都高速の渋滞解消・老朽化対策を視察した際に、首都高側と打ち合わせしたことです。
「エスコートライト」は、車が上り勾配で速度が落ちるのを防ぐための渋滞対策装置。2015年3月に中央環状線が全線開通し、都心環状線の渋滞は50%解消されました。しかし、中央環状線の交通量が増加し、朝夕、中央環状線内回りの中野長者橋付近で慢性的に渋滞が発生しています。この渋滞は、車が上り坂にさしかかった時に速度低下することが原因です。この速度低下を防ぐ対策として、路側に設置したライトの光を進行方向へ流れるように点灯させ、速度を維持させようというものです。実際に、3号渋谷線下り池尻付近に設置した「エスコートライト」によって、最大通過台数が約3%向上し、効果が出ています。
さらに渋滞解消に工夫をし、進めていきます。
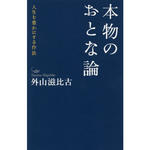 「いつまでも一人前の人間にならない大きなこどもがふえた」「それは当り前である。学校は生活を停止して知識を教え」「家庭は豊かになり、ひとりっ子がふえ"ハコ入りこども"として大事に育てられ、生活がない」という。
「いつまでも一人前の人間にならない大きなこどもがふえた」「それは当り前である。学校は生活を停止して知識を教え」「家庭は豊かになり、ひとりっ子がふえ"ハコ入りこども"として大事に育てられ、生活がない」という。
「大人といわれる人はそれぞれのスタイルをもっている。スタイルのない生き方をしているのは大人ではない」「落ち着いた声で話すのが大人である」「ハダカのことば、むき出しのことばは・・・・・・よくないことばである。ことばを慎む――それが大人である」「大人にはたしなみが必要。敬語はことばのたしなみである」「ハコ入りはハコから出さなくてはいけないというのが大人の知恵である」「学校出は多く、苦労が足りない・・・・・・人間がわからない。心が冷たい。自己中心的で幼稚である。知識と智恵を混同している・・・・・・あわれな知性の貧困である」「エスカレーターでなく、階段が大人をつくる。いまの教育はエスカレーターのようなものである。知識(教育)だけでは人は育たない。苦労という月謝が人を育てる」「文化はウソ半分、である。ウソのうまくないのは、幼い文化、幼い人間である」「相手を大切にするのが大人である」「A級人間は試行錯誤する。模倣は易く、失敗は難し。知識は安く、生活は貴重。B級の優等生よりA級の劣等生の方がすぐれているのである」・・・・・・。
中年になっても大人になれない人が少なくないことが問題だと、静かに説く。
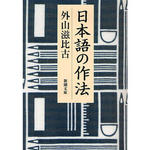 「いくら乱暴な人でも上司に会うのに腕まくりをするようなことはすまいが、ことばに関しては腕まくりのようなことばを使って平気である。ことばの文化は服装ほどには進化していないのかもしれない。ことば遣いは相手を考え、遠慮会釈のあるのが一人前である」
「いくら乱暴な人でも上司に会うのに腕まくりをするようなことはすまいが、ことばに関しては腕まくりのようなことばを使って平気である。ことばの文化は服装ほどには進化していないのかもしれない。ことば遣いは相手を考え、遠慮会釈のあるのが一人前である」
人にやさしいことば、また刺すことばがあるが、「人を傷つけない、人にやさしいことばは、美しいことば以上に大切である」
「・・・・・・たいへん役不足でありますが・・・・・・」は力不足の誤り、ことばの過ちだ。
「あいさつ、人のためならず」
「ナシのつぶて(投げた小石が返ってこないことに梨とナシをかけた)は礼を失する」
文化の成熟した社会では、ことばが大切にされる。ことばは教養の目じるしだ。戦後、ことばが乱れ、人の心もすさび、人間関係がざらざら、ぎすぎすしている。乱雑な世の中。敬語をきちんと使える人になることが成熟さの度合だ。
「長上に対してなれなれしい口をきいて平気だというのは未熟である」
淡々と書かれているが、内容は重い。


