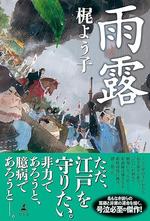 慶応4年(1868) 1月、鳥羽伏見の戦いで幕府軍を破った新政府軍が江戸に迫る。勝麟太郎と西郷隆盛はそれぞれの思惑を抱きつつ「江戸無血開城」を成し遂げる。そこで多くの町人も交えて結成された彰義隊。上野寛永寺に立てこもるが、大村益次郎が指揮する最新兵器を駆使する新政府軍に、わずか半日で敗北する。勝、西郷、山岡鉄舟、益満休之助といった敵味方でありながら江戸無血開城を成し遂げた者たちの、強固な絆を様々な角度で描くことは多いが、この「雨露」は若き彰義隊隊士の葛藤と運命を生々しく描く。彰義隊とは何であったか。なぜ名もなき彼らは無謀な戦いに身を投じたのか。江戸の庶民は、なぜ彰義隊を称賛し味方をしたのか。歴史の残酷さと、激流の中で揺れ動く心、修羅場の濁流に飲み込まれる時の人間の呻き声が聞こえてくるようだ。
慶応4年(1868) 1月、鳥羽伏見の戦いで幕府軍を破った新政府軍が江戸に迫る。勝麟太郎と西郷隆盛はそれぞれの思惑を抱きつつ「江戸無血開城」を成し遂げる。そこで多くの町人も交えて結成された彰義隊。上野寛永寺に立てこもるが、大村益次郎が指揮する最新兵器を駆使する新政府軍に、わずか半日で敗北する。勝、西郷、山岡鉄舟、益満休之助といった敵味方でありながら江戸無血開城を成し遂げた者たちの、強固な絆を様々な角度で描くことは多いが、この「雨露」は若き彰義隊隊士の葛藤と運命を生々しく描く。彰義隊とは何であったか。なぜ名もなき彼らは無謀な戦いに身を投じたのか。江戸の庶民は、なぜ彰義隊を称賛し味方をしたのか。歴史の残酷さと、激流の中で揺れ動く心、修羅場の濁流に飲み込まれる時の人間の呻き声が聞こえてくるようだ。
彰義隊(義を彰かにする隊)の中心となった天野八郎と、渋沢成一郎。「返す返すも残念。徳川の屋台骨が揺らいでいるならば、新たに立て直しを図るのが、主家に対する武家の務めではないか。しかし、薩長は国を思うのではなくて、徳川一家を潰すことに血道を上げている。我らの敵は、官軍にあらず。傲慢という衣を纏った薩長軍だ」と天野は武士としての道を言う。渋沢は「家臣として慶喜と徳川を守る」という意思を貫こうとする。江戸の町には薩長の乱暴・狼藉に対する反感が充満していた。慶喜はどこまでも恭順の姿勢を貫いており、「我らが見境なく血気に逸ることは、すなわち、我らの首を絞めることにもなりかねない。武力で薩長に当たれば、お上の意志を潰すことになる」との逡巡もある。「お上を守り、徳川を守り、江戸を守る」と言っても、それぞれの思惑は違い、複雑であった。
そうしたなか、臆病者の武士・小山勝美は兄・要太郎に言われて彰義隊に入る。絵を描くのが好きで、浮世絵の歌川国芳の弟子・芳近に学んでいた。父に軟弱を責められて勝美は言う。「私は確かに兄上に連れられ、彰義隊に入りました。何のためであるのか全くわからず。江戸は火の海にはならなかった。代わりに、江戸城は薩長の手に落ち、お上はお発ちになった。薩長率いる新政府軍は既に江戸にいる。私は、絵筆を取り戻すために彰義隊におります。小銃も刀も持てない人々が再び安心できるように・・・・・・。我ら武士は己れの意地を通すだけのものではないと私は思っている」・・・・・・。
そして、5月の雨と露のなかでの阿鼻叫喚の決戦。降り続く砲弾。鈍く不気味な地響き。飛び散る火。勝美は、「やはり戦ってはいけなかったのだ」「武士たちは、義を掲げ、崩壊する主家と運命を共にする潔さに、自分たちも酔いしれた。それを江戸の庶民は歓迎し称賛した。だから、勘違いしたのだ。驕ってしまったのだ」「非力ながらも、江戸を守りたいと思ったからだ。命を落とすことがあったとしても、構わないとわずかでも思った」と、思いは揺れに揺れる。すべてのものが、歴史の激流に翻弄され、深い傷を負い、明治を迎えたのだ。名もなき者たちが激しい葛藤のなか戦いに殉じた姿を赤裸々に描く力作。
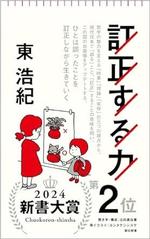 大変刺激的で、面白い(目の前がぱっと開ける)著作。「訂正する力とは『考える力』ということでもある。本書はなによりもみなさんに『考えるひと』になってもらいたいと思って書いています」と言っている。「なにも考えずに成功している人」は確かに多いが、現代社会に「思考停止」「問題を深く考え続けない」「哲学不在」が充満している限り未来は開けない。ウィトゲンシュタイン、トクヴィル、ルソーなどを自在に使いながら・・・・・・、「訂正する力」の意味と重要性を様々な角度から示す。学生時代、激しい学生運動の中で「非政治世界の構築」を掲げて戦ったこと、政治の中で制度改正や法改正などに格闘したことを思い出した。
大変刺激的で、面白い(目の前がぱっと開ける)著作。「訂正する力とは『考える力』ということでもある。本書はなによりもみなさんに『考えるひと』になってもらいたいと思って書いています」と言っている。「なにも考えずに成功している人」は確かに多いが、現代社会に「思考停止」「問題を深く考え続けない」「哲学不在」が充満している限り未来は開けない。ウィトゲンシュタイン、トクヴィル、ルソーなどを自在に使いながら・・・・・・、「訂正する力」の意味と重要性を様々な角度から示す。学生時代、激しい学生運動の中で「非政治世界の構築」を掲げて戦ったこと、政治の中で制度改正や法改正などに格闘したことを思い出した。
政治と金、デフレ脱却への経済戦略、米中対立の中での安全保障・・・・・・。「訂正する力」の重要性は日常だ。「訂正する力」とは、「過去との一貫性を主張しながら、実際には過去の解釈を変え、現実に合わせて変化する力――過去と現在をつなげる力」「持続する力であり、聞く力であり、記憶する力であり、読み替える力であり、『正しさ』を変えていく力」である。「リセット、革命」でもなく、「絶対変わらない、頑な、ぶれない」でもない。激動する社会を直視し、「現状を守りながら、変えていく力」が「訂正する力」だ。「自分はこれで行く」「自分はこのルールをこう解釈する」と決断する力のことだが、今の日本にそのような決断をできる人があまりないと嘆いている。私は、「政治はリアリズムであり、現実を直視した臨機応変の自在の知恵である」と言ってきたが、「訂正する力とは、現実を直視する力。現実に対応しながらも、同じ理想を守っているんだと『再解釈』しながら前に進むことだ」と東さんは言う。そして、「互いの顔色を見て」「空気の支配するまま」「正義を掲げる思考停止」「対話を拒否し相手に勝つ論破力」は、訂正する力とは対極にあると言う。あらゆる対話の原点にある力なのだ。ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論、「ゲーム(遊び)とは、人間の言語的なコミュニケーションの全体を覆う概念」に連なっていく。
そして「人間は『じつは・・・・・・だった』の発見によって、過去を常にダイナミックに書き換えて生きています。よく生きるためには、この書き換えをうまく使うことが大事です。それが訂正する力ということです」と、そのダイナミズムを提示する。人口減少・少子高齢化、経済の凋落、深刻な国際情勢に直面している時、リベラル派がリセットを望んでいるようだが、まさにここで「訂正の考え方をとった方が良い」と指摘する。
面白いのは「訂正する力とは文系的な力」と言う。文系の学問は「じつは----だった」の学問で、過去の著作を引っ張り出し(例えばマルクス、斎藤幸平の「人新世の『資本論』」)、新たな視点から解釈して読み直すこと始めばかりやっている。理系はニュートンを読み直すなどしないと言っている。私自身、そう思っていたから、私は理系ということになる。また「訂正こそが人間の人間性を支えている」であって、ChatGPTは言葉の世界しかないので訂正ができない。さらに修正する力をうまく使って生きるためには「周りに余剰の情報の場を作ること」「柔軟なひとを周りに集める小さな組織や結社を作り、親密な公共圏を作る」ことの大切さを示している。
これはトクヴィルにつながるが、「彼は民主主義の精神とは喧騒のことだと考えた。アメリカではいろんな人間がいて好き勝手に喋り、出版の自由も結社の自由も保証されている」と言い、「平和とは喧騒があるということだ。その喧騒の正体は、社会が政治に完全に支配されていないことにある」と指摘する。「平和とは、戦争の欠如であり、つまりは政治の欠如である」。そして戦後日本は、「脱政治的な活動」の領域が豊かだった国、政治の外側に豊かな「喧騒」の世界をつくり続けてきた国ではないか。「ぼくは戦後日本の平和主義をそんなふうに『訂正』してみたいと思う」と言うのだ。そして親鸞の自然(非政治)と日蓮の作為(政治)、ルソーの中に同居する自然と社会契約の矛盾撞着の思想を紹介する。
敵と友に二分し、極論ばかりの分断・抗争の21世紀の世界――「訂正する力の歴史を思い出すことが、失われた30年を乗り越え、この国を復活させる一つのきっかけになる」と結論付ける。
 武士を主人公にした心に沁み入る時代小説を数々著してきた砂原さんが初挑戦した「江戸市井もの」。表と裏の顔、感情のひだ、人生の哀切を実にリアルに描いた8つの短篇。
武士を主人公にした心に沁み入る時代小説を数々著してきた砂原さんが初挑戦した「江戸市井もの」。表と裏の顔、感情のひだ、人生の哀切を実にリアルに描いた8つの短篇。
「帰ってきた」――賭場で相手に大怪我をさせ島送りになった夫。それから3年、妻は夫の弟分で冴えない男とねんごろの仲になっていた。「帰ってきたらしいんだ。兄きが」・・・・・・。二人は慌てるが、事件には予想もしない真実があり・・・・・・・。女の腹の決め方は切れ味鋭く絶妙。
「向こうがわ」――両国橋を挟んで喧嘩のための喧嘩を繰り返している幹太と進次郎。2人は、子供の頃は同じ裏長屋に住んでいた。橋は出会いと別れ、恋と欲と意地の交差点。思いもよらない展開が----。
「死んでくれ」――10年も前に借金を作って逃げた親父が、日本橋界隈でも知られた太物問屋で働いていた娘を突然訪ねてくる。それでまた借金の穴埋めを頼む。娘の放った驚くほど冷え冷えとした「死んどくれよ」の一言。いなくなってほしいと願ったのは、本当だった。でも・・・・・・。
「さざなみ」――子ども時分からおさくを想い続けてきた勝次。ところが、おさくは源太という猪牙舟の船頭と所帯を持ってしまう。源太が、やくざ者に刺されて死んだということから、勝次はおさくと一緒になる。そんな時、おさくをつけ狙ってる男がうろつき始める。ある日、寝ているおさくが「げん、た・・・・・・」「・・・・・・かんにんして」と漏らす。動揺する勝次は・・・・・・。何という展開か、「さざなみ」の結末は凄まじい。映像が浮かぶような丁寧な筆致にも感動する。
「錆び刀」――主家が改易になって投げ出された若者・田所平右衛門。浅草の裏長屋に住むが、3軒隣に住んでいる娘・およしが何かと手助けをしてくれる。心を惹かれる平右衛門だったが、道場仲間の山崎市之進が仕官の当てがあるという誘いをかける。どちらを取るか悩む市之進の決断は・・・・・・。
「幼なじみ」――日本橋の呉服屋・武蔵屋に奉公して5年以上、主人たちに気に入られて手代に取り立てられた秀太郎。跡取り娘のおそのにも何かと声をかけられ、心を寄せられる。そんな時、年下の幼なじみの梅吉が奉公に来て再会する。貧しい長屋で育った二人。ところが、その梅吉は盗人の手先だった。「裏店で生まれたら、ずっと裏通りなんだよ」「おめいだけは・・・・・・いや、おめいも、やっぱり、そうなっちまうのかよ」・・・・・・。驚く結末。過酷な人生の裏表、哀切漂う物語。
「半分」――生まれた長屋も齢も同じで、幼い頃から姉妹のようにして育ったおゆみとおのぶ。おのぶは17で3つ年上の大工と所帯を持ち、橋を渡って深川に越したが、亭主が死に、次第に転落していった。そのおのぶが死んだという。子供は17になる草太と父親違いの妹お咲が残された。何故か気になるおのぶは通って、何かと面倒を見るが・・・・・・。「こいつ17なんだろう、おめいの半分しかねえじゃないか」・・・・・・。母親のような愛の形もあるだろうと、しみじみ思ってしまう。
「妾の子」――「妾の子」「囲い者の娘」と蔑まれ続けた娘・るいが母の死によって本宅に引き取られる。やがて嫁ぐことになるが、相手の男から「妾の子だそうだな」と言われ動揺、思わぬ行動をとるが・・・・・・。これは気持ちの良い結末の物語。閉塞した江戸社会の宿業の重さと一瞬の光による転換。人間の一言の大切さが鮮やかに描かれる。
原作から脚本・演出にまで広がるような空気・温度まで感じさせる砂原浩太朗の新しい世界。
 「ことばはどう生まれ、進化したか」が副題。「オノマトペの性質や役割を明らかにしたいという筆者たちの探求は、『言語習得』『言語進化』に変わり、いつしか『言語の本質』という、エベレストの山頂を目指すような旅になっていった」――。今井さんは、発達心理学の視点から、秋田さんは言語学の視点から、協力してオノマトペを問うことから始まり、言語の習得と起源・進化の道のりを探求、言語の本質に迫る。人間だけが持つ言語。そこに根源的かつ実証的に迫っていく挑戦的な姿勢はきわめて刺激的で納得する著作。
「ことばはどう生まれ、進化したか」が副題。「オノマトペの性質や役割を明らかにしたいという筆者たちの探求は、『言語習得』『言語進化』に変わり、いつしか『言語の本質』という、エベレストの山頂を目指すような旅になっていった」――。今井さんは、発達心理学の視点から、秋田さんは言語学の視点から、協力してオノマトペを問うことから始まり、言語の習得と起源・進化の道のりを探求、言語の本質に迫る。人間だけが持つ言語。そこに根源的かつ実証的に迫っていく挑戦的な姿勢はきわめて刺激的で納得する著作。
すべての出発点はオノマトペ。オノマトペは、物事の一部分を「アイコン的」に移し取る。残りの部分を換喩的な連想で補う点が絵や絵文字などとは根本的に異なる。「角張っている阻害音、丸っこい共鳴音」「オノマトペは聴覚を軸としながらも、ジェスチャーという視覚的媒体と、マルチモーダルなコミュニケーション手段」「オノマトペは子供じみた音真似であって言語ではない、と言う学者もいるが、あくまで言語である」など、言語の十大原則等に基づいて分析する。極めて興味深い。「オノマトペは、言語が身体から発しながら身体を離れた抽象的な記号の体系へと進化・成長するつなぎの役割を果たすのではないか」と言う。オノマトペは、言語学習の足場なのだ。
それでは、言語はどのようにオノマトペから離れて、巨大な記号の体系に成長していったのか。「言語の進化」だ。ここで紹介される身体につながっていることばはオノマトペだけでなく、「やわらかい」「かたい」など、世界各地の「一般語と身体性」「音と意味のつながり」が紹介されるが、極めて面白い。「言語の学び手(赤ちゃん)は、新しいことばを覚えるとともに母語の音やリズムの体系、音と意味の対応づけ、語彙の構造などを自分で発見しながら学んでいく。・・・・・・自分を母語の体系の中に溶け込ませていき、体系の中で、もともと文化や言語の文脈の外では感じなかった二次的なアイコン性の感覚を作り上げていく」「言語が進化する上で、オノマトペから離れながらも、抽象的な意味を持つ記号が、言語の使い手の中で身体とつながっている感覚を残していく。このような図式が記号接地問題に対する答えだ」・・・・・・。そして知識を蓄え、学習した知識を分析してさらなる学習に役立つ手がかりを探して学習を加速させ、効率よく知識を拡大していく。その背後にあるのが「ブートストラッピング・サイクルである」と言う。
「つまり言語習得とは、推論によって知識を増やしながら、同時に『学習の仕方』自体も学習し洗練させていく、自律的に成長し続けるプロセスなのである」――。そこで「ヒトが磨いてきた推論」と「動物は行わない(できない)推論」という推論問題に到達する。著者たちが示したのが「演繹推論、帰納推論に加え、『仮説形成推論(アブダクション推論』」だ。演繹推論は新たな知識を創造しない。生息地が限定的なチンパンジーなどの動物は、生活の中で遭遇する対象の多様性・不確実性はヒトほど高くない。そこでは直接観察できる目の前の対象を精度よく処理するには、誤りを犯すリスクが少ない演繹推論の方が生存に有利となる。しかしヒトは居住地を全世界に広げ、他の民族や不確実な自然などの対象を推測・予測する必要があり、新しい知識で立ち向かうしかなかった。アブダクション推論の必要性だが、それによって、人間は言語というコミニュケーションと思考の道具を得ることができたのだ。観察される部分を全体的に一般化するのが帰納推論、観察不可能な何かを仮定し仮説を形成する推論がアブダクション推論だ。当初は感覚に頼って作った小さな知識が新たな知識を生み、雪だるま式に自律的に知識を成長させていく「ブートストラッピング・サイクル」の中心的な役割を果たすのが「アブダクション推論」だ。「AならばX」を「XならばA」に過剰一般化する、原因と結果をひっくり返すなどの非論理的で誤りを犯すリスクのあるアブダクション推論を人間は発達のエンジンとし、抽象的な概念を習得してきたのだ。なお現在のニューラルネット型AIは記号接地を全くしていない。
確かに、本書を読み進めるうち「オノマトペからスタートした筆者たちの言語探求の旅」に、自分が伴走していたことに気づく。それほどの迫力ある知的刺激の著作だ。
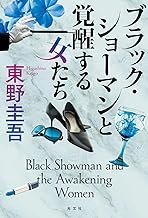 真世の叔父さん、警察を手玉に取って、謎を解明していく心理学にたけた「黒い魔術師」の知恵と仕掛けが満載。痛快、爽快、バー「トラップハンド」のマスター神尾武史が活躍する。
真世の叔父さん、警察を手玉に取って、謎を解明していく心理学にたけた「黒い魔術師」の知恵と仕掛けが満載。痛快、爽快、バー「トラップハンド」のマスター神尾武史が活躍する。
「リノベの女」――亡き夫から莫大な財産を相続した女性・ 上松和美の前に、何十年も会っていない絶縁したはずの兄が突如現れ、「あんたは俺の妹じゃない。偽物だ」と脅す。一体どうなっているのか。一部始終を聞いていたマスターの神尾は驚くべき謎解きを披露する。よくぞここまでという絶妙のさばきは素晴らしいし、面白い。
「マボロシの女」――歯科医でジャズ・ミュージシャンの高籐智也は火野柚希と「息子が高校を卒業したら離婚して一緒になろう」約束をしていた。ところが突然、交通事故で死亡してしまう。2年たっても立ち上がれない柚希。「親友の為なら、たとえ自分が傷ついても構わない」と、親友の山本弥生は神尾と相談し思いもよらない手を打つ。人が生きていくうえで助けとなるのは、失ったものではなく、手に入れたものです。愛する人は帰ってこない。だけどあなたには、あなたの為なら、血を流す覚悟を持つ友人がいる」・・・・・・。柚希は「明日からは生まれ変わろう」と神尾に言うのだった。
「相続人を宿す女」――文光不動産の神尾真世はマンションのリフォームを頼まれ富永良和・朝子夫妻から相談を受ける。ところが大変なことが起きる。その持ち主の息子が交通事故で急死。さらに8ヶ月前に離婚した奥さんから、妊娠しており、おなかの子には相続権があると言ってきたという。相続目当ての嘘ではないか。――神尾が動くが・・・・・・。とてつもない真実に、本作に没入、驚愕した。凄まじい謎解き。
「続・ リノべの女」――老人施設に入っている末永久子は認知症が始まっていたが、自殺した娘はまだ生きていると言い始める。そんな時、古くからの親しい友人からも「街で偶然懐かしい奈々恵さんを見かけた」との手紙を受けていた。「彼女の幽霊を探し出そうとするやつが店にやってきた」「上松和美は、真世が部屋のリノベーションを担当した客だが、重大な秘密があった。・・・・・・本名は末永奈々恵・・・・・・」。「リノベの女」の後日談だが、よくこんなことを思いつくというほどの謎解きと解決策。
「査定する女」――「トラップハンド」の常連客・インテリアコンサルタントの陣内美菜は、"玉の輿願望"の持ち主で、相手を連れてきては神尾に査定をお願いしていた。いつも大胆かつ巧妙な見事な査定だった。今回、真世の紹介で会った男はなかなかの男で査定は合格。ところが、同時にアメリカのミュージカルスターへの本格的誘いを受ける。さぁどうする? そこで神尾の仕掛けた驚天動地の一手とは・・・・・・。
いずれも、さすがと唸らせる東野圭吾の世界。かつ登場する女性は皆、覚醒し、新出発をするのだ。

