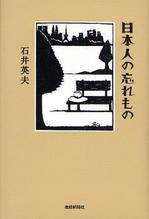ボーイング787型機のさまざまな不具合、事故が起き、連日、原因究明や対応に取り組んでいます。何よりも安全第一、そして利用者の方々に安心して搭乗いただけるよう全力をあげる決意です。
ボーイング787型機のさまざまな不具合、事故が起き、連日、原因究明や対応に取り組んでいます。何よりも安全第一、そして利用者の方々に安心して搭乗いただけるよう全力をあげる決意です。
16日は、「東京ユビキタス計画・銀座」を視察しました。これはICT(情報通信技術)を活用した歩行者移動支援の意欲的な試みです。東京大学の坂村健教授の案内のもと、東京メトロ銀座駅構内で、災害があった場合の安否情報や、車いすの人にも進行通路の案内などの情報が的確に伝わるように、ICTが使われるシステムを視察できました。また銀座4丁目付近では、一般のスマートフォンを活用した観光案内が外国人の方々にも利用できるきわめて多機能のシステムを体験しました。
現在は銀座、新宿などで試行している段階ですが、防災、観光等々、きわめて有効なもので、地道に推進したいと思っています。
こんにちは、太田あきひろです。
1月4日、5日、東日本大震災の被災地に入り、復興に向けた現地の要望を受けました。4日は福島県相馬市の災害公営住宅(被災地で最も早く完成)と港湾の整備状況を視察。5日は、ガレキ処理などで悩んできた石巻市で市街地の復旧・復興の状況と要望を亀山紘市長から受け、南三陸町の鉄骨がむき出したままの防災対策庁舎で佐藤仁町長から「津波警報を早く正確に」との要望を受けた後に町づくりを視察。さらにJR気仙沼線の線路跡地を走行するBRT(バス)の運行の現場視察。またカツオの水揚げや地盤の嵩上げに私自身動いてきた気仙沼漁港では、菅原茂市長や佐藤亮介組合長から現状の説明と要望を受けました。その間、村井嘉浩宮城県知事と懇談、意見交換を行いました。
「復興元年は昨年。今年は復興実感の年に」「各市町村にはそれぞれ異なった課題がある。街づくりであったり、災害公営住宅であったり、地盤の嵩上げであったり、職人がいなくて入札不調になったり、鉄道やBRTの交通であったり。それぞれのネックを打ち破ってほしい」ーー。このことを痛感し、復興を持続的かつ積極的に行うことを表明しました。
現場を推進する国交大臣としての責任は重く、しっかり頑張ります。
新しい年を迎えました。
日本再建をかけた重要な年です。皆様の真心を全身で受け止め、全力で走り抜く決意です。地域のためにも働きます。本年一年、何卒よろしくお願いいたします。
何よりも景気・経済の再建――。国力といっても、社会保障といっても、まず景気・経済の再建が大事です。円高・デフレを脱却し、細ってきている企業の基礎体力を回復させ、中小企業が元気になる施策を総動員させます。
防災・減災ニューディール。「脆弱国土を誰が守るか」――私はその責を担うため、東日本大震災の復興に力を注ぐとともに、大地震や災害への備えを図ります。本格的な「防災・減災元年」です。
外交の再建、社会保障の再建(持続性の確保)、危機管理体制の再建・確立など、全方位的に結束して頑張ります。
本年が皆様にとって良き一年でありますよう心よりお祈りいたします。
しっかり頑張ります。