 昨日22日は、「やり続ける政治家」の大切さを、改めて教えていただく再会がありました。
昨日22日は、「やり続ける政治家」の大切さを、改めて教えていただく再会がありました。
ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会の竪山勲事務局長、全国ハンセン病療養所入居者協議会の神美知宏会長など代表の皆さんから、国立ハンセン病療養所の職員増員について要請をいただきました。
全国の療養所入居者は、現在、平均年齢が82.1歳。介護が必要な方が多くなっています。しかも、重度の合併症から、自由に物を持つことができず、例えば食事でも、一人で食べるとなると、口を直接、食器に運ばなければ食べられない方も多くいるそうです。それによって、食べ物が誤って気管などに入り、肺炎を引き起こして、多くの方が亡くなっていると伺いました。
この原因は、政府の国家公務員削減方針です。それによって、療養所の職員も削減されていく流れにあります。皆さんの訴えは、「ハンセン病療養所だけは除外してほしい」との悲痛な叫びでした。
私は2001年5月、ハンセン病訴訟熊本地裁判決で国が敗訴したことを受け、小泉首相に控訴断念を要請しました。特に、坂口厚生労働大臣(当時)の奮闘もあり、国は控訴断念を決定。さらに、ハンセン病への取り組みを反省する趣旨を含めた国会決議の取りまとめにも、尽力しました。
あの日から11年、政治が"液状化"している今という時にあって、再び私を頼りにしてくださったことに、使命感と大きな責任を感じ、私は「問題解決に、信念をもって取り組み続けます」とお応えしました。
薬害肝炎問題しかり。学校耐震化しかり。児童手当の拡充しかり。私がライフワークとして取り組んできた仕事は、多くあります。最初は大変でした。薬害肝炎問題も、厚労省は「一律救済は莫大な財源が必要」と、全面解決に消極的でした。しかし私たちは、原告団、弁護団と一体になって主張し続けました。
何が、その原動力となったか。私は、「代理役」としての責任感だったのではないかと思います。代理として、ご本人たちの心情に肉薄すればするほど、途中で投げ出せるはずがありません。「やり続ける」といっても、その内容は、連日ニュースで取り上げられるような性質のものとは、まったく違います。たいていは光の当たっていない世界のこと。パフォーマンスの政治家から見れば、地味で、目立たなくて、まったく関心のないことばかりでしょう。
しかし、それでは何のための「代議士」なのでしょうか。
「国民の声を代弁して、国政を議論する」──大局観に立つことと同時に、声なき声を政治に反映させてこそ、私は政治家だと信じています。
「一人を大切に」──この当たり前のようで当たり前になっていないことを、当たり前にしていきたいと、いっそう決意しています。
■私のレポートと、竪山勲事務局長からの応援メッセージの動画を、Youtubeチャンネルでご紹介しています。ぜひご覧ください。
≫ビデオメッセージ@国立ハンセン病療養所職員増員要請
先日、うれしいお話を伺いましたので、我がことで恐縮なのですが、ご紹介させていただきます。
先日、私の支持者のAさんのもとへ、東京12区地域にお住まいの友人Bさんから"個人的に会いたい"とのご連絡があったそうです。
会うなりBさんは、Aさんに、こう話されたそうです。
「実は3年前、私は太田さんに入れなかった。ごめんなさい」
Bさんは涙ながらに語られたそうです。しかもBさんは、東北の被災地で、私と会ったとのこと。Aさんは驚きました。 聞けば、ご主人のご両親が、東日本大震災で被災し、体育館に避難していた折、そこを訪れていた私を、ちょうどBさんは目にしたそうです。
聞けば、ご主人のご両親が、東日本大震災で被災し、体育館に避難していた折、そこを訪れていた私を、ちょうどBさんは目にしたそうです。
"議員でもないのに、一生懸命、避難所の人たちを励まして、働いている姿を見て、涙が止まらなかった。両親からも「あなたの地元でしょ。あんな人を落としてはいけない」と言われ、今度は必ず応援することを、あなたに伝えたかった"
このようなお話だったそうです。
私は、このエピソードを伺って、心の底から感動しました。そして、「行動ほど雄弁なものはない」と改めて思い知りました。
3・11以降、私は十数度にわたって被災地を訪れ、現場の悲鳴を聞き、それを体当たりで政治に反映させてきました。気仙沼ではカツオの水揚げ復活を支援したり、石巻では被災者の短期滞在用に大型客船を誘致したりと、お役に立てた仕事は数多くあります。
しかし、現場の悲鳴が今なお耳に残って消えぬ私にとっては、それも、まだまだ、やりたいこと、やるべきことの万分の一でしかありません。政府・与党の無関心・無策ぶりに、「もっと早く! もっと鋭く! もっと温かく!」と歯ぎしりしてきた日々を思う時、「いよいよ!」との闘志が湧き上がってきます。
「心」を動かすものは、「心」しかありません。そして、政治は、救いを求めている人のためにあります。だから私は、涙や汗から震える「心」を感じるために、現場に行き、人と会います。揺さぶられた自分の「心」が、共に怒り、共に泣き、それが言葉となり、行動となります。"視察"などと気取って「頑張ってください」と言うのが政治家の仕事ではなく、「私が頑張ります」──これが政治家の責任ではないでしょうか。
「行動ほど雄弁なものはない」
だからこそ「政治は結果」だと、私は信じます。
■気仙沼や石巻での取り組みについては、「ピックアップレポート」もご覧ください。
≫NO.1 被災地にカツオが戻った!復興から再建へ 突破口を開く
≫NO.4 被災者を癒やすため 石巻港に短期滞在用の大型客船を!
 いよいよ本日、衆議院が解散しました。解散から12月16日の投票日まで、ちょうど30日間──まさに短期決戦です。全力で走り抜いてまいります。
いよいよ本日、衆議院が解散しました。解散から12月16日の投票日まで、ちょうど30日間──まさに短期決戦です。全力で走り抜いてまいります。
この衆院選、私は3つの点が問われていると思います。
1点目は、「民主党政権の3年間、日本は、前進したのか、後退したのか」です。
マニフェストは総崩れで"サギフェスト"だったことが明らかとなりました。外交・安全保障も、日米関係をはじめ迷走、東日本大震災の復旧・復興も、遅い、鈍い、心がない。迷走した民主党に、政権担当能力がなかったことは明白です。
2点目は、「日本再建を担うことができるのは、誰か」です。
特に、景気・経済対策は待ったなしです。しかし、民主党は、円高・デフレ対策しかり、雇用対策しかり、まったくの無策。企業の体力は弱り、中小企業、商店街からは悲鳴が上がっています。日本経済を壊した張本人に、日本再建を担うことなど、できるわけがありません。
3点目は、「国民の生活に根を張り、現場の声を政治に反映できるのは、誰か」です。
全国にわたって、地域に、しっかりとした目と耳を持っていなければ、生活者第一の政治は実現できません。「一度やらせてみよう」は、もう、民主党だけでコリゴリ。政治は結果──実際に、何を、どうしたのか、が厳しく問われねばなりません。
思えば、21世紀になって、名目GDPや税収が最も高く、株価も最高値となったのは、2007年、安倍内閣の時。当時、私は与党の代表として、政治の中核を担っておりました。あのリーマン・ショックの後も、エコポイント制度の導入などを実現し、景気を回復傾向に向けることができました。
私は、「金融政策」「防災・減災ニューディールなどの財政政策」「産業支援政策」を総動員して、雇用を生み出し、必ずや景気を回復させます。
国難ともいうべき今、「日本再建」のために、太田あきひろは、我が身をなげうって働いてまいります。
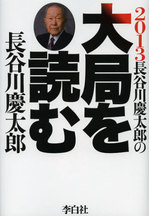 「シェールガス革命は、エネルギーだけでなく、世界の農業、安全保障など多くの分野を一変させる」
「シェールガス革命は、エネルギーだけでなく、世界の農業、安全保障など多くの分野を一変させる」
「中国は混乱状況に入る。人民解放軍は、機が熟するのを待てばいいと、柔軟路線に転換している」
「経済が失速しているBRICs、なかでもロシア経済は悪化する」
「ユーロは10年混乱するが、危機は続いても崩壊しない」
「"自由"のロムニーが、"公平"のオバマに勝つ」
「シェール革命はデフレに拍車をかけ、世界的に物価や労働賃金を引き下げる」
「日本のデフレは深化し、賃下げ時代、牛丼100円時代に向かい、トヨタも落日のパナソニック、ソニーの後を追う」
「日本でもメタンハイドレードがエネルギー革命を起こす」・・・・・・。
CDでは「オスプレイー配備の意味」などを語っている。まさに大局を大胆に語っている。
 10日、11日の土日、野球、サッカー、ソフトボール、アクアスロン大会など多くのスポーツ行事、華道、茶道、舞踊大会などの文化行事などが行われました。私も合唱に加わったりしました。
10日、11日の土日、野球、サッカー、ソフトボール、アクアスロン大会など多くのスポーツ行事、華道、茶道、舞踊大会などの文化行事などが行われました。私も合唱に加わったりしました。
先日来、私たちに野菜、果物、花などを提供してくれる東京各市場まつりが連続して行われ、地元の北足立市場(10/21)や板橋市場(10/28)、豊島市場まつりに参加しました。豊かな「食」は生活・文化の基本。「食育」という言葉もかなり定着。安全・安心の「食」の提供がスムーズに活発に行われることはとても大事です。 今年の市場まつりでは、どの会場にも福島のブースが設けられ、福島県庁からの職員も来て、「全て検査をしています。流通されているものは全て安全。おいしいです」と訴えていました。今年3月に佐藤雄平福島県知事にお会いした際、「風評も心配だが、これからは風化も心配」と言っていました。大変ななかで頑張っている人を応援する――全てに通じる大切なことだと思います。
今年の市場まつりでは、どの会場にも福島のブースが設けられ、福島県庁からの職員も来て、「全て検査をしています。流通されているものは全て安全。おいしいです」と訴えていました。今年3月に佐藤雄平福島県知事にお会いした際、「風評も心配だが、これからは風化も心配」と言っていました。大変ななかで頑張っている人を応援する――全てに通じる大切なことだと思います。
頑張ります。

