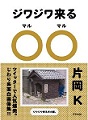 ネッ
トに投稿された作者不詳の面白写真集。エッと思うもの、つい吹き出してしまうもの、偶然もあるだろうし、ギャグもある。たしかに「思わず二度見しちゃう面
白画像集」だ。わからない、何だろうと思いつつ、絶妙なキャプションで救われたりもする。動物は面白いし、可愛いし、たしかに癒しだ。よくぞ集めてくれ
た
ネッ
トに投稿された作者不詳の面白写真集。エッと思うもの、つい吹き出してしまうもの、偶然もあるだろうし、ギャグもある。たしかに「思わず二度見しちゃう面
白画像集」だ。わからない、何だろうと思いつつ、絶妙なキャプションで救われたりもする。動物は面白いし、可愛いし、たしかに癒しだ。よくぞ集めてくれ
た
 リッ
キービジネスソリューションを立ち上げて活躍している渋谷さんの近著。ノウハウ本は多いが、経営者の心理、交流・信頼の拡大、関係作りの実践的ポイントを
分析している良書。「自尊心」「自由・独立」「強み」「志」「社会貢献」などの経営者の基本心理を分析しつつ、「感謝」「人脈」「縁」「好かれる人」など
を説く。要は、人間学であり、私流に言えば、自らの人間を創り、「人と人との間」である人間関係を創る。積極的に意欲を持って。挿入されるコラムも面白
い。渋谷さんの意欲と経験が語られ説得力を増している
リッ
キービジネスソリューションを立ち上げて活躍している渋谷さんの近著。ノウハウ本は多いが、経営者の心理、交流・信頼の拡大、関係作りの実践的ポイントを
分析している良書。「自尊心」「自由・独立」「強み」「志」「社会貢献」などの経営者の基本心理を分析しつつ、「感謝」「人脈」「縁」「好かれる人」など
を説く。要は、人間学であり、私流に言えば、自らの人間を創り、「人と人との間」である人間関係を創る。積極的に意欲を持って。挿入されるコラムも面白
い。渋谷さんの意欲と経験が語られ説得力を増している
 「少子化と財政難を克服する条件」「成長なくして幸福なし」と副題にある。デフレ不況問題、財政難問題、国の債務残高問題、少子化問題の四重苦。それに今、未曾有の大震災・原発事故が加わった日本――。四重苦はしかも、1つを解決しようとすると他が悪化するという矛盾対立が絡み合う。
「少子化と財政難を克服する条件」「成長なくして幸福なし」と副題にある。デフレ不況問題、財政難問題、国の債務残高問題、少子化問題の四重苦。それに今、未曾有の大震災・原発事故が加わった日本――。四重苦はしかも、1つを解決しようとすると他が悪化するという矛盾対立が絡み合う。
「政治主導とムダの削減で成長?」「失われた20年の要因――生産性低迷説・行財政改革不徹底説・消費飽和説・民間の資金需要減退説・バランスシート不況説・不良債権処理の遅れ・日銀真犯人説?」など、あらゆる論点を鋭く分析する。そのなかで、プラザ合意以来の円高の桎梏について強調しているのが目立つ。
「一 時的な国債の増発をともなう財政の拡大と金融の量的緩和で一定の成長軌道を確立する。タイミングをはかり、消費税を引き上げて税収基盤を整え、国債依存を 減らしていく。その間、拡大した財政基盤のなかから積極的な未来への投資を展開していく。そうすることで、債務残高問題を本質的に悪化させることなくデフ レ不況と財政難を克服し、少子化を緩和して、将来への希望を確かなものにしていく」ことを例証をあげつつ提示する。
太田あきひろです。
円高がさらに進行。19日夜には円相場が一時、75円95銭となり、戦後最高値を更新しました。欧米の財政不安、世界経済の先行き不安が強まったことによるものですが、事態は深刻。大企業・中小企業と懇談しても、「円高、電力不足、政治の混迷の3つだけは、とにかく何とかしてほしい」との悲鳴。被災地では、「現場の気持ちが全く政権はわかってない」との怒りの声。「遅い、にぶい、心がない」というあきれ果てた民主党政権への批判。いずれの現場も「ポスト管は誰か」どころではない。大変な状況です。
円高については、いつも思うのは傍観しているかのような政府・日銀の後手・後手。しかし、世界経済はリーマン・ショックからちょうど3年。欧州、米国、日本、中国それぞれが、国際金融危機の後遺症をひきずりながら国際金融危機の第二幕に突入したという巨視的な構造認識に立つことが大切だと思います。各国に共通するのは、政治の混迷、政策の手詰まり、為替切り下げ競争、そして世界同時株安です。
市場介入や追加の金融緩和策を早急に進めるべきことは当然ながら、日本のデフレ・財政難・少子化問題、そして大震災を踏まえたうえでの積極的な経済戦略が不可欠です。
スピードも戦略も弱すぎる今の日本、これを打開しなければなりません。頑張ります。
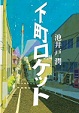 ロ
ケットエンジンの開発に携わっていた佃航平は、打ち上げ失敗の責任をかぶって辞職、父親が創業した町工場を引き継ぐ。その世界最先端のエンジン特許がなけ
ればロケットは飛ばない。大企業は焦る。町工場の技術、プライド、意地と夢、生き残りをかけた戦い、大企業などとの攻防が描かれる。つぶしにかかる敵対す
る人たちは、あまりに図式的・劇画的ではあるが、佃を支える人が心を一つにして、ついにロケットは打ち上げられる。痛快。
ロ
ケットエンジンの開発に携わっていた佃航平は、打ち上げ失敗の責任をかぶって辞職、父親が創業した町工場を引き継ぐ。その世界最先端のエンジン特許がなけ
ればロケットは飛ばない。大企業は焦る。町工場の技術、プライド、意地と夢、生き残りをかけた戦い、大企業などとの攻防が描かれる。つぶしにかかる敵対す
る人たちは、あまりに図式的・劇画的ではあるが、佃を支える人が心を一つにして、ついにロケットは打ち上げられる。痛快。

