 「危険な原発はいらない」という京大原子炉実験所助教の小出さんの近著。東日本大震災の原発事故――外部からの送電も非常用発電機も使えない「ブラックア
ウト」、「崩壊熱によるメルトダウン」「今も心配な高温・不安定な3号機など」「たまる汚染水」「水棺方式と水素爆発懸念のチグハグ」「放射能汚
染」......。次々と警鐘を鳴らす。
「危険な原発はいらない」という京大原子炉実験所助教の小出さんの近著。東日本大震災の原発事故――外部からの送電も非常用発電機も使えない「ブラックア
ウト」、「崩壊熱によるメルトダウン」「今も心配な高温・不安定な3号機など」「たまる汚染水」「水棺方式と水素爆発懸念のチグハグ」「放射能汚
染」......。次々と警鐘を鳴らす。
 原発事故についてNHKで解説し続けている水野・山崎さんらの緊急出版。「何が起きているかわからない」――こうした国民のいらだちを共有しながら格闘
していた3人に、私が感じていたのは「誠実」ということ、「わかりやすく」ということ、そして「イデオロギーではなく現場」ということだ。今日の事故につ
いて現時点でいえること、問題点が整理される。「福島第一原発で何が起きたのか?(山崎さん)」「日本はどうして原発を進めたのか?(水野さん)」「放射
線の健康への影響は?(藤原さん)」そして「これからの原発はどうなるのか?(日本の今後のエネルギー政策)」を扱ってくれている。原発・エネルギーをめ
ぐる問題について、本書は最もわかりやすい。
原発事故についてNHKで解説し続けている水野・山崎さんらの緊急出版。「何が起きているかわからない」――こうした国民のいらだちを共有しながら格闘
していた3人に、私が感じていたのは「誠実」ということ、「わかりやすく」ということ、そして「イデオロギーではなく現場」ということだ。今日の事故につ
いて現時点でいえること、問題点が整理される。「福島第一原発で何が起きたのか?(山崎さん)」「日本はどうして原発を進めたのか?(水野さん)」「放射
線の健康への影響は?(藤原さん)」そして「これからの原発はどうなるのか?(日本の今後のエネルギー政策)」を扱ってくれている。原発・エネルギーをめ
ぐる問題について、本書は最もわかりやすい。
 朝日新聞の記者・奥山俊宏さんが、東電本店において3.11から50日間の克明な取材・記録。断片的にしか報道されなかった会見での一部始終。混乱、危
機とあせり、試行錯誤、情報の不足、そのなかでの決断。――貴重な記録だが、そのなかに「なぜ備えを怠ったか」「電源喪失のような危機の兆しはこれまでも
あったではないか」――小事を大事としなかった背景にあるもの。それが原発・エネルギー問題として浮き彫りにされる。
朝日新聞の記者・奥山俊宏さんが、東電本店において3.11から50日間の克明な取材・記録。断片的にしか報道されなかった会見での一部始終。混乱、危
機とあせり、試行錯誤、情報の不足、そのなかでの決断。――貴重な記録だが、そのなかに「なぜ備えを怠ったか」「電源喪失のような危機の兆しはこれまでも
あったではないか」――小事を大事としなかった背景にあるもの。それが原発・エネルギー問題として浮き彫りにされる。
太田あきひろです。
本日 21日、坂口元厚生大臣とともに、東京北社会保険病院を訪れ、先日成立した「改正年金・健康保険福祉施設整理機構法」の報告とともに、更に地域のために貢献できるよう連携を約しました。この法案は「病院が存続できるように、委託という形でも続けられる」ように公明党が主導して成立させたもの。
私と坂口元大臣が、昨年夏以降、進展のなかった社会保険病院の存続問題で、公明党が主導し、改正法をまとめた経緯を紹介。さらに、社会保険病院は、地域医療推進機構という枠組みに入るが、個々の病院の特色は残し、存続可能となったことを説明しました。病院側からは公明党の尽力に感謝の言葉があり、産科・小児科をはじめ地域医療への取り組み強化が話されました。
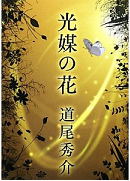 六つの短編(六章)それぞれ別だが、人物や心象はつながっている。子ども、兄妹、姉弟、親子、昆虫、草花、夕暮れ、光、悲哀、沈潜する思い
出......。第一章から徐々に旋律が高まり、「冬の蝶」「春の蝶」でヤマを迎えるような感がする。息苦しいほどに心に迫ってくる小説だが、最終第六章
「遠い光」で、解き放たれて安堵する。運命に翻弄されながら「風が吹くのを待つ"風媒花"」のような心に影をもつ人々が、ちょっとしたことで前へ進む小さ
な光を見出す。「この全六章を書けただけでも、僕は作家になってよかったと思います」と道尾さんは語っているが、そうだろうなと思う。優しさが広がる作品
だ。
六つの短編(六章)それぞれ別だが、人物や心象はつながっている。子ども、兄妹、姉弟、親子、昆虫、草花、夕暮れ、光、悲哀、沈潜する思い
出......。第一章から徐々に旋律が高まり、「冬の蝶」「春の蝶」でヤマを迎えるような感がする。息苦しいほどに心に迫ってくる小説だが、最終第六章
「遠い光」で、解き放たれて安堵する。運命に翻弄されながら「風が吹くのを待つ"風媒花"」のような心に影をもつ人々が、ちょっとしたことで前へ進む小さ
な光を見出す。「この全六章を書けただけでも、僕は作家になってよかったと思います」と道尾さんは語っているが、そうだろうなと思う。優しさが広がる作品
だ。

