北島康介、福原愛、魁皇、乙武洋匡、さかなクン、山崎直子、ベッキー、広瀬章人、大日方邦子、吉田沙保里......。子どもゆめ基金10周年を記念して、各分野で活躍している30名とのインタビュー。
子どもの頃、個性あるゆえか仲間はずれにされたり、悩んだり......。しかし、「好きなものを見つける努力」「夢をさがす」「もうやめたいと思ってもやり続ける」「厳しい練習を乗り越えてきたことが、自分の自信となった」などと語る。今の若者は伸びる。自由度も大。
太田あきひろです。
9月4日、各町会・自治会で早朝より防災訓練が行われました。いずれも例年より多くの人が参加し、震災を意識しての新たな取り組みも交えた、充実した訓練となりました。消火や救命、AED、避難場所の心得、緊急時の連絡方法、震度7の体験、地元消防団との一体的な活動など、工夫がこらされていました。一人暮らし、高齢者も多く、人と人との結びつき自体が貴重です。
地域の安全、地域の安心、地域の元気のために頑張ります。
 東
野圭吾の加賀恭一郎シリーズ。なじみの地域なので想像力がかきたてられる。日本橋の欄干にもたれかかった男に突き刺さったナイフ。ていねいに、ささいなこ
とから感情をもたどって事件の真相に迫る加賀。東野さんの小説はだんだんシンプルに人がやさしくなっていくように思う。「麒麟の翼」は親父のかなしさか。
東
野圭吾の加賀恭一郎シリーズ。なじみの地域なので想像力がかきたてられる。日本橋の欄干にもたれかかった男に突き刺さったナイフ。ていねいに、ささいなこ
とから感情をもたどって事件の真相に迫る加賀。東野さんの小説はだんだんシンプルに人がやさしくなっていくように思う。「麒麟の翼」は親父のかなしさか。
太田あきひろです。
今日、9月1日は防災の日。「鳥の目の防災」と「虫の目の防災」が大事です。今日9時から10分間、東京では環7の内側に入る車をストップさせる訓練が行われ、4日には各町会・自治会ごとに防災訓練が行われ、3・11を受け、昨年までとは違う工夫がされています。
"鳥の目"の防災――。
東京湾北部地震、三浦半島断層帯地震、大阪・上町断層帯地震、東海・東南海・南海の3連動地震をはじめとして、各地で対応は異なり、しっかりした対応をしなければなりません。
特に津波か倒壊・火災か――は大前提です。
東京湾北部地震の場合は、M7.3、冬、18時、風速15m/sの場合、「建物の全壊・焼失85万棟」「死者数約11000人、それも火災によるものが多い」という予測。東日本大震災の津波被害とは頭を切り替え、火災対策、建物の耐震化、救命ライフライン(私の京大土木耐震研究室の主張した言葉)に力を注がなければなりません。
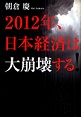 「日
本経済と世界経済がいかに危機的状況か」「金融市場で高速取引をするコンピューターがいかに資本市場を支配しているか」「上昇を続ける商品価格とインフ
レ」「リーマン・ショック後の世界中でバラ撒かれたマネーは、各国の国債市場の大暴落をもたらす」「米国・EU・中国の思惑と弱点」などを示しつつ、2012年、世界経済の大崩壊の危機を指摘している。
「日
本経済と世界経済がいかに危機的状況か」「金融市場で高速取引をするコンピューターがいかに資本市場を支配しているか」「上昇を続ける商品価格とインフ
レ」「リーマン・ショック後の世界中でバラ撒かれたマネーは、各国の国債市場の大暴落をもたらす」「米国・EU・中国の思惑と弱点」などを示しつつ、2012年、世界経済の大崩壊の危機を指摘している。
各国の思惑、ヘッジファンド、格付け会社など、市場における裏面にふれつつ、警告する。

