今年の「私の3冊」が23日付の公明新聞に掲載されました。
私は以下の3冊をあげました。意を尽くすため若干加えて掲載します。
●「レオナルド・ダ・ヴィンチ(上・下)」
ウォルター・アイザックソン 著 土方奈美 訳 文芸春秋 各2200円
●「日本史に学ぶマネーの論理」
飯田泰之 著 PHP研究所 1600円
●「八本目の槍」
今村翔吾 著 新潮社 1800円
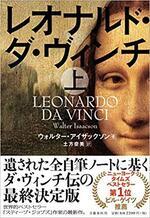
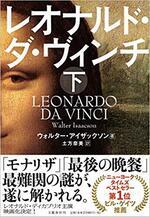 今年はレオナルド・ダ・ヴィンチ没後500年――。遺された「記録魔ダ・ヴィンチ」の全7200枚の自筆ノートを基にして、ウォルター・アイザックソンが挑んだ力作が「レオナルド・ダ・ヴィンチ」だ。レオナルドが画家としてだけでなく、建築、数学、解剖学、動植物学、光学、天文学、物理学、水力工学等々に、とてつもない業績を残したことは名高い。しかし、「レオナルドを安易に天才と呼ぶべきではない」という。旺盛な好奇心を原動力に、果てしない驚きと向き合い、全方位・全分野を論理的・実証的に探究し続けた創造的人間であったことを描く。哲学不在、人間としての深さが欠落する現代。森羅万象、宇宙と人間の本質に迫り続けたレオナルドの人物に接する意味は大きい。
今年はレオナルド・ダ・ヴィンチ没後500年――。遺された「記録魔ダ・ヴィンチ」の全7200枚の自筆ノートを基にして、ウォルター・アイザックソンが挑んだ力作が「レオナルド・ダ・ヴィンチ」だ。レオナルドが画家としてだけでなく、建築、数学、解剖学、動植物学、光学、天文学、物理学、水力工学等々に、とてつもない業績を残したことは名高い。しかし、「レオナルドを安易に天才と呼ぶべきではない」という。旺盛な好奇心を原動力に、果てしない驚きと向き合い、全方位・全分野を論理的・実証的に探究し続けた創造的人間であったことを描く。哲学不在、人間としての深さが欠落する現代。森羅万象、宇宙と人間の本質に迫り続けたレオナルドの人物に接する意味は大きい。
 いよいよ人口減少・少子高齢化の大きな坂にさしかかる。人生100年時代、社会保障を考えるにしても、「経済」「財政」を考えなければならない。加えて「金融」「電子・暗号通貨の流通」「キャッシュレス化」が話題となる新時代。飯田泰之氏の「日本史に学ぶマネーの論理」は、あらためて経済・財政の基となる「貨幣とは何か」を問い直す。しかもそれを歴史から経済的な知見を導き検証する。政府発行の貨幣の強みは「納税に使えること」であり、政府発行益を手にできるのだが、「政府負債、名目貨幣、循環論法」の3つを重要な要素として示す。現在の「経済」「金融・財政政策」「仮想通貨」の本質を突いている。
いよいよ人口減少・少子高齢化の大きな坂にさしかかる。人生100年時代、社会保障を考えるにしても、「経済」「財政」を考えなければならない。加えて「金融」「電子・暗号通貨の流通」「キャッシュレス化」が話題となる新時代。飯田泰之氏の「日本史に学ぶマネーの論理」は、あらためて経済・財政の基となる「貨幣とは何か」を問い直す。しかもそれを歴史から経済的な知見を導き検証する。政府発行の貨幣の強みは「納税に使えること」であり、政府発行益を手にできるのだが、「政府負債、名目貨幣、循環論法」の3つを重要な要素として示す。現在の「経済」「金融・財政政策」「仮想通貨」の本質を突いている。
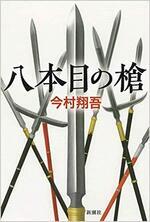 「八本目の槍」(今村翔吾)は、「石田三成の魅力と凄さ」「関ケ原で秀吉の小姓衆はなぜ敵味方に分かれたか」の謎を解き明かす。本能寺の変の後の天正11年(1583年)4月、羽柴秀吉が柴田勝家と雌雄を決した賤ヶ岳の戦い。華々しい活躍をした秀吉の小姓衆の殊勲者7人は、「賤ヶ岳7本槍」と呼ばれるようになった。加藤虎之助、福島市松、脇坂甚内らであり、もう一人、同年代の小姓衆の仲間に桁違いの知力をもち、秀吉の信を得た男がいた。石田佐吉である。1600年の関ケ原、賤ヶ岳7本槍は東軍・西軍に分かれて戦う。しかしこの7人の胸中には「豊臣家」があり、「厳しいことも言い争うことができた8人の仲間」があり、とりわけ「佐吉の言っていたことの深さと情、眩しいほどの生き方を曲げない姿勢」が心の芯にあったのだった。
「八本目の槍」(今村翔吾)は、「石田三成の魅力と凄さ」「関ケ原で秀吉の小姓衆はなぜ敵味方に分かれたか」の謎を解き明かす。本能寺の変の後の天正11年(1583年)4月、羽柴秀吉が柴田勝家と雌雄を決した賤ヶ岳の戦い。華々しい活躍をした秀吉の小姓衆の殊勲者7人は、「賤ヶ岳7本槍」と呼ばれるようになった。加藤虎之助、福島市松、脇坂甚内らであり、もう一人、同年代の小姓衆の仲間に桁違いの知力をもち、秀吉の信を得た男がいた。石田佐吉である。1600年の関ケ原、賤ヶ岳7本槍は東軍・西軍に分かれて戦う。しかしこの7人の胸中には「豊臣家」があり、「厳しいことも言い争うことができた8人の仲間」があり、とりわけ「佐吉の言っていたことの深さと情、眩しいほどの生き方を曲げない姿勢」が心の芯にあったのだった。
 「日本史を学ぶことは、日本人とは何かを考えることだと思う」と本郷さんはいい、「私は井の中の蛙だと思う」という。本書は日本人と「この国のカタチ」が二人の間で自由闊達に論じられる。なんと、日本史をどうとらえるのかの、東西のバトルが行われているのだ。京都史観と関東史観。「ひらたく言えば、京都が拠点となる朝廷の威光を大きくえがこうとする。朝廷をとりまく公家や寺社の存在感を特筆する。7、8世紀にできた律令のしくみが、のちのちまで社会を左右したという見方の京都史観」と「律令等の秩序をくずしていく新しい勢力に光を当てる。武士の革新性を輝かしくとらえてきた見方の関東史観」だ。権門体制論、東国国家論、顕密体制論等の「日本のかたち」が紹介され、京都における「女官の色香、誘惑」も歴史に影響を与えたのではないかとまで語る。
「日本史を学ぶことは、日本人とは何かを考えることだと思う」と本郷さんはいい、「私は井の中の蛙だと思う」という。本書は日本人と「この国のカタチ」が二人の間で自由闊達に論じられる。なんと、日本史をどうとらえるのかの、東西のバトルが行われているのだ。京都史観と関東史観。「ひらたく言えば、京都が拠点となる朝廷の威光を大きくえがこうとする。朝廷をとりまく公家や寺社の存在感を特筆する。7、8世紀にできた律令のしくみが、のちのちまで社会を左右したという見方の京都史観」と「律令等の秩序をくずしていく新しい勢力に光を当てる。武士の革新性を輝かしくとらえてきた見方の関東史観」だ。権門体制論、東国国家論、顕密体制論等の「日本のかたち」が紹介され、京都における「女官の色香、誘惑」も歴史に影響を与えたのではないかとまで語る。
「ここだけの話(日本に古代はない、皇国史観の亡霊)」の序からバトルが始まる。「神話と統治(天皇家の存続と神話、伊勢神宮と鈴木姓が多い理由)」「祭り上げの政治技術(摂関政治は不安定だった、官僚主導=摂関政治と官邸主導=院政、幻の関東独立国)」「武士と武芸の源流(源氏・平氏は傭兵集団、在地領主の誕生、武家と公家の埋められない差、女官の誘惑)」「『日本国』意識(日本人意識の芽生え、元寇に抗した武士と日本のまとまり、東国国家論では天皇と将軍は並び立つ)」「絶対王政・室町幕府(室町幕府はゼニカネの政権、日野富子とその一族と義政、寺は租税回避地だった!?、禅寺は観光ホテル)」「朝廷は下剋上で輝く(戦国大名は京都の律令制と訣別し自分の力で土地を支配、貴族は文化で延命する、信長は朝廷を滅ぼそうとしたか、秀吉・家康は朝廷をどう見たか)」「鎖国と米本位制(銭本位制から米本位制へ、幕府の貴穀賤金、家康は鎖国的でもなかった、寺社が資本主義の抜け道)」「明治維新はブルジョワ革命だった(倒幕の軍資金は三井等から、大坂商人の腹積もり、奇兵隊のスポンサー下関の豪商、天皇の絶対性は方便だったか、平和な明治維新というウソ・流血革命)」「日本人と天皇(権威と権力、象徴天皇制=天皇機関説!?)」・・・・・・。
自由闊達できわめて面白い。
 歴史はどうしても勝者の歴史となる。西欧史が世界の主流として分析され、そして東洋史は東アジア全体というより、中国と韓半島、そして日本史を我々は学ぶことになる。これまでの世界史だ。本書ではこれまでにない世界史が「世界史のミカタ」として語られる。特徴的なのは、中央アジアに蟠踞した遊牧民への視座。「中国史でも、ヨーロッパ史でもない、中央アジアの勢力を公平に評価する世界史のミカタ(中国史の研究者は黄河より内側の勢力争いに興味を寄せやすく、ヨーロッパ史の研究者は民主的なギリシアが専制的なペルシアをどうあしらったかといった視点で研究してきた)」「遊牧民は季節に応じた牧草を求めて移動するので、土地を与えられて主従関係を結ぶという封建制の関係が成り立ちにくい。・・・・・・土地が欲しい農耕社会、つまりユーラシア大陸の両端に封建的な世界が成立し、真ん中の草原が封建制と関係ない世界になる(梅棹忠夫)」わけだ。もう一つ、「世界史から見た日露戦争」「第一次世界大戦のインパクト」に象徴されるように、世界が大航海時代と産業革命を経て、相互に影響を与えて共振し、それに各国の戦略が加わって大変動をもたらすダイナミズムを語っていることだ。世界史の"共振のダイナミズム"といえようか。たしかに国家の枠を超えて「世界を見る力」を刺激的に開示してくれる。
歴史はどうしても勝者の歴史となる。西欧史が世界の主流として分析され、そして東洋史は東アジア全体というより、中国と韓半島、そして日本史を我々は学ぶことになる。これまでの世界史だ。本書ではこれまでにない世界史が「世界史のミカタ」として語られる。特徴的なのは、中央アジアに蟠踞した遊牧民への視座。「中国史でも、ヨーロッパ史でもない、中央アジアの勢力を公平に評価する世界史のミカタ(中国史の研究者は黄河より内側の勢力争いに興味を寄せやすく、ヨーロッパ史の研究者は民主的なギリシアが専制的なペルシアをどうあしらったかといった視点で研究してきた)」「遊牧民は季節に応じた牧草を求めて移動するので、土地を与えられて主従関係を結ぶという封建制の関係が成り立ちにくい。・・・・・・土地が欲しい農耕社会、つまりユーラシア大陸の両端に封建的な世界が成立し、真ん中の草原が封建制と関係ない世界になる(梅棹忠夫)」わけだ。もう一つ、「世界史から見た日露戦争」「第一次世界大戦のインパクト」に象徴されるように、世界が大航海時代と産業革命を経て、相互に影響を与えて共振し、それに各国の戦略が加わって大変動をもたらすダイナミズムを語っていることだ。世界史の"共振のダイナミズム"といえようか。たしかに国家の枠を超えて「世界を見る力」を刺激的に開示してくれる。
各章の対談は、大胆・率直だ。「神話の共通性(なぜ世界の神話は似ているか)(女装する英雄)」「世界史を変えた遊牧民(すべてはアレクサンドロスから始まった)(異民族に寛容だったローマ帝国)(遊牧民のインパクト)」「宗教誕生とイスラム世界の増殖(なぜ多神教から一神教が生まれたのか)(ローマ帝国にキリスト教が広まった理由)(貨幣経済と寄付社会)(教会がなければ統治できない王たち)」「中華帝国の本質(漢民族の王朝は漢、宋、明の三つしかない)(中国には内側で完結する強い内向性=中華意識)(中国の伝統にある文人の文化、人文的教養・文弱の中国)」「ヨーロッパの二段階拡大(大航海時代の"点の支配")(産業革命による"面の支配")」「明治維新とフランス革命の類似性(なぜ、ルイ16世は処刑されたか)(強烈な「日本」意識)」「システムとしての帝国主義(ビスマルクの深謀遠慮)(未熟なアメリカ外交)(世界史から見た日露戦争)」「第一次大戦のインパクト(帝国の解体)(日本にとっての第一次世界大戦)」「今も残るファシズムの亡霊(ムッソリーニが残した文化遺産)(ナポレオンとヒトラーの決定的違い)」「社会主義は敗北したか(社会主義はフランス革命から始まった)(平等の為に人は戦わない)(社会主義の闇)」「国民国家の次に来るもの(人間は何のために死ねるか)(日米英三国同盟)(すぐに降伏するイタリアは進んでいる)」・・・・・・。
世界の歴史を俯瞰する。自由自在に。
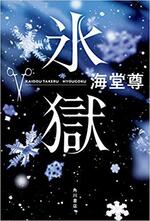 最新の心臓手術の最中に起きた前代未聞の殺人事件を描いた「チーム・バチスタの栄光」。それから13年ぶりに海堂尊が続編として出したのがこの「氷獄」。「バチスタ・スキャンダル」の裁判がいよいよ始まったという設定だ。
最新の心臓手術の最中に起きた前代未聞の殺人事件を描いた「チーム・バチスタの栄光」。それから13年ぶりに海堂尊が続編として出したのがこの「氷獄」。「バチスタ・スキャンダル」の裁判がいよいよ始まったという設定だ。
「バチスタ・スキャンダル」から2年。被疑者・氷室は黙秘を続け、弁護をも拒み続ける。しかも「保身の願望もない」と言うのだ。死刑に持ち込みたい検察もこれに手こずり、起訴の基本方針も決められないでいた。そこに国選弁護士として新人弁護士・日高正義が名乗りをあげる。しかし、意気込んで東京拘置所に行った日高に対して、氷室は「保身の願望もない」「ここは氷の牢獄。何をしても凍えるだけ」と虚無的態度に取り付く島がない。諦めない日高は、「チーム・バチスタの栄光」の田口医師やインテリ・ヤクザ、イヤミの白鳥技官らの話を聞き、ある提案を持ち掛ける。そして2人は、氷室の"死刑"と引き換えにしたそれぞれの闘いを始めるのだ。
日高正義の名前にもあるとおり、テーマは「医療と司法の正義を問う」だ。難しい生死の境に立つ医療現場、有罪率99.9%の検察司法の難しさと歪み――そうしたなかでの正義とは何か、医療過誤に苦しむ患者と医師の双方を助けるにはどうしたらいいのか。「『正義』とはできるだけ小さく使う方がよい。大きく使おうとすればするほど、か弱き人々を傷つける」「私が医師のミスを徹底的に叩くシステムを作った結果、誠実な医師のミスを糾弾し、潰してしまうことになった。だが今回、そんな医師を救えて、酷いシステムを手直しすることもできた」「『小さき正義』とは、悪の中にも棲息しているかもしれない。・・・・・・正しいものばかり集めたら、世界は息苦しくなり、潰れちゃう。だからバランスを取るためにわたしは極悪人でも誰も弁護を引き受けたがらないような人を引き受けることにしたの。世の中にはへそ曲がりが必要なのよ」・・・・・・。そういう意味では登場人物がいずれもキャラの立つ"へそ曲がり"だ。
本書は他に東城大学医学部付属病院を舞台とし、田口や白鳥らも登場する「双生」「星宿」「黎明」の3編がある。






