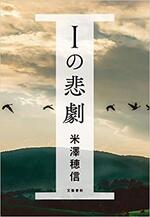 6年前に住民がいなくなった南はかま市の簑石という集落。この無人となった簑石に新しい定住者を募る市長肝いりの南はかま市Iターン支援推進プロジェクトが始まった。その「甦り課」を担うのは、さばけた新人・観山遊香、出世志向の真面目な公務員・万願寺邦和、やる気の全く見えない課長・西野秀嗣の3人。
6年前に住民がいなくなった南はかま市の簑石という集落。この無人となった簑石に新しい定住者を募る市長肝いりの南はかま市Iターン支援推進プロジェクトが始まった。その「甦り課」を担うのは、さばけた新人・観山遊香、出世志向の真面目な公務員・万願寺邦和、やる気の全く見えない課長・西野秀嗣の3人。
募集するやまず2世帯が移住する。しかし隣同士のトラブルで去っていく。次に10世帯が移住してくる。ところが、事業を起こそうとした稚鯉が突然消えたり、未就学児が迷子となり、防空壕に入って重い本の下敷きになったり、毒キノコの食中毒事件があったりと、次々と不可解な事件やトラブルが発生。ついに全員が去って再び無人となってしまう。話題を呼んだ「満願」を想起するミステリー連作短篇集だ。
しかし、この背景には村が消えていくという過疎化の深刻な現実がある。都市に住む者の地方への郷愁。自然への回帰。土地への愛着とは何か。一方で、人口急減の限界集落の深刻さ。夢だけでは田舎に住めない。仕事の問題もある。隣人とのトラブルもある。全ての生活インフラ整備にまで予算をかけられない地方行政の現実・・・・・・。本書は個々のトラブルが「Iの喜劇」であったことを終章で謎解きをするが、全体を覆うのは間違いなく「Iの悲劇」だ。
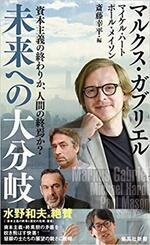 「資本主義の終わりか、人間の終焉か?」が副題。今を「未来への大分岐」と危機感をもって把える。斎藤幸平氏と「なぜ世界は存在しないのか」の哲学者マルクス・ガブリエルと新しい権力との対峙を社会運動のなかで模索する政治哲学者マイケル・ハート、ポストキャピタリズムを展開する経済ジャーナリスト・ポール・メイソンの3人との対談。きわめてラジカルな討論だ。しかし、世界的な経済低迷、国家負債の増大、気候変化と災害の激化、AI時代とGAFAの跳梁と支配、先進諸国における格差の拡大と貧困化、トランプ現象、民主主義の機能不全などをどう脱出するか。世界の「大分岐の時代」と把え、分析し、模索する。カール・マルクスの問いかけたものも語る。
「資本主義の終わりか、人間の終焉か?」が副題。今を「未来への大分岐」と危機感をもって把える。斎藤幸平氏と「なぜ世界は存在しないのか」の哲学者マルクス・ガブリエルと新しい権力との対峙を社会運動のなかで模索する政治哲学者マイケル・ハート、ポストキャピタリズムを展開する経済ジャーナリスト・ポール・メイソンの3人との対談。きわめてラジカルな討論だ。しかし、世界的な経済低迷、国家負債の増大、気候変化と災害の激化、AI時代とGAFAの跳梁と支配、先進諸国における格差の拡大と貧困化、トランプ現象、民主主義の機能不全などをどう脱出するか。世界の「大分岐の時代」と把え、分析し、模索する。カール・マルクスの問いかけたものも語る。
マイケル・ハートは「電力や水、知識や情報、自然や地球という環境そのものを<コモン>として資本の支配から取り戻し、自分たちで管理していく」「民主主義を危機から救い出すためには<コモン>を自分たちのものとして共同決定していく経験こそ鍵になる」「上からの社会変革ではなく、下からのコミュニズム。苦しみや欲求を分かち合う連帯によって新しい未来をつくる」という。マルクス・ガブリエルは「『ポスト真実』とは『客観的な事実』の危機であり、相対主義の時代であり、それは事実があるところで事実を見ないという民主主義にとって危険な考え方である」「フェイクがあふれ、プロパガンダがあふれ、客観的事実が軽視される社会となっている」「私たちが『人権』と呼ぶ普遍的価値の唯一の基盤が切り崩されてはならない」「新実在論で民主主義を取り戻す」「世界は存在しない、ユニコーンは存在する。人間の尊厳は現実にあらゆる人間に属しており、人権も存在する」「未来への大分岐――環境危機とサイバー独裁」「危機の時代の哲学、事実を真摯に受け止めて態度調整をするための哲学的土台を提供するのが新実在論。それは『ポスト真実』と相対主義に終止符を打つ宣言だ」という。ポール・メイソンは「資本主義は情報テクノロジーによって崩壊する。成長の鈍化と生産力の過剰、利潤率の低下は明白」「ポストキャピタリズムと労働。人間が強制労働そのものから解放される"可能性の世紀"に私たちはいる。持続可能な協同型経済の完成形がポストキャピタリズム。しかし、これに抵抗する資本の動きが市場独占、プラットフォーム資本主義、ブルシット・ジョブなどで顕著だ」「ポストキャピタリズムの未来に向け、独占の禁止、再生エネルギー100%の道、AIの暴走阻止への普遍的原理たるヒューマニズムの確立、利潤だけを追求するのではない下からの社会的協働の活発化」などを提唱する。
「メイソンやガブリエルは、非人間化に対抗して、『人間とは何か』をいうことを明らかにしながら、普遍的人権や普遍的価値を積極的に擁護するヒューマニズムの立場に移行している」と斎藤氏は語る。
 24日、2月に開幕した「東アジア文化都市2019豊島」の閉幕式典、レセプションが池袋のハレザ池袋で盛大に開催されました。
24日、2月に開幕した「東アジア文化都市2019豊島」の閉幕式典、レセプションが池袋のハレザ池袋で盛大に開催されました。
「東アジア文化都市2019豊島」は、日本・中国・韓国の3か国から1都市が選抜され、文化交流を行うものです。今年は日本の豊島区、中国の西安市、韓国の仁川広域市です。3都市による交流の成果の振り返りや3都市芸能団によるステージパフォーマンス、2020年開催都市(北九州市)への引継式などが行われました。
また、23日、24日の土日、地元では「自治会・町会のもちつき」「染井よしの桜のふる里 秋祭り」「連合町会の避難所開設訓練」「親子でチャレンジ飛鳥山」「北区少林寺拳法大会」「芋煮会」「北区陶芸展」「JAZZ IN 十条」など多数の行事があり、参加しました。
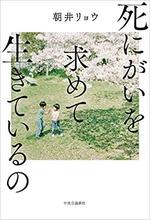 2019年、螺旋プロジェクトのなかの一作―。8組9名の作家陣が古代から未来までの日本を舞台に、「海族」と「山族」が対立するというテーマで描いた競作企画。この「死にがいを求めて生きているの」は朝井リョウ氏が「平成」を描く。
2019年、螺旋プロジェクトのなかの一作―。8組9名の作家陣が古代から未来までの日本を舞台に、「海族」と「山族」が対立するというテーマで描いた競作企画。この「死にがいを求めて生きているの」は朝井リョウ氏が「平成」を描く。
「逃げる中高年、欲望のない若者たち」といったのは村上龍だ。たしかに、昭和の時代までは「食べることに懸命」「生きることに必死」という時代だったが、平成の時代の「デフレ」「災害の頻発」「そこそこ幸せな日本」のなか、「生きがい」が語られるようになった。
本書は、性格の全く異なる親友2人の青年期の交わりが描かれる。堀北雄介と南水智也。周りを囲む坂本亜矢奈、前田一洋、安藤与志樹ら。堀北雄介は血気盛ん、対立をつくり注目を浴びることで存在を確認したい。「いつも手段と目的が逆転している」「喋って満足するだけのおままごとはもう終わり」「無理やりターゲットを見つけて、反発する理由をどうにか生み出して、対立構造作ってハブる。そうでもしないと生きがいがなくなっちゃう」「煙が上がるような摩擦がないと、自分がどこにいるか自分で確認できないあの感じ」――。平成はそれに抗して「ナンバーワンよりオンリーワン」といったが、「人間は、自分の物差しだけで自分自身を確認できるほど強くない」。全く堀北雄介とは逆の冷静で平衡感覚をもつ性格の智也も、雄介をなだめながらも自身の内に同種のものがあると思うのだ。
自分の存在を実感する。人と人、人と人の間としての人間。その存在の課題が微温的、デフレ社会の内に不安と不満をため込む。智也は今、植物状態、雄介はそれを献身的に見守る。そこにも存在を実感するための歪みがある。後半から最終章に至るまで緊迫感がいや増す。






