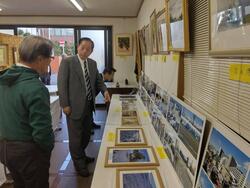「1973-74年に、『マルクスその可能性の中心』と『柳田国男試論』を書いた。いずれも文芸評論の延長として書いたものだが、それらの違いは大きかった」「『世界史の構造』(2010年)を書き終えたあと、私は急に、柳田国男について考えはじめたのである。それは一つには、2011年に東北大震災があったからだ。だが別の視点からみれば、私の中で『文学』と『日本』が回帰してきたということかもしれない」という。明治8年に生まれ昭和37年に亡くなった柳田国男は民俗学者・官僚。「日本人とは何か」を近代日本の黎明期から激動の時代を生き、調査・研究を続け求め続けたがゆえに、「柳田にとって『神国日本』とは、世界人類史の痕跡を留める『歴史の実験』場だった」「日本は世界史の『実験』にとって恵まれた場所だ、と柳田は考えた」・・・・・・。
「1973-74年に、『マルクスその可能性の中心』と『柳田国男試論』を書いた。いずれも文芸評論の延長として書いたものだが、それらの違いは大きかった」「『世界史の構造』(2010年)を書き終えたあと、私は急に、柳田国男について考えはじめたのである。それは一つには、2011年に東北大震災があったからだ。だが別の視点からみれば、私の中で『文学』と『日本』が回帰してきたということかもしれない」という。明治8年に生まれ昭和37年に亡くなった柳田国男は民俗学者・官僚。「日本人とは何か」を近代日本の黎明期から激動の時代を生き、調査・研究を続け求め続けたがゆえに、「柳田にとって『神国日本』とは、世界人類史の痕跡を留める『歴史の実験』場だった」「日本は世界史の『実験』にとって恵まれた場所だ、と柳田は考えた」・・・・・・。
世界の文明・宗教・思想を凝縮して掴み、柳田国男の人類史のベースとなった「実験の史学」を浮かび上がらせる。カントの「永遠平和のために」「国際連盟」とマルクスの「ドイツ・イデオロギー」「ロシア革命」の近接と「1928年の不戦条約」「大正デモクラシー」「憲法9条」――それらが1921年に新渡戸稲造に誘われてジュネーブの国際連盟委任統治委員に就任した柳田に投影されるのだ。その「歴史の実験」が1930年代に消滅し、柳田は1935年に「実験の史学」を書いた後、沈黙する。
「実験の文学批評」として、島崎藤村と柳田国男の思想と確執、本居宣長の古道と平田篤胤の平田神道・本地垂迹、本居・平田を超えた柳田の「祖霊」が止まる「神国日本」の「新国学」等々が、研ぎ澄まされるように詳述される。第2部の「山人から見る世界史」では、デカルト、レヴィ・ストロースから「柳田のコギト」を示しつつ、関西弁で「思うわ、ゆえに、あるわ」と語ったりする。柳田はナショナリズムとは対極の「一国民俗学」を唱え、「山人」に固執する。「狩猟民、遊牧民、漁撈民の遊動性と商人」「原無縁と原遊動性、原父と原遊動性、武士と遊牧民、インドの山地民と武士、海上の道と鈴木姓や信州の文明、山人の動物学とオオカミ(山人は遊動的狩猟採集民で狼と一緒に狩猟した)」等が語られ、「山人の宗教学―固有信仰」「御霊と氏神」「双系制と養子制」「歴史意識の古層」などが解説され、抜群に面白い。
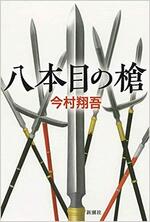 本能寺の変の後の天正11年(1583年)4月、羽柴秀吉が柴田勝家と雌雄を決した賤ヶ岳の戦い。華々しい活躍をした秀吉の小姓衆の殊勲者7人は、「賤ヶ岳7本槍」と呼ばれるようになった。名を轟かせたこの7人――加藤虎之助、志村(糟屋)助右衛門、福島市松、脇坂甚内、平野権平、片桐助作、加藤孫六。それぞれが夢見た大名へと出世していくが、もう一人、同年代の小姓衆の仲間に、桁違いの知力をもち、秀吉の信を得た男がいた。石田佐吉である。朝鮮への出兵の後、秀吉は1598年に没し、1600年の関ケ原。賤ヶ岳7本槍は東軍・西軍にそれぞれ分かれて戦い、石田三成、糟屋助右衛門は散る。しかし、この7人の胸中には「豊臣家」があり、「厳しいことも言い争うことができた8人の仲間」があり、とりわけ「佐吉の言っていたことの深さと情、眩しいほどの生き方を曲げない姿勢」が心の芯にあったのだった。抜群に面白い気鋭の作品。こんな三成なら魅力的で好きになる。凄みもある。
本能寺の変の後の天正11年(1583年)4月、羽柴秀吉が柴田勝家と雌雄を決した賤ヶ岳の戦い。華々しい活躍をした秀吉の小姓衆の殊勲者7人は、「賤ヶ岳7本槍」と呼ばれるようになった。名を轟かせたこの7人――加藤虎之助、志村(糟屋)助右衛門、福島市松、脇坂甚内、平野権平、片桐助作、加藤孫六。それぞれが夢見た大名へと出世していくが、もう一人、同年代の小姓衆の仲間に、桁違いの知力をもち、秀吉の信を得た男がいた。石田佐吉である。朝鮮への出兵の後、秀吉は1598年に没し、1600年の関ケ原。賤ヶ岳7本槍は東軍・西軍にそれぞれ分かれて戦い、石田三成、糟屋助右衛門は散る。しかし、この7人の胸中には「豊臣家」があり、「厳しいことも言い争うことができた8人の仲間」があり、とりわけ「佐吉の言っていたことの深さと情、眩しいほどの生き方を曲げない姿勢」が心の芯にあったのだった。抜群に面白い気鋭の作品。こんな三成なら魅力的で好きになる。凄みもある。
「家康は佐吉のことを無謀な戦に挑んで敗れた愚将だと流布している。佐吉は己に汚名を雪ぐ機会をくれた。今度は己がこれをもって佐吉の名誉を取り戻すつもりでいる。・・・・・・治部は恐ろしい男であったと覚えておこう(「権平は笑っているか」の章)」「家康は隙あらば天下を簒奪しようとする。『俺たちが付いて負ければ、豊臣家は真に滅びる』。虎之助に限らず、豊臣家を守らんとする者の大半の意見が『内府家康亡き後ならば、徳川を封じ込められる』であった。・・・・・・殿下は四杯目を所望した。困り果てた佐吉は遂にどのようにすればよいか、殿下に直接尋ねたという。困った時はつまらない誇りを捨て、真摯に尋ねることが出来るか。人の身になって物事を考えられるか。殿下はそれを試されたのだろうと佐吉は取っていたらしい(槍を捜す市松)」「当初は勝手に戦を起こし、結果的に豊臣家の力を削ることになったと佐吉を憎んでいた。しかし、佐吉のいうように、あの時しか家康を排除する機会はなかったかも知れない。さらに佐吉は負けた時のことも考え、一計を打っていた」「佐吉は皆が羨むほどの権を握ったが一点の清らかさだけは失わなかったらしい。それは佐吉が心の中に、いつも原点に立ち返る『家』を持っていたからではないか(槍を捜す市松)」・・・・・・。他の「虎之助は何を見る」「腰抜け助右衛門」「惚れてこそ甚内」「助作は夢を見ぬ」「蟻の中の孫六」の各章。いずれも自らと佐吉の心中を語らせている。
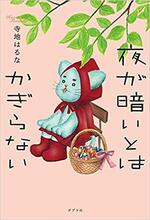 大阪近郊の町にある「あかつきマーケット」の閉店が決まる。そこのぬいぐるみのマスコット・あかつきんが失踪したことが話題となるが、突然現われては人助けをしているという。この町のごくありふれた人々の日常を人物をリレーしていくように描く。14編のリレー短編集。
大阪近郊の町にある「あかつきマーケット」の閉店が決まる。そこのぬいぐるみのマスコット・あかつきんが失踪したことが話題となるが、突然現われては人助けをしているという。この町のごくありふれた人々の日常を人物をリレーしていくように描く。14編のリレー短編集。
ごくありふれた家族や仕事――。それぞれ何気ない言葉に傷ついたり、家庭内のふとしたことで会話が閉ざされたり、引っ込み思案で「友だちがいない」と悩んだり、葛藤もする。ひとりぼっちで心細くもなる。「すごろくに似ている、と思っていた。この世に生まれ出たら最後、さいころをふり続けて前に進まなくてはならない。だけど、このすごろくにあがりがない。・・・・・・みんな、際限なくいろんなことを言う。悪気なく。そう。悪気はないのだ、みんな」「この子は『普通』じゃないんだろうか。『普通』って、いったい、なんだろうか。普通は、普通は、普通は・・・・・・」「そう。未来も、心も、身体も全部、自分のもの。他人の期待に応えるために生まれてきたわけやない。他人に渡したらあかん。"いい子"になんてならなくていい」・・・・・・。
「あかつきん」は知るのだ。「着ぐるみを纏って街を歩いていると、具合の悪そうな老人や迷子の子ども、そういった人々のことがまっさきに目に飛び込んできた。もめている人たちや、困っていそうな人なども。ちょっとした親切。そういうことが、昔からあまり自然にできなかった」「たくさんの人がここで生きているんだと知った。以前は俺以外のすべての人は俺よりずっと強くて大人、たくましく人生を楽しんでいるように見えた。でもそうでもないのかもしれない。もしかしたら俺だけじゃなく、多くの人が見えない着ぐるみを着て生きているのかもしれない。弱さやあさましい気持ちや泣きごとや嫉妬を内側に隠して、他人には笑顔を見せている」「朝は明るく、夜は暗い。それはただ地球がまわっているだけのことだ。明るいことに良い意味も、悪い意味も、含まれていない。ただの朝と夜だ」・・・・・・。
「あかつきん」という"ゆるキャラ"と"着ぐるみ"が、終わりのない日常を「ばあちゃんはもうじいちゃんの一部になっている」という人間のポジティブで温かな縁と感慨の世界に誘う。