 「世界が変わる『視点』の見つけ方」「未踏領域のデザイン戦略」という表題に全ては集約される。ユニクロ、楽天グループ、今治タオル、国立新美術館のシンボルマークや幼稚園、社会施設などのブランド戦略を手がける佐藤可士和さんが、慶應大学湘南藤沢キャンパス(SFC)で行っている授業「未踏領域のデザイン戦略」を書籍化したもの。
「世界が変わる『視点』の見つけ方」「未踏領域のデザイン戦略」という表題に全ては集約される。ユニクロ、楽天グループ、今治タオル、国立新美術館のシンボルマークや幼稚園、社会施設などのブランド戦略を手がける佐藤可士和さんが、慶應大学湘南藤沢キャンパス(SFC)で行っている授業「未踏領域のデザイン戦略」を書籍化したもの。
「今の世の中は、情報が入り乱れて正解が何かもわからないし、正解に行き着く前に、課題が何かもわからない。・・・・・・それが、ますます複雑でわからなくなっている。その時に武器となるのがデザイン戦略」「デザインとは『ビジョン』を設計すること」という。
①課題(問題解決の取り組みやテーマ)→②コンセプト(考え方の方向性)→③ソリューション(具体的に課題解決をするアイデアと実行プラン)――を提示する。まず「課題を正しく発見する。前提を疑う。本質を探る」ことが大事で、よくある例が、いきなり「有名タレントを起用してCMをつくる」など安易にソリューションから入ること。課題設定の作業は有能なドクターの問診に似ているという。課題が設定されたら「耐久性のあるコンセプトを見つける」こと。考え方の方向性だ。「コンセプトメイキングのスキルは、訓練で磨くことができる。失敗と成功の経験が大切」「ベストソリューションは"行ったり来たり" "もがいてつかむ"」という。そしてデザインにおいて大事なのは「勘と感を研ぎ澄ます」「AI時代が本格的に到来すると、ロジカルな分析はAIがほとんど担う」「人間が担うのは"美しい""カッコイイ""愛おしい""面白い"といった人のナマの感覚につながる部分」「普通の感覚を手放すな」。さらに「反射神経(反応より速く)、運動神経を鍛えよ」という。
私は仕事をする場合、「動体視力をもて」「立体的に組み立てよ」「世の課題となっていることの感覚を常にもて」、さらにベルクソンの「問題は正しく提起された時、それ自体が解決である」など、多くの発言をしてきた。戦略とかデザインを若い頃に実践的に学ぶことは、AI時代を迎える今、うらやましいことだ。
 生老病死――。「産むこと、生まれてくるとはどういうことなのか」「わたしたちにとって最も身近な、とりかえしのつかないものは『死』であると思うのですが、生まれてくることのとりかえしのつかなさについても考えてみたいと思っていました」と川上未映子さんは語っている。この世の中の多くの人々も、親も、産む側から考えるが、生まれてくる側から考えることがどれだけあるだろうか。「産むこと、生まれてくること」を精子提供(AID)の現実から考えさせる挑戦的力作。
生老病死――。「産むこと、生まれてくるとはどういうことなのか」「わたしたちにとって最も身近な、とりかえしのつかないものは『死』であると思うのですが、生まれてくることのとりかえしのつかなさについても考えてみたいと思っていました」と川上未映子さんは語っている。この世の中の多くの人々も、親も、産む側から考えるが、生まれてくる側から考えることがどれだけあるだろうか。「産むこと、生まれてくること」を精子提供(AID)の現実から考えさせる挑戦的力作。
「自分の子どもに会いたい」――。パートナーなしの妊娠、出産を願うようになった駆け出しの30代小説家の夏目夏子。親を知らないAIDのグループの逢沢潤、彼の恋人の善百合子、小説家仲間でもありはっきりした考えをもつ遊佐リカ、小説を書くよう励ます大手出版社編集者・仙川涼子ら、周りの人々がこの根源的な「産むこと、生まれてくること、生まれないこと」「AID」「産むという決定権をもつ親の身勝手な選択」について考えを述べる。生命の意味をめぐっての真摯な問いと、自らのたどった人生そのものから来る率直な感情がぶつかり合う。AIDによって生まれてきた者の苦悩・葛藤、「自分の子どもに会いたい」という女性の理由を超えた気持、生老病死のただ一つ自意識のない「生まれる」こと――未知の重い領域に踏み込んだ長編。大阪弁の姉・巻子と娘・緑子のユーモアと強さにほっとする。
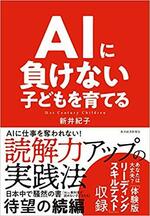 待望の「AI vs.教科書を読めない子どもたち」の続編。前著はAIの限界、AI時代の迷妄を打ち破るとともに、日本の教育の本質に迫る衝撃的著作だったが、本書は具体的、実践的で抜群に面白く、重要だ。「読解力が人生を左右する。とくにAI時代は」「『教育のための科学研究所』(新井紀子代表理事・所長主催)は日本全国の幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校のホームページを無償で提供する」と覚悟を示す。
待望の「AI vs.教科書を読めない子どもたち」の続編。前著はAIの限界、AI時代の迷妄を打ち破るとともに、日本の教育の本質に迫る衝撃的著作だったが、本書は具体的、実践的で抜群に面白く、重要だ。「読解力が人生を左右する。とくにAI時代は」「『教育のための科学研究所』(新井紀子代表理事・所長主催)は日本全国の幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校のホームページを無償で提供する」と覚悟を示す。
「AIが苦手とする読解力を人間が身につけるにはどうしたらいいのか」――。徹底して作り上げてきたRST(リーディングスキルテスト)を実際に示し、「係り受け解析」「照応解決」「同義文判定」「推論」「イメージ同定」「具体例同定」の6つの構成を提示する。RSTがいかに信頼性を獲得してきたか、努力には感服する。しかし、RSTはあくまで、視力検査と同様、「診断のツール」で達成度テストではない。そのうえで「読解力を培う授業」「意味がわかって読む子どもを育てるため」にどのようにしたらいいのか。実例を積み重ねながらの挑戦の課程が示される。
加えて本書には「体験版リーディングスキルテスト」が収録されている。やってみると「よく読む」という作業は結構、エネルギーを使うものだ。前著とともに面白く必読の書。







