今回の台風19号は死者74名、行方不明者12名(10月16日9時現在)という未曾有の災害をもたらしました。15日、私は福島市内で氾濫した濁川、大森川に行き、浸水被災の状況を調査・視察しました。これには、伊藤たつや県議(11月10日投票、福島県議選公認候補)、甚野源次郎・福島県本部議長、福島県庁の担当者らが同行しました。
氾濫した箇所は、濁川・大森川が、阿武隈川に向かって合流する所。家屋に土砂が流入していたり、新築の家が激流により土台が崩れ住めなくなっていたり、床下浸水していたり、浄化槽がやられて水が出なくなっていたり、様々な生活被害を目の当たりにしました。何人かの住民の方々と話をしましたが「これからどうなるのか?」といった不安の声もありました。まずは復旧、とくに一刻も早い生活インフラの再建に全力をあげなければなりません。
視察の後、福島市内で行われた公明党時局講演会に出席しました。私は「国交大臣時代から福島復興のために、常磐道路の全通、福島―相馬道路の早期完成など、必要なインフラ再生に手を尽くしてきた。今回の台風被害を含め、福島復興のためにさらに尽くしたい」「政治は結果だ。伊藤たつやさんは、現場にすぐに飛んで行って優先順位を察知し即座に結果を出していく行動第一の議員だ」などと挨拶をしました。
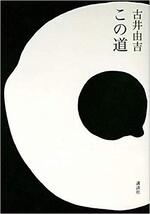 80歳を越えた古井由吉氏の最新小説。2017年8月から18年10月まで、2か月ごとに書いた8篇。その時期の"つれづれ随想"的だが、戦争や戦後の恐怖や「生きる」に精一杯であった時のこと、東日本大震災などの大地震、執筆時の九州北部豪雨や西日本豪雨、昔と今の「季節」「街の変化」の感じ方の相違等々にふれつつ、「生老病死」の老いの実存と境地から描く。「個の記憶を超え、言葉の淵源から見晴るかす、前人未踏の境。」と帯にあるが、深い思索と観識眼とその境地はうなるほどだ。
80歳を越えた古井由吉氏の最新小説。2017年8月から18年10月まで、2か月ごとに書いた8篇。その時期の"つれづれ随想"的だが、戦争や戦後の恐怖や「生きる」に精一杯であった時のこと、東日本大震災などの大地震、執筆時の九州北部豪雨や西日本豪雨、昔と今の「季節」「街の変化」の感じ方の相違等々にふれつつ、「生老病死」の老いの実存と境地から描く。「個の記憶を超え、言葉の淵源から見晴るかす、前人未踏の境。」と帯にあるが、深い思索と観識眼とその境地はうなるほどだ。
老いは喪失、諦念、自愛の組み合わせだろう。諦(あきらめる)とは明らかに観ることだ。「老年に至って振り返ればこれでもさまざま、何事かを為したにつけ為さなかったにつけ、すこしずつおのれを捨てて、置き去りにしてきたことだ。なしくずしの自己犠牲、なしくずしの自愛である。最後の運命の定めるところと受け止めて、これに順う。従容とまではおのれをたのめなくても、その諦念にわずかな自由を見る」という。今の社会は昔に比べ静謐が消え、季節が消え、むき出しの貧病が消え、人と人の生死につながる絆が消えていく。昭和12年生まれの古井さんと、20年生まれの私とは戦争の陰影が異なるからだろう、それらの感受性がかなり異なる。凶災だけでなく、梅雨時、暑さに陰りの見え始める初秋、そして晩秋、花の咲く春を待つ時。季節によって生老病死の感じ方・気分は変化する。「たなごころ」「梅雨のおとずれ」「その日のうちに」「野の末」「この道」「花の咲く頃には」「雨の果てから」「行方知れず」の8篇を味わいながら読んだ。
 「地域再生は『儲かる会社』作りから」が副題。題名と副題に尽きており、小出宗昭氏は年間相談件数4000超の企業支援拠点「エフビズ」の代表。他の自治体も共鳴し、全国約20か所にご当地ビズが誕生している。全国の成功事例を示しながら各ビズの奮闘ぶりを示している。
「地域再生は『儲かる会社』作りから」が副題。題名と副題に尽きており、小出宗昭氏は年間相談件数4000超の企業支援拠点「エフビズ」の代表。他の自治体も共鳴し、全国約20か所にご当地ビズが誕生している。全国の成功事例を示しながら各ビズの奮闘ぶりを示している。
上からの地方創生、単なる相談の受け手の官制の支援はなかなかうまくいかない。魂を入れ、具体的な生きた対策こそが重要。「儲かる会社」をどうつくるか。その通りだ。しかし、地方の企業は「ないないづくし」に苦しんでいる。「ないないづくし」の逆境に打ち勝ち、瀕死の企業をよみがえらせるには、必要な資質を備えたプロの人物が不可欠となる。企業支援のプロとして絶対不可欠なのは、「ビジネスセンス」「高いコミュニケーション力」「情熱」の3条件だという。仕事のできる政治家もそうだから納得する。成果を上げるには「セールスポイント(強み)を見つける」「ターゲットを絞る」「連携する」の3つの方法を示す。
「車いすスポーツのためのトレーニングマシン」「被災した学習経営者の再スタート支援」「自然薯ブランド化」「スポーツ弁当」「お掃除グッズ・ほこりんぼう」「防音防振製品」・・・・・・。具体的成果を示しつつ「商店街といっても"個店"から」「地域ビジネスのために金融機関は奮い立て」という。大事な働きを展開してくれている。
 足利尊氏によって京都に開設された室町幕府。「初代尊氏、三代義満、八代義政が有名だが、三代義詮、四代義持、六代義教といった面々もなかなかのもので、統治者として政治を推し進めた。義政の時代以降、室町幕府の力は衰えていくが、・・・・・・代々の将軍は、みな自身は王者であるという自尊心を持ち、勢力を伸ばそうと務めた」「ただ将軍(室町殿)が政治のすべてを仕切っていたわけではなく、細川氏をはじめとする有力な守護大名が並び立ち、将軍を支えながら政治に関与していた」・・・・・・。
足利尊氏によって京都に開設された室町幕府。「初代尊氏、三代義満、八代義政が有名だが、三代義詮、四代義持、六代義教といった面々もなかなかのもので、統治者として政治を推し進めた。義政の時代以降、室町幕府の力は衰えていくが、・・・・・・代々の将軍は、みな自身は王者であるという自尊心を持ち、勢力を伸ばそうと務めた」「ただ将軍(室町殿)が政治のすべてを仕切っていたわけではなく、細川氏をはじめとする有力な守護大名が並び立ち、将軍を支えながら政治に関与していた」・・・・・・。
「創世期の室町幕府と南北朝(鎌倉幕府討幕、建武の新政、南北朝の戦い、観応の擾乱)」「足利将軍の権威確立(上杉禅秀の乱、クジ引き将軍・六代義教)」「鎌倉公方と関東の争乱」「応仁の乱と室町幕府の動揺(無気力将軍・八代義政と日野富子、東山文化)」「足利将軍の衰退と室町幕府の滅亡(義輝・三好体制、信長の15代・義昭)」・・・・・・。まさに激動、動乱の室町時代の全貌をまとめてくれている。






