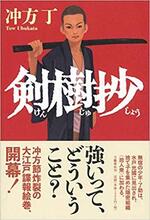 明暦3年(1657年1月18・19日 将軍家綱)の江戸の大火(振袖火事)は、江戸城をはじめ市中の6割を焼失させ、死者は10万人にも及んだが、この月は火事に次ぐ火事の連続だったという。元日、2日、4日、5日、9日、18・19日。その6年前、由井正雪が江戸を焼き討ち、幕府転覆を企てたこともあり、「反幕浪人による放火ではないか」との噂が広まった。
明暦3年(1657年1月18・19日 将軍家綱)の江戸の大火(振袖火事)は、江戸城をはじめ市中の6割を焼失させ、死者は10万人にも及んだが、この月は火事に次ぐ火事の連続だったという。元日、2日、4日、5日、9日、18・19日。その6年前、由井正雪が江戸を焼き討ち、幕府転覆を企てたこともあり、「反幕浪人による放火ではないか」との噂が広まった。
再建の任を受けたのが、水戸徳川光國。若い頃は遊蕩狼藉で知られたが、いまや30歳。街の再建、学問の書籍等の収集・再興、そして治安にと情熱を注いでいた。幕府には"捨て子"を保護し、諜者として育てる「拾人衆」なる組織があり、老中・阿部豊後守忠秋は"子拾い豊後守"とあだ名されるほど孤児の保護に熱心だった。そこに親を殺された無宿者の少年・六維了助が加わり、光國はその「拾人衆」の目付け役にも任じられる。
浪人が跋扈し、火付盗賊、火事場泥棒、辻斬りが繰り返される江戸・・・・・・。光國らは賊とその黒幕を追う。当時の世相がダイナミックに描かれ、目黒の五百羅漢寺、水野十郎左衛門と幡随院長兵衛、初代横綱・明石志賀之助、鎌倉の極楽寺良観と火災などの話が挿入され興味を惹く。
 「カッコいい存在とは私たちに"しびれ"を体感させてくれる人や物である」――。「カッコいい」とは、じつはかなり本質的な生き方の問題だ。「『カッコいい』は、民主主義と資本主義とが組み合わされた世界で、動員と消費に巨大な力を発揮してきた。『カッコいい』とは何かがわからなければ、私たちは、20世紀後半の文化現象を理解することが出来ないのである」という。「カッコいい」という概念は、そもそも何なのか。それを、歴史的に、文明論的に、「クール」「ヒップ」「ダンディズム」から、キリスト教や英雄崇拝の事例から、文学や芸術・美学から、広範かつ本源的に剔抉している。
「カッコいい存在とは私たちに"しびれ"を体感させてくれる人や物である」――。「カッコいい」とは、じつはかなり本質的な生き方の問題だ。「『カッコいい』は、民主主義と資本主義とが組み合わされた世界で、動員と消費に巨大な力を発揮してきた。『カッコいい』とは何かがわからなければ、私たちは、20世紀後半の文化現象を理解することが出来ないのである」という。「カッコいい」という概念は、そもそも何なのか。それを、歴史的に、文明論的に、「クール」「ヒップ」「ダンディズム」から、キリスト教や英雄崇拝の事例から、文学や芸術・美学から、広範かつ本源的に剔抉している。
「カッコいい」の条件――。「魅力的、生理的興奮(しびれる体感)、多様性、自分にはない他者性、非日常性、理想像、同化・模倣願望、再現可能性(憧れていた存在のカッコよさを分有できる)」「カッコいい存在は、マスメディアを介したその絶大な影響力故に、反対の立場に立つものを脅かす」「カッコ悪い存在は、人から笑われ、侮られ、同情され・・・馬鹿にされる。まず感じるのは羞恥心だ」「カッコいいへの同化・模倣願望をカッコ悪いと見做されている時のカッコいいへの復帰・同調願望が一体となって作用し、カッコいいは民主主義と資本主義とが組み合わされた世界で、異例の動員と消費の力を発揮してきた」「武士道的な義理は"人倫の空白"を埋めるために求められたが、戦後社会においても強欲に対する戒めの一種の精神主義に引き継がれ、『カッコいい』存在への憧れが、人としていかに生きるかという"人倫の空白"を満たす社会的機能をもった」・・・・・・。
「ヒップ(勇気があり、好奇心に満ち、クールで執着がなく、権威的でない。自分自身になる意志をもつ)とスクエア(体制側で、責任感が強く、真面目で、ルールを守り・・・・・・単調な生活を守って生きる)」「ロックコンサートの"しびれる"ような体感」「ダンディズムの三世代(貴族的オシャレから"さりげなさ"、そして絶対的単純の品位)」「(最近の)カッコいい女(男に媚びない、知的で自由、何が自分にとって大切かを知り抜く)」「古代ギリシャ以来の男らしさ(死を恐れず、敵と戦う勇気、正義のために体制に背く反抗、説得力のある言葉を発する力、セックス・アピール、家族を守ること)」・・・・・・。
「日本の『カッコいい』にせよ、『クール』にせよ、『ヒップ』にせよ、『ダンディズム』にせよ、共通した美徳の一つに自己抑制がある」・・・・・・。戦後社会が人々を自由に放り込んだがゆえに、"人倫の空白"が生まれ、理想像を追い求めることになっていた。「カッコ悪くない」「ダサい」と目されることの羞恥心や屈辱感がSNS社会で加速され、動員される危険性は当然ある。多様性のなかの画一性。そうした危機感をもちつつ自立して生きる。変化する社会のなかでいかに生きるべきかを考えさせる充実した著作。
10月5日、札幌で行われた「衆議院議員佐藤英道さんと語る会」に出席し、挨拶をしました。これには、吉川貴盛・自民党衆院議員、鈴木直道・北海道知事、秋元克広・札幌市長、真弓明彦・北海道経済連合会会長など、多くの首長、経済界、各種団体、地域有力者の方々が出席しました。
私は「今日10月5日は、"政治の安定と改革のリーダシップ"の旗頭のもと、自公連立政権が発足してちょうど20年目にあたる。これまで幾多の風雪をくぐり抜け、両党の信頼を作り上げ、現在の政権の安定をもたらした」「佐藤英道さんは、公明党が最も大切にしている、人とのつながりを大事にする政治家で、北海道のために誰よりも縦横無尽に駆け巡る現場の人だ」「北海道は、2030年の札幌冬季オリンピック・パラリンピックの実現を目指すと共に、観光、北海道新幹線、7空港のコンセッション、高速道路のアンビシャス・ロードなど、重要課題が目白押しだ。私もさらに、北海道の発展のために尽力していく」などと挨拶をしました。
また、これに先立ち、石狩湾新港発電所に行き、LNGを燃料として、ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた「コンバインドサイクル発電」と呼ばれる新しいタイプの発電所を、地元の石狩市議と視察しました。北海道の新たなベース電源として大きな役割を期待されています。
 湊かなえワールドを実感させる力作。立石力輝斗が高校3年の妹・沙良を刺殺し、火を放って両親を焼死させた「笹塚町一家殺害事件」。ミュンヘン国際映画祭で特別賞を受章したばかりの気鋭の映画監督・長谷部香は、この事件を手がけようとし、新人脚本家の甲斐千尋に脚本製作を持ちかける。笹塚町は、千尋の生まれ故郷。この事件をめぐっての隠されていた事実の連鎖が始まる。
湊かなえワールドを実感させる力作。立石力輝斗が高校3年の妹・沙良を刺殺し、火を放って両親を焼死させた「笹塚町一家殺害事件」。ミュンヘン国際映画祭で特別賞を受章したばかりの気鋭の映画監督・長谷部香は、この事件を手がけようとし、新人脚本家の甲斐千尋に脚本製作を持ちかける。笹塚町は、千尋の生まれ故郷。この事件をめぐっての隠されていた事実の連鎖が始まる。
「長谷部香の母親は、なぜ虐待まがいの教育に熱心だったのか」「香の父親はなぜ自殺したのか」「引きこもりの立石力輝斗はなぜ殺人を犯したのか」「妹・沙良はどういう人物だったのか。人を壊滅させる攻撃的虚言癖は真実なのか」「甲斐千尋の姉・千穂はフランスでピアノを学んでいるというが、その真実は」・・・・・・。そもそも「この事件を映画にしたいという長谷部香の意図は何か」・・・・・・。
各家族が背負う宿業。不思議な縁と結び付き。そこには法廷での判決・筋書きとは別の生々しい人間の感情が噴出する宿命的ドラマがある。"真実"を知ること、"知ること"と"救い""受容"、それを表現するのは何の為か、どういう意味があるのか。午前の太陽ではなく、落日の輝きに心惹かれるときがあるのはいったい何故なのか・・・・・・。1行1行に緊迫が漲る。




