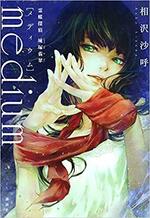 推理作家・香月史郎は城塚翡翠という霊媒の若き女性の助けを借り、様々な難事件を解決してきた。香月の大学の後輩・倉持結花が殺害された事件、作家の黒越篤が閉鎖空間で殺害される"水鏡荘の殺人"。そして女子高生連続絞殺事件。翡翠が死者の言葉を伝え、それを香月は論理の力を組み合わせて解決するという訳だ。
推理作家・香月史郎は城塚翡翠という霊媒の若き女性の助けを借り、様々な難事件を解決してきた。香月の大学の後輩・倉持結花が殺害された事件、作家の黒越篤が閉鎖空間で殺害される"水鏡荘の殺人"。そして女子高生連続絞殺事件。翡翠が死者の言葉を伝え、それを香月は論理の力を組み合わせて解決するという訳だ。
そんな時、同一犯と思われる姿なき8件もの連続殺人事件が起きていた。手口も異常だが、何の手がかりも残さない。全員が20代の女性会社員、一人暮らし、失踪届が出されていることを後で知る。犯人は狡猾で、警察の捜査手法にも詳しいようだ。事件は予想外の展開に。「大ドンデン返し」と「緻密な推理」に身体ごと持っていかれる本格ミステリー。
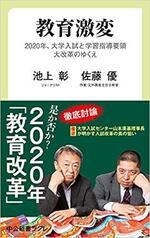 「2020年、大学入試と学習指導要領大改革のゆくえ」が副題。共通一次からセンター試験で40年。昨年末、「大学入学共通テスト(新テスト)」が立ち止まったが、本書発行は昨年4月。2人の対談に、大学入試センターの山本廣基理事長が最後に加わり、苦労と考え方を率直に語る。
「2020年、大学入試と学習指導要領大改革のゆくえ」が副題。共通一次からセンター試験で40年。昨年末、「大学入学共通テスト(新テスト)」が立ち止まったが、本書発行は昨年4月。2人の対談に、大学入試センターの山本廣基理事長が最後に加わり、苦労と考え方を率直に語る。
「日本が危機的状況から脱するために、偏差値競争から抜け出して、真に知識を得て、活用するような教育を定着させたい(佐藤優)」「小中高校の現場では受験競争が激化し、特に一部の私立中学高校では"受験予備校"化している。これからの日本の教育はどうあるべきか(池上彰)」「40年間の『共通テスト』というのは大事な公共財だと思う。今回の入試改革の議論にはテストの専門家の参加が十分ではなかったという印象がある(山本理事長)」と語る。
「日本の"病"を進行させた教育の歪み(AI時代に必要な能力とは何か。本来教育は、理不尽な格差を生まないような知恵を育むためにある)」「是か非か? 2020年教育改革(連合赤軍が生んだ共通一次。新テストの"プレテスト"は非常によくできている。英語の試験に"話す"能力はいらない)」「アクティブ・ラーニングと『エリート』教育(アクティブ・ラーニングとは主体的・対話的で深い学び)」「テロも教育が生んだ?(高学歴揃いだったオウム真理教幹部。宗教に対する無知の危険。宗教を教えるには宗教が絡んでいるいい小説を何冊か勧める)」「揺らぐ知の基盤・大学をどうする(いい大学に入ったとたんに何をしたらいいか見えなくなる。怠慢を超えた犯罪に近い知の軽視。私大は入試の『作問力』で勝負を始めた)」「大学入試センター理事長が明かす2020年度入試改革の真の狙い(高校・大学・受験産業――現場では3つのベクトルが動き、それぞれ別の角度で考えている。文理融合を本気で考えるべき。記述式の導入はこういう問題に対応できる力を鍛えようという高校生へのメッセージでもある。センター試験の作問には2年近くかかっている。批判の前に問題を見よ。改革に試行錯誤は避けられない)」・・・・・・。昨年の春頃に本格的・最終論議をすべきだったと思っている。











