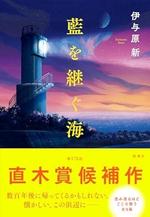自分の人生を決定づける言葉がある。苦難に直面した時、重要な決断の時、惰性に流れてしまっている時、絶望の淵に立っている時、師匠や先達の一言があったればこそ、今の自分がある。文藝春秋誌上に、かつて掲載された「わたしの師匠」や「肉親と先達が遺した言葉」など、よりすぐりを取り上げた本。語られる人も凄いが、それを語っている人も素晴らしい。
自分の人生を決定づける言葉がある。苦難に直面した時、重要な決断の時、惰性に流れてしまっている時、絶望の淵に立っている時、師匠や先達の一言があったればこそ、今の自分がある。文藝春秋誌上に、かつて掲載された「わたしの師匠」や「肉親と先達が遺した言葉」など、よりすぐりを取り上げた本。語られる人も凄いが、それを語っている人も素晴らしい。
「松下幸之助(語るのは野田佳彦)」「丸山眞男(三谷太一郎)」「石原裕次郎(峰竜太)」「井上ひさし(野田秀樹)」「田部井淳子(市毛良枝――エベレストも登りたくて登っただけよ。自分がやりたいと思うことは、やろうとさえすれば何でもできる)」「後藤田正晴(的場順三)」「やなせたかし(梯久美子――逆転しない正義というものがこの世に存在するのか。たどり着いたのが『飢えた子供にひときれのパンを与えること。少なくともそれはひっくり返ることのない正義であるはずだ。自分の顔を食べさせる。ヒーローアンパンマン』――正義には自己犠牲が伴う)」・・・・・・。
「吉本隆明(糸井重里)」「蜷川幸雄(鈴木杏――できない悔しさや認められたいという気持ちに向き合っていなければ、上手くはならない。自分の感情から逃げるな)」「司馬遼太郎(村木嵐ーームラ気乱子さん)」「小山内美江子(名取裕子――年を重ねているのにいい仕事、いい役に恵まれているみたい。そのまま、ふわりと演じているからかな)」「黒田清(大谷昭宏――権力との向き合い方)」「大平正芳(古賀誠――君はヒンクを経験しているじゃないか)」・・・・・・。直接お会いした方もいる。改めて思い出す。
「水木しげる――『妖怪』と『家族』を愛した漫画家の幸せな晩年(武良布枝=夫人、長女、次女)」「美空ひばり(加藤和也――おふくろの素顔、不死鳥コンサートの舞台裏)」「石原慎太郎(石原延啓――父は最期まで『我』を貫いた。創造的な世界にひとつのやり方を投げかけることはできたよな)」「阿川弘之(倉本聡――「瞬間湯沸器」と云われるほど短気直情の方である一方、ユーモア好きの男っぽい紳士)」「立花隆(佐藤優――私とは波長が合わなかった『形而上学論』)」「半藤一利(保阪正康――徹底したリアリズムの手法で昭和史に新たな光を当てた。卓越していた証言の真贋を見極める眼。経験上、証言者には「1 ・ 1 ・ 8の法則」がある)」「中村哲(澤地久枝――後世への最大遺物。用水路は残る)」・・・・・・。
凄い人たちがいる。
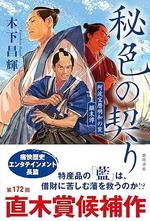 江戸中期、徳島蜂須賀藩25万7000石は特産の藍を持ちながら30万両もの巨額の借財を抱えていた。しかも藍の流通は大阪商人に握られ、藍玉の生産農家は苦しい生活を強いられて藍師株を手放す藍作人も出ていた。
江戸中期、徳島蜂須賀藩25万7000石は特産の藍を持ちながら30万両もの巨額の借財を抱えていた。しかも藍の流通は大阪商人に握られ、藍玉の生産農家は苦しい生活を強いられて藍師株を手放す藍作人も出ていた。
徳島藩蜂須賀家の物頭・柏木忠兵衛は新藩主候補である秋田藩主の弟・佐竹岩五郎との面会のため、江戸に向かった。岩五郎は第10代藩主・蜂須賀重喜となるが、「政には興味なし」と言い放ち、儒学や囲碁、茶道、戯画などを専らとした。家老たちの専横が続くなか、柏木忠兵衛、樋口内蔵助、林藤九郎、寺沢式部ら中堅家臣団は藩主による藩政改革を目指していた。そして、ついに重喜は立ち上がるが、その改革案はあまりにも斬新なものだった。そして旧態依然の家老たちを次々に追い落としていく。
重喜の急進的改革と忠兵衛、内蔵助らの漸進的改革、抵抗する家老たち、藍をめぐる大阪商人の策謀・・・・・・実に激しい智謀渦巻く戦いは極めて面白く、現代にも通ずるものがある。重喜の苛烈な藩政改革、抜きんでた知識と弁舌、厳しい倹約令と公共投資、牢固とした岩盤のごとき身分制度の破壊への意思は凄まじい。戸惑いながらも支えようとする忠兵衛ら中堅4人の結束と友情も現実感がある。
「秘色に染めた品をともと共有すれば互いの願いが叶う」――阿波の特別な言い伝えだと言う。「私は藩政改革をやる。私は誓った。次はお前だ。何があっても私を裏切るな。改革は茨の道だ。親子兄弟で憎み合い、時に殺し合う。だが、お前だけは俺の味方でいろ。どんなことがあってもだ。仲間や旧友を敵に回すことがあっても、決して私を裏切るな」・・・・・・。
「新法も同じです。速い変革は、蠅にとっての速い動きと同じです。蠅が刀に見立てた箸をよけたように、家臣たちも抗い、何とか逃れようとします・・・・・・一気呵成にゆっくりとやるのです。それが藩政改革の成功の秘訣です」・・・・・・。「新法は納豆を食するが如し。拙速よりも巧遅が尊ばれることがあるとはな」・・・・・・。
「忠兵衛、お主は、改革の肝は何だと思う。・・・・・・改革で大切なのは、人の心よ。どんな正しい法度であっても、人の心がついて来なければ意味がない。・・・・・・樋口や忠兵衛たちも、そんなことにさえ思い至らなかった。それは、家臣たちの心が旧態のままだったからだ」・・・・・・。
「内蔵助や式部は、徳島藩に忠義を尽くし、藤九郎は蜂須賀重喜に忠義を尽くす。・・・・・・忠兵衛はひとり取り残される。頭を抱えた。俺は、何に殉じるべきなのか。重喜を裏切らないと秘色に誓った。しかし、その結果、徳島藩がふたつに割れ、改易されてもいいのか」・・・・・・。
藩政改革に挑んだ藩主と若き中堅武士たちの戦いを鮮やかに描く熱量こもった力作。
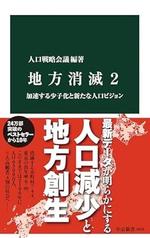 「加速する少子化と新たな人口ビジョン」が副題。2014年刊行の「地方消滅」では、896の「消滅可能性都市」リストが出され衝撃を与えた。それから10年――消滅する市町村は744となったが、東京の出生率は0.99、このままでは2100年に人口6300万人、そのうち高齢者が4割の社会になる。本書は、全国1729自治体を9つに分類。「ブラックホール型自治体」の特性なども分析し、持続可能な社会へ向かうための戦略とビジョンを打ち出す。
「加速する少子化と新たな人口ビジョン」が副題。2014年刊行の「地方消滅」では、896の「消滅可能性都市」リストが出され衝撃を与えた。それから10年――消滅する市町村は744となったが、東京の出生率は0.99、このままでは2100年に人口6300万人、そのうち高齢者が4割の社会になる。本書は、全国1729自治体を9つに分類。「ブラックホール型自治体」の特性なども分析し、持続可能な社会へ向かうための戦略とビジョンを打ち出す。
「消滅可能性都市」が減ったのは、「外国人入国者数がかなり増加したためで、危機的状況は全く改善されていない」(増田寛也)と言う。ただし、東京豊島区は消滅可能性都市と言われ、高野之夫区長を中心に区全体が一丸となって反転攻勢の戦いを始めた。私の地元でもあって、その懸命の戦いを目の当たりにした。若い女性が住み続けられるように、様々な手を打ち、待機児童ゼロを実現。「国際文化都市」をキーコンセプトにし、池袋は「文化」の街へと大変貌した。大塚、巣鴨も変わった。その熱量はすごいもので、地域の創生はやればできるのだ。
人口減少の要因は、「自然減」と「社会減」。自然減に対してはまさに異次元の少子化対策。非婚、晩婚、晩産、少産の4つの壁を打ち破ることだ。そのためには、「若い世代の給料を上げて、かつ女性の非正規労働を減らし、出産後も復帰しやすい体制を整え、安心して子どもを産み育てられるような環境を整備すること」(三村明夫)だ。「共働き共育て」社会であり、本書で言う「子どもをみんなで育てる『共同養育社会』」だ。この10年、女性のM字カーブは解消してきたが、L字カーブ問題(女性の正規雇用率が20代後半をピークに急低下する)は残っている。
社会減については、地方に仕事を作り、東京への若者の流出を食い止めようとしたが、「地方自治体は自らの住民数を増やすことに躍起になり、近隣自治体との移住者の奪い合いに終始してしまった」(増田寛也)。取り組みはバラバラで「空回り」と指摘する。政府も官も民も国民全体での対策の盛り上がりが絶対不可欠となっている。
人口戦略会議の緊急提言「人口ビジョン2100」では、「安定的で、成長力のある『8000万人国家』へ」を目指している。そして総合的、長期的な戦略として「定常化戦略(人口減少のスピードを緩和させ、最終的に人口を安定させること)と「強靭化戦略(質的に強靭化を図ることにより、多様性に富んだ成長力のある社会を構築していく)」を目指している。
大事なことは総合的に、持続的に、強力に、具体的に推進することだ。本当に待ったなしだと思う。
「夢化けの島」――。萩市の北西、約45キロ。日本海の小さな島・見島。山口県内の国立大学で助教をしている久保歩美の専門は、火成岩岩石学。見島で、竹藪をかき分けて萩焼に使う見島土を探している変な男に会う。三浦光平というこの男は元カメラマンだが、萩焼の名品・紅萩手の陶芸家の末裔で、萩焼の絶妙な色味を出す伝説の土を探していた。「じいちゃんが、『土にはの、土のなりたい形があるんじゃ。その声をよう聞きながら、さぐりさぐりのばすことや』と言っていた」・・・・・・。共に土を探すなか、陶芸家はろくろ挽きをしながら粘土の声を聞く。地質学者もまたハンマーを振るい、ルーペを覗いて岩石の声を聞く。それを漏らさず記録することで、研究という器の形ができていくと思うのだ。
「狼犬ダイアリー」――。「わたし、負け犬やねん」。30歳という節目に、まひろは都会から逃れ奈良の山奥に移住してきた。ある日、「ウォーン、ウォールルルン」という遠吠えを聞く。オオカミではないか。集落で騒動が起きる。絶滅したはずのニホンオオカミ。そこに現れたのは狼混だった。
「祈りの破片」――。長崎県の長与町役場に勤める小寺の元に、「放置された空き家の中で青白い光が見えた」「えすか(怖い)家や」という声が寄せられる。中に入ると、木箱の山がぎっしり詰まり、全てが岩石だった。表面が溶けて鈍く光る岩石。細かな気泡で覆われた瓦。焦げて変色したレンガ。首が曲がった瓶。長崎の原爆にあった長崎師範学校で博物の教師をしていた加賀谷昭一の収集物だった。「彼がここにあるすべてのものに込めた祈りだ」・・・・・・。
「星隕つ駅逓」――。北海道遠軽町。ドーンという轟音とともに、西の空に大きな火の玉が見えた。その正体は、大きな流星、火球で、隕石として落下した可能性が高い。隕石調査隊が乗り込んでくるが、駅逓の使命を受け継いでいる郵便局の夫婦が見つける。「隕石には発見地点の最寄りの郵便局の名前が付けられる」と聞きかじった妻がとった意外な行動・・・・・・。「星隕つ駅逓 野知内駅逓跡」の話。
「藍を継ぐ海」――。徳島県の南東部に位置する太平洋に面した阿須町。ウミガメの卵を孵化させ、自分で育てようとする中学生の沙月。アカウミガメの子ガメは、すぐに外洋に出て、遥か太平洋の向こう側、カリフォルニア沖の食べ物の豊富な海域まで行く。海流に乗り、流れ藻の中に隠れ、流木にしがみつきながら、3~4年もかけて渡る長い旅。10年余り過ごした後、若ガメに成長すると、また太平洋を渡り、「母浜回帰」する。地磁気を利用するようだ。「どの浜に帰るかはカメさんたちが決めること。気に入った浜には帰るし、気にいらん浜には帰らん。保護したいとか、増やしたいとか言うても、人間はまだそこまでウミガメのことを知らんと思うんよ。人間の考えるとおりにはなかなかならん」「人間も同じや思うんよ。好きなところで、気に入った場所で、生きたらええの。生まれた土地に責任がある人なんて、どこにもおらんのよ」と、姫ケ裏海岸の「ウミガメ監視員」を任されている佐和は言う。