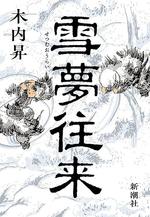 越後国魚沼郡の南端にある塩沢村の縮仲買商・鈴木牧之。19歳の時、行商に訪れた江戸で、ふるさと越後の雪の多さなどが、まるで知られていないことに驚き、雪を主題とした随筆で、雪国越後を紹介しようと決意する。やがて彼の書いた「雪話」は、人気戯作者の山東京伝の目に止まり、出版へと動き始める。しかし山東京伝も本気で取り合ってくれず、版元からの金銭要求や仲介者の死去等もあり、事態は暗礁に乗り上げ、年月のみが経過する。
越後国魚沼郡の南端にある塩沢村の縮仲買商・鈴木牧之。19歳の時、行商に訪れた江戸で、ふるさと越後の雪の多さなどが、まるで知られていないことに驚き、雪を主題とした随筆で、雪国越後を紹介しようと決意する。やがて彼の書いた「雪話」は、人気戯作者の山東京伝の目に止まり、出版へと動き始める。しかし山東京伝も本気で取り合ってくれず、版元からの金銭要求や仲介者の死去等もあり、事態は暗礁に乗り上げ、年月のみが経過する。
やがて、原稿は山東京伝への敵対意識に燃える曲亭馬琴の手に渡る。馬琴は12年間も本気で板元を探すでもなくほったらかしにした上、牧之の催促に腹を立て、送った膨大な原稿を捨てたとまで言う。牧之は虚々実々の江戸出版界に翻弄され、何十年も放置されたのだ。特に馬琴の狷介、固陋、京伝への敵対心はあまりにもひどいもので、牧之の人生をかけた願いを踏みにじり続けた。
ようやく山東京伝の弟・山東京山が乗り出してくれる。「やはり会って話さねばなるまい。牧之さんが越後の話を書こうと思った経緯を。なにゆえ何十年にもわたり、ひとつの事柄を紡ぎ続けたのか」と越後に訪ねてくる。そして天保8年(1837)に「北越雪譜」が刊行される。実に山東京伝に依頼してから40年が経っていた。67歳になっていた。
京山は「私には戯作者としての抜きん出た才はないかもしれぬ。兄ほど評判の作も書けぬ。そういう者が秀でるにはいかにすればよいと思う。それは、ひたすら実直に書き続けることさ。手を抜かず、欲を張らず、多くを望まず、ただただ生一本に書いていくことだ」と言う。牧之もそうだろう。また京伝は京山にこう言ったという。「戯作においては、何でもかんでもつまびらかにせずともよいのだ。正体がわかれば、胸のつかえは下りるだろうが、この世の中は、正体の知れねぇものばかりなのだ。俺にしたって、お前にしたって、一見しただけじゃあわからねぇものを、密かに抱えているだろう。いかに戯作といっても、何でもかんでも白日のもとにさらすのは、野暮でしかねぇのだ。不可解な事は、不可解なままに描くのが一番なのよ。わっちら戯作者は神じゃねぇんだからさ。神どころか、世の底の底を這いずってねぇと、ろくなものは書けねぇんだぜ――」・・・・・・。
「越後の鈴木牧之、その諦めない人生」というが、刊行40年。名著「北越雪譜」はけたはずれだ。
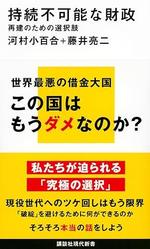 「再建のための選択肢」副題。「物価は上がらないもの」「給料は上がらないもの」「金利は上がらないもの」と3つのノルムに支配された20年余のデフレの日本。今、物価が、目指した2%以上上がり、賃金も2年連続上がり、いよいよ「物価を上回る賃金上昇」のデフレ完全脱却、ノーマルな経済になろうとしている。ここで、「日本銀行は2016年以降続けてきたマイナス金利政策を解除し、わが国においても、本格的な金利上昇局面入りが意識されるようになった」わけだ。ここで「世界最悪の借金大国・日本」「負担なき大盤振る舞いで崖っぷち、世界最悪の借金大国に迫る『危機』」の日本財政を考える著作。
「再建のための選択肢」副題。「物価は上がらないもの」「給料は上がらないもの」「金利は上がらないもの」と3つのノルムに支配された20年余のデフレの日本。今、物価が、目指した2%以上上がり、賃金も2年連続上がり、いよいよ「物価を上回る賃金上昇」のデフレ完全脱却、ノーマルな経済になろうとしている。ここで、「日本銀行は2016年以降続けてきたマイナス金利政策を解除し、わが国においても、本格的な金利上昇局面入りが意識されるようになった」わけだ。ここで「世界最悪の借金大国・日本」「負担なき大盤振る舞いで崖っぷち、世界最悪の借金大国に迫る『危機』」の日本財政を考える著作。
「"財政事情は世界最悪"の国が財政破綻せずにこられた理由」――それは「『何も起こらない』のは利払費が増えずにすんできたから。ずっと横ばいで、2025年度予算案の歳出でも、利払費は10.5兆円」「日銀が国債を買い占めてきたから」「『利払費圧縮』の代償は、日銀財務の悪化」と言い、「我が国でも円安や物価上昇が、このまま続けば、日銀が金利をさらに上げていかなければ、円安もインフレも止められなくなることは自明」と言い、危機を示す。
第2部「シミュレーション 日本の財政はどうなるか」、第3部「聖域なき歳出削減 何をどう減らすか(医療・介護・少子化対策、年金=第3号被保険者制度をまだ続けますか?、地方財政=地方交付税制度は既に事実上破綻状態など)」、第4部「公平・公正な税制と納得できる税負担を考える」の詳細に述べる。
そして、「政党は財政問題から決して逃げず、悲惨なまでに厳しい財政の現実から決して目を背けずに、実効性のある財政再建プランを策定していただきたい」「財源もないのに、大規模な経済対策を打ったり、大規模な減税策を提案するようなことはもうやめていただきたい」「コロナ危機が過ぎ去り、物価が上がり、市場金利が上がり始めた今こそまさに、誰がどれだけ負担するのが良いか、どうやってこの国の財政運営を立て直していけば良いのか、私たち一人一人が真剣に考えるべき時が来ている」と危機を訴える。
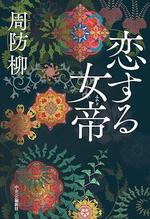 「蘇我の娘の古事記」(周防柳著)も抜群に面白かったが、その時代に続いて2度にわたって皇位にあった女帝高野(阿倍の時代を「孝謙天皇」、重祚後の高野の時代を「称徳天皇」)と道鏡の恋の真相、奈良の都の最大の醜聞の真相を、天智天皇以降の皇統の連綿たる系譜の中で描く。皇位継承の争いと天皇の女心、道鏡の人物像が立体的に浮かび上がってくる。見事な力作。
「蘇我の娘の古事記」(周防柳著)も抜群に面白かったが、その時代に続いて2度にわたって皇位にあった女帝高野(阿倍の時代を「孝謙天皇」、重祚後の高野の時代を「称徳天皇」)と道鏡の恋の真相、奈良の都の最大の醜聞の真相を、天智天皇以降の皇統の連綿たる系譜の中で描く。皇位継承の争いと天皇の女心、道鏡の人物像が立体的に浮かび上がってくる。見事な力作。
21歳で歴史上唯一の女性皇太子となった阿倍は、「我らの輝ける御祖、天武天皇と持統天皇のお二人によって創り出された高御座の業を少しでも永く保て」と愛する父・聖武天皇から玉座を託される。母・光明子は帝聖武の妻である前に、藤原一族の女王であり、藤原氏の世にしようと仲麻呂と組んで画策する。阿倍は仲麻呂を信じ大炊王に譲位するが、用済み扱いとなり、日陰の谷間に追いやられる。失意のなか生きる気力を失った姫太上天皇の病の源を取り除き救ったのが道鏡禅師。阿倍は吉備真備、道鏡らと仲麻呂を討ち果たし、玉座に返り咲き、高野と称する。道鏡は法王に上り詰める。
持統天皇が夫・天武天皇への愛。二人が創り上げた皇統の血を守りぬかんとする高野。それを支える道鏡との激しい恋----。やがて、道鏡が、女帝の寵愛を良いことに、さらなる欲をかいて天皇になろうとしているなどの醜聞がまき散らされる。女帝・高野の追い落としが画策される。皇位継承の激しい争いだ。その中心となるのが、壬申の乱以降、日陰になってきた天智天皇系の者たち。
物語は、衝撃的な歴史の真実に至る。「壬申の乱はなぜ起きたのか」「天智天皇はなぜ天武でなく、愛児・大友皇子を立てようとしたのか」「この国のすめろきの道のあるべき筋とは」「道鏡とは何者であったのか」――。本書は、驚愕の事実を、歴史ミステリーのように、100年の歴史をうねるように描き切る。
歴史を大きく変える「恋する女帝」――。持統天皇の天武天皇への鋼のような愛。女帝高野の道鏡への全身の愛。道鏡の本心。そして男帝の血・・・・・・。歴史は孝謙天皇、称徳天皇を経て、天智天皇系の白壁王、そして桓武天皇に引き継がれていくのだが、その意味が明かされていく。
奈良の都、女帝と道鏡の醜聞の真相が、100年にわたる皇位継承の争いの根源から解き明かされる。ギラギラした道鏡ではなく、透明感と深い思索と溢れる愛を抑制する奥行きのある男として描く。
歴史の謎と情愛のうねりを剔抉、解明する素晴らしい傑作。
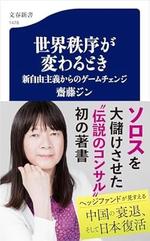 「新自由主義からのゲームチェンジ」が副題。齋藤さんは1993年に単身で渡米。ヘッジファンドを始めとするプロの資産運用者に各国政府の経済政策分析等の助言をするコンサルタント。仕事柄、外に情報は出さないが、本書は初の著書。「世界はアメリカを地殻変動の震源地とする『大転換』のただ中にあり、これから起きる変化は、日本にとって有利なものになる」「日本は今、数十年に1度の千載一遇のチャンスを迎えている。東西冷戦後の『新自由主義』が崩壊し、勝者と敗者がひっくり返る"ゲームチェンジ"が来ているのだ」と言う。大変刺激的で、激しく微妙なマネーの世界に長くいるだけに、クリアで明快。特に「カジノのオーナーはアメリカ」――そのアメリカはどう考えているかを見ている点、世界秩序が変わる、世界観が変わることを実感している点、日本の「失われた30年」を見ているが故に、説得力がある。帯に、「ソロスを大儲けさせた"伝説のコンサル"初の著書。ヘッジファンドが見すえる中国の衰退、そして日本の復活」とある。
「新自由主義からのゲームチェンジ」が副題。齋藤さんは1993年に単身で渡米。ヘッジファンドを始めとするプロの資産運用者に各国政府の経済政策分析等の助言をするコンサルタント。仕事柄、外に情報は出さないが、本書は初の著書。「世界はアメリカを地殻変動の震源地とする『大転換』のただ中にあり、これから起きる変化は、日本にとって有利なものになる」「日本は今、数十年に1度の千載一遇のチャンスを迎えている。東西冷戦後の『新自由主義』が崩壊し、勝者と敗者がひっくり返る"ゲームチェンジ"が来ているのだ」と言う。大変刺激的で、激しく微妙なマネーの世界に長くいるだけに、クリアで明快。特に「カジノのオーナーはアメリカ」――そのアメリカはどう考えているかを見ている点、世界秩序が変わる、世界観が変わることを実感している点、日本の「失われた30年」を見ているが故に、説得力がある。帯に、「ソロスを大儲けさせた"伝説のコンサル"初の著書。ヘッジファンドが見すえる中国の衰退、そして日本の復活」とある。
トランプ現象も、欧州における極右や自国中心主義の台頭も、新自由主義的価値観の崩落、新自由主義への反乱が背景にある。「小さな政府」の価値観の崩落だ。それが詳しく述べられる。
冷戦下は米ソ対立のなか、「カジノのオーナー」のアメリカは日本を支援、日本は繁栄を謳歌した。しかし、新自由主義へのパラダイムシフトが起きた時、アメリカはその変化をうまく乗り切ると同時に、冷戦下で「(大きな政府時代)勝ちすぎた日本を、勝てないテーブルに座らせた」と言う。この「大きな政府、新自由主義」の恩恵を最も受けたのが中国。日本はデフレのノルムに沈んだ。それが今、「新自由主義という様々な行動の根底にあった世界観が瓦解し、勝者と敗者が入れ替わると確信している」と言うのだ。分析は詳細だ。
日本は、世界が構造改革をするなか、「雇用を守ろうとした」。損切りすべきところ、「雇用」を守り、人件費も物価も下がったままだった。賃金カットを受け入れる代わりにクビを切らない。失業率を上げない。新しい成長局面に入ることができない。それが30年デフレだ。
しかし30年経ち、新自由主義を潰そうとするトランプ現象。米中対立から経済的にも中国を嫌悪し抑え、一方でパートナーとして日本を重視するアメリカ。さらに日本国内では、人手不足時代になり、賃金を上げなければ人が来ない。賃金を上げ、インフレ基調になる新しい風が吹いてきたのだ。物価を上回る賃金上昇が現実になってきている。それはまた高付加価値化を迫られることでもあり、最も生産性が低いサービス業も、AI、デジタル化をしなければ、生きていけない時代となったのだ。「日本復活の大チャンスが到来した」と言う。
これらが実に丁寧に鋭く説明される。語ってると言ってもいい。「失われた30年の本質」「中国は投資対象ではなくなった」「強い日本の復活」「新しい世界にどう備えるか」を詳述する。「小泉・竹中が新自由主義を進めた」などは、アメリカから見ると誤解、「雇用を守る」だったのではないかとも言っている。
 「認知症になったら理性や人格が壊れ、何もわからなくなってしまう」というのは誤り。「認知症になったらおしまいではない。自分でできることと、できないことがある。できないことがあるのは不安だが、できないことの中にも少しはできるものがある」「認知症は何もわからなくなった人ではない」――。「長生きすれば認知症になるのは自然なこと。あなたの人格も心も失われることはないのです」「高齢者のアルツハイマー型認知症は病気ではない」(松下正明東京大学名誉教授)。長い間に刷り込まれてしまった歪んだ認知症観を変え、認知症の人の本質を見なくてはいけない。そして認知症になっても、幸せに生きる社会を目指そうと訴える。
「認知症になったら理性や人格が壊れ、何もわからなくなってしまう」というのは誤り。「認知症になったらおしまいではない。自分でできることと、できないことがある。できないことがあるのは不安だが、できないことの中にも少しはできるものがある」「認知症は何もわからなくなった人ではない」――。「長生きすれば認知症になるのは自然なこと。あなたの人格も心も失われることはないのです」「高齢者のアルツハイマー型認知症は病気ではない」(松下正明東京大学名誉教授)。長い間に刷り込まれてしまった歪んだ認知症観を変え、認知症の人の本質を見なくてはいけない。そして認知症になっても、幸せに生きる社会を目指そうと訴える。
認知症とは、認知機能が障害を受け、脳の神経細胞が壊れて記憶などの認知機能が低下し、日常の生活に支障をきたすようになった状態。アルツハイマー型認知症、血管性認知症、これにレビー小体型認知症、前頭側頭型認知症を加えると、92.4%になる。この中で圧倒的多数を占めるのがアルツハイマー型認知症で67.6%に及ぶ。しかもアルツハイマー病の1番のリスク・ファクターは年齢であるゆえに、老年期のアルツハイマー型認知症だけが増えているわけだ。神経細胞の周りに、アミロイドβたんぱくという物質が蓄積して、神経細胞に障害をきたす。この変化は、脳の老化現象の現れであると理解すると、アルツハイマー型認知症は病気ではなく、脳が年をとってきた証に過ぎない。まさに「認知症は病気ではない」と言う。
2025年、認知症高齢者数は471.6万人、MCI高齢者数は564.3万人と推計されている。合わせれば1000万人を超える。70歳代後半では10人に1人だが、80歳代前半になると10人に2人に増え、85歳からは実に10人に4人と急増する。90歳代前半になると10人に6人という。アルツハイマー型認知症が、脳の老化現象の表れと理解すれば、「95歳以上になると10人に8人が認知症」というのもよくわかる。そして著者は「認知症は病気ではなく老化。心の中は私たちと同じだ」と指摘する。
認知機能の低下で日常生活に支障が出てくるのが中核症状で生活障害を招くことになる。しかし、二次的に引き起こされる周辺症状がある。
「周辺症状」と「BPS D」――徘徊や暴言・暴行、物盗られ妄想など深刻な問題だ。国際的には周辺症状が「BPSD(認知症の行動・心理症状)」と言われる。本書はこの家族を悩ませている「徘徊」「物盗られ妄想」「暴言・暴行」について、認知症の人が綴った「手記」を手がかりに、それらが引き起こされる背景について徹底的に検証している。納得する。これらは、人間関係のズレなどから生まれたものがほとんどであることを示す。どうやって改善もしくは軽減させたか。この周辺症状が「病気」の症状では無いこと。家族に何ができるか。「とにかく笑うこと」「生きがいが暴言を抑えた」「居場所が不安を和らげる」などの実例が紹介される。認知症の人の心の声を徹底して聞く。そして支える。すごい努力が身に迫ってくる。辛くて暗い闇が晴れてくる。
「共生」と言うが、「認知症とともに生きる」とは、「自分が認知症になっても、認知症の症状を抱えながら幸せに生きる」ことであることがよくわかる。すべての人に読んでもらいたい本だ。

