 宇喜多直家の嫡子・宇喜多八郎秀家。仕物(暗殺)で名をはせ謀略の限りを尽くした梟雄・直家に比べ、育ちも良いが、凡庸ではない。時は戦国、西には毛利、東には秀吉・家康等に挟まれて苦難の連続。幼くして天正9年(1581年)に父・直家が病死、翌年には本能寺の変、紀州討伐、小田原征伐、朝鮮遠征、伏見城や杭瀬川の戦い、そして関ケ原、逃亡して薩摩、50年にもわたった八丈島。秀吉から寵愛を受けるが、晩年の秀吉は常軌を逸していたし、その後の家康の知謀・圧力はすさまじい。しかも「宛行」をめぐっての家中の騒動も激しい。
宇喜多直家の嫡子・宇喜多八郎秀家。仕物(暗殺)で名をはせ謀略の限りを尽くした梟雄・直家に比べ、育ちも良いが、凡庸ではない。時は戦国、西には毛利、東には秀吉・家康等に挟まれて苦難の連続。幼くして天正9年(1581年)に父・直家が病死、翌年には本能寺の変、紀州討伐、小田原征伐、朝鮮遠征、伏見城や杭瀬川の戦い、そして関ケ原、逃亡して薩摩、50年にもわたった八丈島。秀吉から寵愛を受けるが、晩年の秀吉は常軌を逸していたし、その後の家康の知謀・圧力はすさまじい。しかも「宛行」をめぐっての家中の騒動も激しい。
「強き者、弱き者にかかわらず、健やかに過ごせる。そんな楽土をつくる。民のために干拓する」――。父・直家の心を真っすぐに受け、秀家は濁流のなか懸命に走る。家康はいう。「わしは流されただけにすぎませぬ。流れに逆らった者はことごとく滅びます」「才覚ゆえではない。流れにだれよりも従順だった」――。秀家は「私は内府殿とはちがいます。この生き方は変えられませぬ」「父の直家もまた、流れに抗いつづけた人生だったではないか。その最たるものが、この干拓地だ」「宇喜多の領国のために戦う。豊臣家や秀頼を滅ぼさんとする流れに、全力で抗う」と誓う。
激流のなかで秀家は敗北の将でもあり、時流に抗い続けた人生に見える。しかし、策に溺れず情をもつ丈夫の生き方からか、いざ逆流の極みとなった時に、必ず守る人が現われるのだ。とくに正室となった前田利家の娘・豪姫の存在はゆるぎない。心の柱だ。
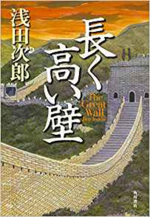 日中戦争の最中の1938年。当代きっての流行探偵作家の小柳逸馬は、従軍作家として北京に派遣されていたが、検閲班長の川津中尉とともに、前線である万里の長城への移動を命ぜられる。その張飛嶺で待ち受けていたのは、第一分隊10名が全員死亡するという事件だった。
日中戦争の最中の1938年。当代きっての流行探偵作家の小柳逸馬は、従軍作家として北京に派遣されていたが、検閲班長の川津中尉とともに、前線である万里の長城への移動を命ぜられる。その張飛嶺で待ち受けていたのは、第一分隊10名が全員死亡するという事件だった。
二人は、事件解明に直ちに着手し、関係者を聴聞する。「匪賊からの襲撃か」「分隊内での恨みつらみ、内輪揉めか」・・・・・・。そこには軍人のかかえる嘘と体裁、規律のゆるみ、親を殺され妻を辱められ焼き尽くされた中国人の憎悪があった。そしてたどり着いたのは「そもそもこの戦争には、大義がないのではないか」「戦いながら大義を探しているのではないか」「要するに日本は、わけのわからない、戦いの理由がわからない戦争をしている。そんな戦争の中で日本軍は軍隊としての正体をなくし、謀略がすっかり習い性になってしまった」という根源的なやり切れない闇だ。その闇と嘘の隠蔽の重ね役として、小柳は従軍作家として派遣されたことを悲しみのなかで思うのだ。感情を押し殺して・・・・・・。
子どもの脳は、生まれてからずっと成長・発達途上にあり、我々が想像している以上に柔らかく、傷つきやすい。とりわけ最も身近で安全な場所であるはずの親から「攻撃」を受けると、深いダメージを受けてしまう。マルトリートメント(不適切な養育)が、外から見える傷はなくとも子どもの脳を"物理的"に傷つけ、変形させる。言葉のDVはより脳に大きなダメージを与えるという。
友田さんは小児精神科医として、子どもの発達に関する臨床研究を続け、「日常のなかにも存在する不適切な養育」「マルトリートメントによる脳へのダメージとその影響」を示し、「子どもの脳がもつ回復力を信じ」て専門的な療法を提示する。親も子どもも専門的で粘り強い治療が大切となる。そして、「健やかな発育に必要な愛着形成」「マルトリートメントからの脱却」の新たな試みを示す。
私たちの子どもの頃は、もっとひどい体罰等が行われていたと思われるが、「愛着」という観点から見ると、今の親が孤立し、ストレスをため、子どもを追い込んでいること、また子どものレジリエンスを伸ばせないでいることも理解できる。本書での警鐘を真正面から受け止めたい。













