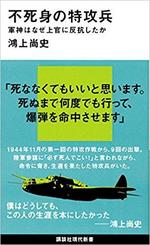 「軍神はなぜ上官に反抗したか」が副題。9回出撃して9回生還した特攻隊員の佐々木友次さん。「臆病者」「なぜ死なないのだ」「なんで貴様ら、帰ってきたんだ。貴様らは人間のクズだ」と罵られ、「処刑飛行」までされた佐々木さんは答える。「私は必中攻撃でも死ななくてもいいと思います。その代わり、死ぬまで何度でも行って爆弾を命中させます」・・・・・・。
「軍神はなぜ上官に反抗したか」が副題。9回出撃して9回生還した特攻隊員の佐々木友次さん。「臆病者」「なぜ死なないのだ」「なんで貴様ら、帰ってきたんだ。貴様らは人間のクズだ」と罵られ、「処刑飛行」までされた佐々木さんは答える。「私は必中攻撃でも死ななくてもいいと思います。その代わり、死ぬまで何度でも行って爆弾を命中させます」・・・・・・。
神風特攻隊については、幾多もの本が出版され、「悠久の大義に殉ずる」などの一言ではとても表わせない言語絶する世界の苦悶・沈黙が知られるようになっている。本書がド迫力で迫ってくるのは、「命令された側」の生の証言であることとともに、「特攻隊とは何であったのか」「なぜ愚かな特攻を続けるに至ったか」を、支配・被支配、戦争という異常時における組織と人間、国民・マスコミの熱狂、過剰な精神主義とリアリズム、「異常」への責任回避・転嫁、日本における「世間」と「社会」、思考の放棄と「集団我」、「当事者」の沈黙と「傍観者」の饒舌、日本文化と戦争など・・・・・・。まさに構造的に深く広く剔抉しているからである。それゆえに佐々木さんの「寿命ですよ」という言葉、岩本益臣隊長や美濃部正少佐等の勇気と存在が心に響く。現在の社会・組織と人間の問題を考えさせられる。
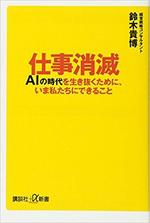 2035年には世界的に多くの人がAIとロボットの進化によって、職を失うことになる。ロボットは仕事を奪っていくが、医療・介護・各種サービス・インフラ整備をはじめ人手不足を補うとともに、生産がボトルネックとなって急に"仕事消滅"にはならないが、AIは違う。人類を超える汎用的でかつ世界最高レベルの頭脳が開発されれば、数十分でデジタルコピーができる。ゆえに、本当に心配すべきは肉体労働の仕事ではなく頭脳労働の仕事であり、2030年代以降、急速度に"仕事消滅"が進む。"ディープラーニング"というAI分野のブレークスルーで、今、50年来の大ジャンプが起きたという。AI上司の下で働く時代はそう遠くない。
2035年には世界的に多くの人がAIとロボットの進化によって、職を失うことになる。ロボットは仕事を奪っていくが、医療・介護・各種サービス・インフラ整備をはじめ人手不足を補うとともに、生産がボトルネックとなって急に"仕事消滅"にはならないが、AIは違う。人類を超える汎用的でかつ世界最高レベルの頭脳が開発されれば、数十分でデジタルコピーができる。ゆえに、本当に心配すべきは肉体労働の仕事ではなく頭脳労働の仕事であり、2030年代以降、急速度に"仕事消滅"が進む。"ディープラーニング"というAI分野のブレークスルーで、今、50年来の大ジャンプが起きたという。AI上司の下で働く時代はそう遠くない。
"仕事消滅"の大変化は、2025年自動運転車の登場によってタクシーやトラックドライバーの仕事が世界中で消えていくことが幕開けとなる。
大失業時代という災厄ではなく、幸せの転機にするにはどうしたらいいのか。「働くロボットに人間と同等の給料を支払うという社会ルールを作る」「ロボットの給料を国に支払う」という解決策が示される。ロボットで稼いだお金は、経済発展の中で、全国民が受け取るベーシック・インカムにするという考え方だ。そして「今世紀の人類は、AIやロボットと共存し、仕事を分担しながら働いた方が、最大多数の最大幸福という意味で、一番いい」という。「AIの時代を生き抜くために、いま私たちにできること」が副題だ。
28日、東京北区西が丘にある「味の素ナショナルトレーニングセンター」(NTC)が開設して10年を迎え、センター内で10周年の記念式典・祝賀会が行われました。これには公明党から富田茂之、浮島智子、佐藤英道の各衆院議員、公益財団法人日本体育協会の伊藤雅俊会長、公益財団法人日本レスリング協会の福田富昭会長(初代NTCセンター長)、NTCの山下泰裕センター長をはじめ多くの関係者が出席しました。
私は、2001年完成の国立スポーツ科学センター、2007年のNTCの建設を強く推進してきましたが、現在、拡充棟(第二トレセン)の工事が行われています。これらはパラリンピック選手も使用できる施設です。2019年5月に完成の予定です。
私は挨拶で、「10年前の開設時にテープカットをしたことを思い起こす。この10年、アスリート強化に最も貢献した施設だ」と感慨をもって話しました。
2020年東京オリパラに向け、最重要の施設であり、更なる充実に力を注いでまいります。
 「珍説トンデモ説は、いちいち批判せずに黙殺すべきだ」――これが日本史学界の共通認識だが、無関心を決め込めば、陰謀論やトンデモ説は生き続ける。「誰かが猫の首に鈴をつけなければならない」と本書を著した理由を語る。陰謀論は人気があるが、「因果関係の単純明快すぎる説明」「憶測や想像で話を作る"論理の飛躍"」「結果から逆行して原因を引きだす(結果からの逆算)」「挙証責任を批判者側に転嫁」などの特徴をもつ。面白いが危い。歴史は過去も現在も複雑な営みのなかで刻まれ、単純ではない。文献も「勝者の歴史」となり偽書も多い。しかし、歴史学の実証的な手法に則って進み、「人びとが陰謀論への耐性をつける一助に」と、日本中世史を整理・分析、そして陰謀論・俗説を斬る。情報社会の現代にも通じ、警鐘を鳴らす。
「珍説トンデモ説は、いちいち批判せずに黙殺すべきだ」――これが日本史学界の共通認識だが、無関心を決め込めば、陰謀論やトンデモ説は生き続ける。「誰かが猫の首に鈴をつけなければならない」と本書を著した理由を語る。陰謀論は人気があるが、「因果関係の単純明快すぎる説明」「憶測や想像で話を作る"論理の飛躍"」「結果から逆行して原因を引きだす(結果からの逆算)」「挙証責任を批判者側に転嫁」などの特徴をもつ。面白いが危い。歴史は過去も現在も複雑な営みのなかで刻まれ、単純ではない。文献も「勝者の歴史」となり偽書も多い。しかし、歴史学の実証的な手法に則って進み、「人びとが陰謀論への耐性をつける一助に」と、日本中世史を整理・分析、そして陰謀論・俗説を斬る。情報社会の現代にも通じ、警鐘を鳴らす。
「保元の乱を起こしたのは崇徳側ではなく、国家権力を掌握していた後白河側」「義経は陰謀の犠牲者ではなく、義経の権力は砂上の楼閣だった」「後醍醐天皇は黒幕でなく被害者だった」「足利尊氏の挙兵は自衛行動であり、積極的主体的に後醍醐を裏切ったわけではない」「応仁の乱の元凶とされた日野富子はスケープゴート」「本能寺の変に黒幕はいない。突発的な単独犯行。騙されやすかった信長と、秀吉の"理外の理"の行動」「関ヶ原は家康の陰謀ではなく、上方での大規模蜂起は想定外で絶体絶命の危機に陥った」・・・・・・。
そして「虚々実々の謀略戦はフィクションとしては面白いが、現実の歴史とは異なる。勝負というものは、双方が多くの過ちを犯し、より過ちが少ない方が勝利するのである」という。





