4月21日、北海道石狩市に行き、この度オープンする「道の駅石狩『あいろーど厚田』」の開業記念パーティー式典に参加し、挨拶をしました。これには、田岡克介石狩市長、佐藤英道衆院議員、横山信一参院議員、和田義明・自民党衆院議員らが出席しました。
この道の駅は、日本海に沈む壮麗な夕日で知られる厚田に建設されたもので、私が国交大臣時代に「重点・道の駅」として認可をしたものです。地元産の新鮮な農産物や、石狩湾を一望できる展望台を備えています。また、厚田の自然や歴史のほか、厚田出身の著名人である戸田城聖・創価学会第二代会長、勝海舟や座頭市などで知られる子母澤寛、横綱吉葉山などの郷土資料室を開設しています。
私は「多くの皆さんの真心が一つの結晶となって生まれた素晴らしい道の駅ができた」「新たな北海道の文化・経済拠点として、またインバウンドの糾合スポットとして、さらに発展することを期待している」と挨拶をしました。夕刻に行われたイベントでしたが、3階の展望室から見た夕日はきわめて素晴らしく印象的でした。
 オルテガやホイジンガに触れ、西部さんの「大衆への反逆」を読んだのが30年以上も前、「死生論」からも20年。今年1月に自裁した西部さんの絶筆の書だけに、言葉は精緻に選び抜かれ、諦観のなかにも激しく、率直に語り、静かに吐く。副題は「JAP.COM 衰滅の状況」――。「今さら歎いても詮無いが、僕が残念至極なのは大東亜戦争の敗北まではかろうじて残っていた日本民族の羞恥心・公平心・正中(的を射ていること)・勇強心がほとんど消滅してしまっている現状を、僕はJAP.COMの『衰滅』と形容したいのである」という。
オルテガやホイジンガに触れ、西部さんの「大衆への反逆」を読んだのが30年以上も前、「死生論」からも20年。今年1月に自裁した西部さんの絶筆の書だけに、言葉は精緻に選び抜かれ、諦観のなかにも激しく、率直に語り、静かに吐く。副題は「JAP.COM 衰滅の状況」――。「今さら歎いても詮無いが、僕が残念至極なのは大東亜戦争の敗北まではかろうじて残っていた日本民族の羞恥心・公平心・正中(的を射ていること)・勇強心がほとんど消滅してしまっている現状を、僕はJAP.COMの『衰滅』と形容したいのである」という。
「自尊・自立――他者や他国に従属することによって安全に生存したとしても、そんな人生や時代の生は、精神的動物としての人間にとって自尊と自立を喪失した果てで空無感や屈辱感をもたらして御仕舞となる」「安全と生存を最高の価値としてきたために戦後日本は(独立と自尊を枯死させ)哀れな民人となってしまった」「瀕死の世相における人間群像――スマホ人・選挙人(朽ちんばかりの病葉の群れ)、いのちの無条件礼賛の『いのち人』、虚言人(言論、世論、ライターのリアリティからの逃走)、法匪人、大量人と模流社会、タダ人、心を亡くす多忙人、エチケット知らずの無礼人、立憲人、根拠なき臆説のメディア人」「社会を衰滅に向かわせるマスの妄動」「近代の宿痾の自由・民主・進歩」「"平和日本とはパワーレス国家"とするのは、児戯にすら及ばない錯乱の国家論だ」「ピープル(一般庶民)の利益を守らんとするポピュリズム(人民主義)とメディアのムードに乗るポピュラリズム(人気主義)の区別すらできていないのが今の民主主義者どものオピニオン」「近代化と大衆化が列島人を劣等にした」「重要なのは国民社会を『公共性の規範』へと繋ぎ止めることであり、自由と秩序の間の平衡としての『活力』、平等と格差の間の平衡としての『公正』、博愛と競合の間の『節度』、合理と感情の間の『良識』だ」・・・・・・。貧しい憲法論議、民主主義の辿り着く先の衆愚、戦後の虚構を、前提から露わにする。
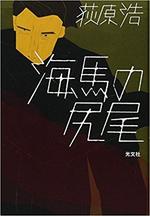 度外れた狂暴、制御のきかない狂気のヤクザ及川頼也。組自体が手を焼いて病院行きを命ぜられると、アルコール依存症どころか、「恐怖心の欠如、他者に対する共感力の欠如、良心がない」という「反社会性パーソナリティ障害」の診断が下る。脳の欠陥だ。大脳辺縁系の海馬とその尻尾のところにある扁桃体(視覚、聴覚、嗅覚その他の外的な刺激に反応して、快、不快、恐怖、緊張、不安、痛みなどの情動を生み出す場所)の異常、「感じる脳」の欠陥というわけだ。ヤクザの暴力抗争がテンポよく展開されると思いきや、話は一転して脳、染色体、遺伝子の世界へと急深化する。
度外れた狂暴、制御のきかない狂気のヤクザ及川頼也。組自体が手を焼いて病院行きを命ぜられると、アルコール依存症どころか、「恐怖心の欠如、他者に対する共感力の欠如、良心がない」という「反社会性パーソナリティ障害」の診断が下る。脳の欠陥だ。大脳辺縁系の海馬とその尻尾のところにある扁桃体(視覚、聴覚、嗅覚その他の外的な刺激に反応して、快、不快、恐怖、緊張、不安、痛みなどの情動を生み出す場所)の異常、「感じる脳」の欠陥というわけだ。ヤクザの暴力抗争がテンポよく展開されると思いきや、話は一転して脳、染色体、遺伝子の世界へと急深化する。
抗争のなか身を隠すことを余儀なくされた及川は、8週間の長期入院治療を受けるが、そこには、反社会性パーソナリティ障害の者だけでなく、その逆の意味で他者への共感力が高いために恐怖の概念が薄くなるウィリアムズ症候群の子どもや、他の感情はコントロールできても恐怖という感情のみ抜け落ちているウルバッハ・ビーチ病の者、PTSDに苦しむ青年たちがいた。
そこで及川たちは、気づくのだ。自分たちは邪魔者扱いされ、異常者として社会から抹殺されようとしている。弱者を切り捨て、多様な生き方を認めない社会になっている。科学の進歩史観の安易さのなかで、実験材料としてモノとして使い捨てられようとしている。ヤクザのバイオレンスから人間生命と医療・科学・文明を考えさせる奥深い世界に一気に引き込まれる異色の力作。
「ふざけるな。俺たちはモルモットじゃねえんだぞ」・・・・・・。
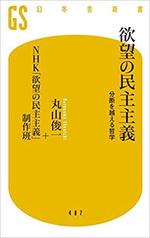 NHK、BS1スペシャル「欲望の民主主義~世界の景色が変わる時~」で、「世界の知性」たちへのインタビューを行った記録。副題は「分断を越える哲学」。問題意識は、英のEU離脱や米のトランプ大統領誕生、そして仏の急進的な右翼の台頭、世界で頻発するテロ・・・・・・。このなかから世界の民主主義に何が起きているかの問いかけだ。民主主義の劣化、熱意の希薄化、破壊衝動、ネット社会の影響、グローバル化、分断の構図、人間の欲望と集合体の社会などを考察する。
NHK、BS1スペシャル「欲望の民主主義~世界の景色が変わる時~」で、「世界の知性」たちへのインタビューを行った記録。副題は「分断を越える哲学」。問題意識は、英のEU離脱や米のトランプ大統領誕生、そして仏の急進的な右翼の台頭、世界で頻発するテロ・・・・・・。このなかから世界の民主主義に何が起きているかの問いかけだ。民主主義の劣化、熱意の希薄化、破壊衝動、ネット社会の影響、グローバル化、分断の構図、人間の欲望と集合体の社会などを考察する。
いずれの「知性」からもホッブス、ルソー、トクヴィル、そして現在が語られる。「万人の万人に対する闘争」を回避するには、自らの欲望を制御し、畏怖する「リヴァイアサン」を打ち立て、国家と契約を結ぶことによって秩序を回復する。ホッブス、ルソーの国家・主権・自由の原始的概念だ。トクヴィルが発見した米の民主主義の良質の部分、中間共同体・市民団体等の活動が、ツイート・ITで崩される現実も語られる。民主主義が衆愚政治や多数者の専制(少数派の抑圧)に陥ることを警戒したベンサムやミルも今、蘇る。
「世界は存在しない。一角獣は存在する」といったマルクス・ガブリエル。「超越した世界」という存在こそが対立を生む。世界を実体化する危険性は、対話のない無数の"正義"の主張の氾濫を生む。ガブリエルは「民主主義とは悪を認識して正す手続き」「倫理観の進歩に照らし合わせて、法律自体を改正すべきです」「民主主義は社会の倫理観の進歩を実践に照らしたもの」「民主主義は、手続きや制度の中で普遍的価値を実現しようとする試み」といい、「民主主義の世界的価値観が崩壊したら、見たこともない規模の戦争(暴力)の世界を目撃する。(民主主義は)今のところ人間がみんなで生き残るための唯一の選択肢」という。民主主義のポテンシャルを引き出せるかどうか、ということだろう。
グローバル化、共同体に参入してくる外国人・移民、格差の拡大、共同体からの孤立化になりかねないIT・AIの時代、代表制民主主義に内包される代表者と有権者のズレ(民主主義の隙間風)、民主主義の主人公でなく阻害されていると感じる者の増大と分極化・・・・・・。「自分たちのことは自分たちの手によって決める。政治参加で世を変える。弱肉強食の世界を避ける」――「自分とは異なる存在を欲望することで自らの欲望を実現する」「民主主義とは自らを問うものだ」との識者の発言は重い。









