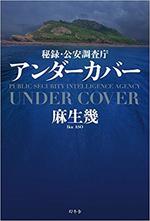4月12日、沖縄市に行き、沖縄市長選挙(4月15日告示、22日投開票)に立候補するくわえ朝千夫現市長の総決起大会に出席し、挨拶をしました。
これには、自民党の竹下亘総務会長、公明党の遠山清彦衆院議員のほか、自民、公明、維新の国会議員、県会議員らが駆け付けました。
私は「くわえ市長は沖縄県、沖縄市の大きなエンジンである」「政治は結果。仕事をすることだ。この4年間で幼稚園給食の導入、子ども医療費無料化の小学校3年までに拡充、そして、2023年にFIBA バスケットボールワールドカップの沖縄市に誘致など実績は豊富」「一万人のアリーナ建設は市発展の起爆剤になる」と訴えました。
くわえ朝千夫市長は「東部海浜地区開発や一万人規模アリーナ建設し、市の発展とともに子どもたちに夢と希望を与えたい」と切々と訴えました。
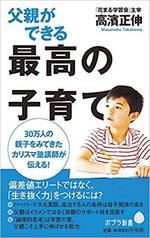 テレビで講演を聞いたこと、さらに「読解力」「意味を考える力」をどう獲得するかを考えていたこともあって、高濱さんの本を読んだ。2050年以降も「生きる」今の子どもが「生き抜く力」を身につけるにはどうしたらよいか。父親の役割は大きいようだ。
テレビで講演を聞いたこと、さらに「読解力」「意味を考える力」をどう獲得するかを考えていたこともあって、高濱さんの本を読んだ。2050年以降も「生きる」今の子どもが「生き抜く力」を身につけるにはどうしたらよいか。父親の役割は大きいようだ。
まずは、「家庭での父親の第一義的仕事はあくまで『妻を笑顔にすること』、そして『母親が安心して育児に取り組めるように支えてあげること』」という。子どもの心身の成長、学力の伸びは、妻の笑顔からということだ。とくに父親は「正しい会話、意味のある会話を日常的に心がけること、論理的思考を伸ばすこと」に努めることだ。言葉の厳密さは学力に比例し、言語感覚は日常会話でしか培われない、という。
妻からの相談ごと、会話には、「解決してあげる」と思わないで「寄り添う」「共感」「聞くこと」にこそ価値がある。そして、「子どもに何かひとつ自信をもたせること」を養うことが大切であり、「子どもの自信、生き抜く力は、親が養ってあげるもの。照れずに本音でぶつかること、取り組むこと」を示す。