豪栄道が全勝優勝――。境川部屋は私の地元、足立区舎人にあり、日常的に交流。この9月上旬も部屋の稽古に行き、力士を激励しました。それがカド番脱出どころか奇跡的ともいえる復活の全勝優勝。26日夜は恒例の千秋楽打ち上げパーティーが一転して、爆発的な大祝勝会となり湧き上がりました。私は「カド番、ケガを乗り越えての優勝。とくに大関になってからの2年は、肩の骨折、手首や足の負傷など、本当に苦しかったと思う。身近で辛い戦いを見てきただけに、心の底から『本当におめでとう』といわせて頂きます」と挨拶をしました。
境川部屋の稽古は角界でも有数の厳しいことで有名。また地域の町会・自治会の人からも愛され、守られています。いつも厳しい境川親方の感激ぶりもひとしおでした。
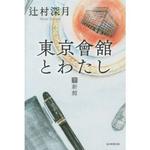 東京、丸の内にある東京會舘は今、建て直し中――。創業は大正11年(1922)。政財界のパーティーや結婚披露宴、芸能界のスターによるディナーショー、芥川賞・直木賞の記者会見や贈呈式も行われ、レストラン等も行き届いており、ファンも多い。創業10か月後にはなんと関東大震災で被害にあい、昭和15年には大政翼賛会の本部(建物の名前は大東亜会館に変更)、戦後はGHQに接収される(アメリカンクラブ・オブ・トーキョーとなる)。昭和44年には建てかえが決まり、12月クリスマスイブには"さよならパーティー"が行われ、新しい東京會舘として、私たちが親しく使わせていただいてきた。
東京、丸の内にある東京會舘は今、建て直し中――。創業は大正11年(1922)。政財界のパーティーや結婚披露宴、芸能界のスターによるディナーショー、芥川賞・直木賞の記者会見や贈呈式も行われ、レストラン等も行き届いており、ファンも多い。創業10か月後にはなんと関東大震災で被害にあい、昭和15年には大政翼賛会の本部(建物の名前は大東亜会館に変更)、戦後はGHQに接収される(アメリカンクラブ・オブ・トーキョーとなる)。昭和44年には建てかえが決まり、12月クリスマスイブには"さよならパーティー"が行われ、新しい東京會舘として、私たちが親しく使わせていただいてきた。
激動の時代を「東京會舘」が見たもの、その舞台での人間ドラマを、辻村深月さんが東京會舘を支えてきた各部門の職員の心にもふれつつ10話として描く。権力者側の歴史のドラマではない。庶民の人間模様、心情がいずれも心の奥底に響いて感動する。「クライスラーの演奏会(大正12年)」「最後のお客様(昭和15年)」「しあわせな味の記憶(昭和39年)」「金環のお祝い(昭和51年)」「星と虎の夕べ(昭和52年)(越路吹雪の姿)」「煉瓦の壁を背に(平成24年)(直木賞受賞者)」など、いずれもじわーとくる。
 進化を続ける石炭火力発電――。石炭火力の問題は、CO2排出の問題と、エネルギーに変える効率をいかにあげるかという2つです。9月23日、神奈川県横浜市磯子区の磯子火力発電所を、斉藤鉄夫衆院議員、上田勇衆院議員、佐々木さやか参院議員、和田卓生、望月康弘、竹野内猛、高橋正治ら各横浜市議とともに視察しました。
進化を続ける石炭火力発電――。石炭火力の問題は、CO2排出の問題と、エネルギーに変える効率をいかにあげるかという2つです。9月23日、神奈川県横浜市磯子区の磯子火力発電所を、斉藤鉄夫衆院議員、上田勇衆院議員、佐々木さやか参院議員、和田卓生、望月康弘、竹野内猛、高橋正治ら各横浜市議とともに視察しました。
この横浜磯子区にある磯子火力発電所(電源開発株式会社)は、最新の環境対策設備を備えるとともに、発電熱の高効率化を実現。環境負荷低減とエネルギー効率向上を両立したコンパクトで世界最高水準の都市型石炭火力発電所です。
昭和42年5月から稼働している同発電所は、東京湾に面する13の火力発電所の中で唯一の石炭による火力発電所。環境対策が進み、平成14年に1号機、平成17年に2号機が運転を開始――。旧発電所に対し発電力は2.2倍、発電熱効率は5%もあがりCO2は17%も削減しました。煙突からの煙は全く見えなく、世界で最もクリーンな石炭火力発電所となっており、世界からも次々と視察団が訪れています。
エネルギー政策は国にとって極めて重要な政策。エネルギーの確保、再生エネルギーの拡充、温室効果ガスなどの環境対策の両立にさらに力を入れます。
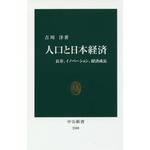 「長寿、イノベーション、経済成長」と副題にあるが、きわめて平易に経済の本質を示している。人口減少が進み、財政赤字は拡大し、地方消滅の危機が叫ばれている。そして、経済成長はムリ、望むことではない、ゼロ成長の定常社会論などが提起されるようになっている。吉川さんは、実は人口減少も含めてそれらは、ロバート・マルサス、アダム・スミス、デイビッド・リカード、そしてケインズ以来論じていたことだと指摘する。そして今、日本に蔓延する「人口減少ペシミズム」を排すること。とくに日本の企業がこの「人口減少ペシミズム」を克服することが、カギを握っている。人口減少は大きな問題だが、日本経済の「成長」については「人口減少ペシミズム」が行きすぎている。高齢社会等の社会の変化は、人が安全・安心・豊かに生きるための新しい需要、高い購買力を要請しているではないかと指摘する。
「長寿、イノベーション、経済成長」と副題にあるが、きわめて平易に経済の本質を示している。人口減少が進み、財政赤字は拡大し、地方消滅の危機が叫ばれている。そして、経済成長はムリ、望むことではない、ゼロ成長の定常社会論などが提起されるようになっている。吉川さんは、実は人口減少も含めてそれらは、ロバート・マルサス、アダム・スミス、デイビッド・リカード、そしてケインズ以来論じていたことだと指摘する。そして今、日本に蔓延する「人口減少ペシミズム」を排すること。とくに日本の企業がこの「人口減少ペシミズム」を克服することが、カギを握っている。人口減少は大きな問題だが、日本経済の「成長」については「人口減少ペシミズム」が行きすぎている。高齢社会等の社会の変化は、人が安全・安心・豊かに生きるための新しい需要、高い購買力を要請しているではないかと指摘する。
人口と経済――。「先進国の経済成長は、基本的に労働人口ではなく、イノベーションによって生み出されるものだ」「労働生産性の上昇は、労働者の頑張り、やる気、体力ではなく、広い意味での『技術進歩』つまり『イノベーション』、資本蓄積、産業構造の変化によってもたらされる」「需要の飽和に対しては、新しいモノやサービスの誕生、つまり『プロダクト・イノベーション』だ。需要の飽和において、通常は"水と油"と考えられるケインズとシュンペーターの経済学は急接近する。需要の不足によって生まれる不況を、ケインズは政府の公共投資と低金利で克服せよと説いた。シュンペーターは需要の飽和による低成長を乗り切る鍵はイノベーション以外にないと主張した」「経済成長至上主義を説くのではない。・・・・・・経済成長の果実を忘れて"反成長"を安易に説く考え方は危険ですらある」・・・・・・。各国の経済に合った経済成長の方が、ゼロ成長よりはるかに自然だと、説得力をもって説く。
19日の敬老の日――。65歳以上の高齢者は3461万人、総人口に占める割合は27.3%で、昨年より0.6%増の過去最高。なかでも女性は30%を越え(30.1%)、1962万人となりました。
この日、地元では連合町会の「輪投げ大会」が行われ出席、開会の輪投げを行いました。大半が65歳以上で、90歳を越える人も何人も参加、大活躍に沸きました。ゲートボールはめっきり減り、輪投げ大会が盛んになっています。街の変化です。
また敬老会もめっきり減り、区や町会からお祝いを届けるように変化しています。団地などでは7割が70歳以上という所も多く、本当に高齢者が増えています。一方、活動的な高齢者も増え、「65歳以上=高齢者」の定義を見直すべきだとの声も浮上しています。現実に日本の高齢者の就業率が増加しており、日本の高齢者の就業率は21.7%、主要7か国で唯一、20%を越えています。「健康で長生き」――健康長寿社会への対応が大事です。







