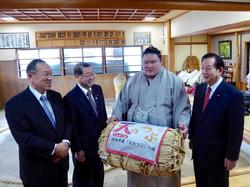「再生エネルギーの推進に水力発電が大きな力」「水力発電が日本のエネルギーを救う」――。14日、公明党総合エネルギー対策本部(顧問=斉藤鉄夫衆院議員、本部長=江田康幸衆院議員)が会議を開き、「水力発電が日本を救う」の著者、竹村公太郎氏(財団法人リバーフロント整備センター理事長)から話を聞き、議論を行いました。出席した公明党の衆参の議員からは、"目から鱗"の声が上がりました。
竹村氏の主張はきわめて明確。①河川法や多目的ダム法を改正してダムの運用を変えれば、多目的ダムの空き容量を活用して発電できる ②既存ダムを嵩上げすることで、新規ダム建設の3分の1以下のコストで、発電能力を倍近くにできる ③現在発電に使われていない砂防ダム等に発電させる ④逆調整値ダム建設でピーク電力需要への対応ができる ⑤小水力発電を増やすために水源地域を支援する――です。
「パリ協定」が11月4日に発効となり、国連気候変動枠組条約締約国すべての国で、2020年以降の国際的な地球温暖化対策の枠組みがスタートします。日本の目標は、2014年に策定した「第4次エネルギー基本計画」の中で、2030年に13年比でCO2などの地球温暖化ガスを26%削減、13年に11%だった再生エネルギーを22~24%まで増やすとしています。太陽光発電の導入は若干進んでいますが、目標達成へのハードルはまだまだ高い状況です。そのなかで水力発電は大きな可能性を秘めています。さらに研究を進めます。
 2025年まで――時間はそうない。団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、要介護や認知症の人の割合が高い75歳以上が約2200万人となる。高齢化率は30%を超える。2012年に約462万人といわれる認知症患者は2025年には約700万人(高齢者の5人に1人)と見込まれている。介護給付費は発足時(2000年度)の3.6兆円が15年には10.1兆円、25年には約20兆円に到達するという。急性期医療とその後の社会復帰のための効率的なこれまでの医療体制は、完治が難しい慢性疾患を複数抱えた高齢者への対応にシフトせざるを得ない。そこで、「地域包括ケアシステム」と「コンパクト+ネットワーク(国土のグランドデザイン2050)」を含めた「ケア・コンパクトシティ」という選択をする以外ない、という。それなしに、「2025年、高齢者が医療・介護難民」という惨状を脱することができない。
2025年まで――時間はそうない。団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、要介護や認知症の人の割合が高い75歳以上が約2200万人となる。高齢化率は30%を超える。2012年に約462万人といわれる認知症患者は2025年には約700万人(高齢者の5人に1人)と見込まれている。介護給付費は発足時(2000年度)の3.6兆円が15年には10.1兆円、25年には約20兆円に到達するという。急性期医療とその後の社会復帰のための効率的なこれまでの医療体制は、完治が難しい慢性疾患を複数抱えた高齢者への対応にシフトせざるを得ない。そこで、「地域包括ケアシステム」と「コンパクト+ネットワーク(国土のグランドデザイン2050)」を含めた「ケア・コンパクトシティ」という選択をする以外ない、という。それなしに、「2025年、高齢者が医療・介護難民」という惨状を脱することができない。
これからの日本は「都市部で急増する後期高齢者と介護難民」「社会保障費の膨張に伴う財政危機」「人口減少に伴う地方消滅」という3つの問題に直面する。人口減少、少子高齢社会が加速する今、「空間選択や時間軸を重視した政策に切り替え、スマートシュリンクの時代に向けて舵を切れ」「"まちづくり"や"エリアマネジメント"の視点を盛り込みつつ、医療・介護など必要なサービスをコンパクトシティという地域の空間の中で効率的・効果的に提供すること」「"まちづくり"はヒューマンスケールで」「地域の共同体マインドを共有することが大事で、規範的統合が重要だ」・・・・・・。
全国の市町村での先駆的取り組みを紹介しつつ、数々の具体的提言を行っている。私も同じ問題意識をもって「コンパクトシティ+ネットワーク」「対流促進型国土の形成」を進めている。「ケア・コンパクトシティ」――同感。実行の時だ。
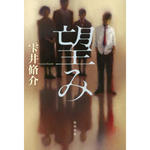 最近もあった少年たちがリンチで殺害する事件――。その事件に突然、わが子が巻き込まれた時、父親は、母親は、娘は、関係のあった人々は、狼狽のなかで何を思い、考えたか。辛い。
最近もあった少年たちがリンチで殺害する事件――。その事件に突然、わが子が巻き込まれた時、父親は、母親は、娘は、関係のあった人々は、狼狽のなかで何を思い、考えたか。辛い。
サッカー少年であった石川規士が高校初の夏休み直後、2日も帰って来ず、父・一登と母・貴代美は胸騒ぎを覚える。そして息子の友人が遺体となって発見され、犯人と思われる少年2人の逃亡が目撃される。しかし、行方不明者は3人。息子は加害者か、被害者か。犯人であっても生きていてほしいと思う母・貴代美。加害者のはずがない、被害者であれと思う父・一登。無事であってほしい、いや無実であってほしい・・・・・・。
「望み」は絶望のなかのせめてもの望みでしかない。望みなき望みだ。父と母、男性と女性、親と子、現在と今をはらむ未来。日常と死。死の現実のなかに「怨」が消える。交錯し、相反する思いが、生死の現実のなかで融け、定置する。