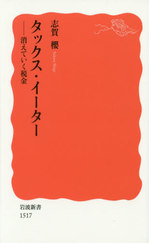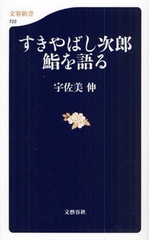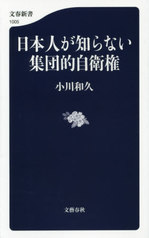「消えていく税金」と副題にある。日本の財政状況が危機的状況にあるという問題意識、日本経済が財政金融政策の発動による景気浮揚策に慢性的に依存してきたという問題意識がまず前提としてある。そして「高度成長の呪縛」「円高恐怖症」「政官業の鉄のトライアングル」などをまず指摘している。
そして「タックス・イーターが群がるもの」として「予算(一般会計、特別会計)」「財政投融資」「租税特別措置」「国債」のそれぞれに、何が、どのように群がるかを示す。族議員、官僚、鉄のトライアングルにもふれる。「官僚」のなかでは、財投対象機関、「公企業」として特殊法人、認可法人、独立行政法人、特別民間法人などの概要を示している。
タックス・イーターとの戦いとして「終わりなき行政改革」「国境を越えて」と国内外の問題を指摘している。肥大のベクトルが働くがゆえに、善悪の二元論を排しつつ、常に厳しく監視する動体視力を養わねばならない。
正直、こんな丹念に、精魂込めた、心の行き届いた達人・凄腕の職人技の鮨を食べてみたい。そう思った。
小野二郎さん。生まれは大正14年(1925年)、静岡県の佐久間村。7歳になって間もなくの正月に、親元を離れて二俣町の割烹旅館「福田屋」へ奉公に出る。休みは元日と盆の2日のみ。隣町まで三輪の自転車をこいで出張料理までした。16歳で横浜の軍需工場に徴用され、20歳で豊橋の工兵隊。26歳で東京・京橋の鮨店「与志乃」へ弟子入り・・・・・・。40歳で「すきやばし次郎」を開業する。
生半可ではない苦労をしている。理不尽なことも山ほどある。しかし、それを生命力と根性で平然(のように見える)と、真っすぐにやりとげている。辛いといわない。常に全力、手を抜かない。そして今も全力、常に現役。「なんでも十年はしがみつかなきゃ、物事の本質なんてつかめっこない」「ワタシは7歳から働き詰めに働いて、それをちっとも辛いとも苦しいとも悲しいとも思わず普通にやって来た」――。
宇佐美さんは「現代とは職人不在の時代だ。職人とは、いついかなる場合でも同じものを同じレベルでこしらえる、あるいは表現する腕の確かさだ」「そのレベルをどこまで高みに引き上げられるかが職人の力量であり、腕の冴えだ。二郎さんは、まさに凄腕の職人である」という。
2月5日、参議院予算委員会で、福島の原発事故避難者に対する高速道路無料措置を来年3月31日まで1年間延長する方針を明らかにしました。
福島の高速道路無料化は、今なお避難を余儀なくされている方々が家族との再会や生活再建に向けて高速道路を利用する際に、大変役に立っています。
私はこれまでも福島の復興に向けて、相馬市などでの災害公営住宅の整備、JR常磐線富岡駅の被災状況、国道6号線の復旧や相馬福島道路の整備などを視察し、常磐自動車道の前倒し開通にも取り組んできました。
3月1日には、常磐自動車道が当初の予定を大幅に前倒しして全線開通します。また相馬市では、計画中の災害公営住宅410戸すべてがこの3月末までに完成する見込みとなるなど、災害公営住宅の整備も目に見えるかたちで進んできました。しかし、原発事故の影響がある地域では、JR常磐線の復旧や災害公営住宅の整備など、復興はこれからです。
震災からまもなく4年目を迎えますが、福島の復興はこれからが山場。少しでも早く復興を実感していただけるよう、さらに全力で頑張ります。
日本を取り巻く安全保障環境が変わるなかで、隙間のない安保体制をどう整備するか――これがテーマとなり、2014年7月1日の閣議決定が行われた。小川和久さんは「閣議決定は安定した仕上がりとなった。公明党が『平和』という立脚的を外さず、憲法との規範性、政府解釈との論理的整合性などを厳格に問い続けてきた結果だ」とインタビューでも発言している。
本書は、そもそも集団的自衛権とはいかなるものか。世界ではどう考えているか。実態はどうか。日本の政治家、官僚、マスコミ世論にいかに誤解が多いか、などに触れている。そして、小川さんは集団的自衛権に限らず、日本の議論は「賛成か反対か?」から始められる傾向があるが、集団的自衛権を考える上で押えるべきポイントは(1)「そもそも国家の平和と安全をどう確保するのか」を考えること(2)日本の防衛力の現状を直視すること――の2点だ、と指摘する。安全保障のスペシャリストが、解説してくれる。