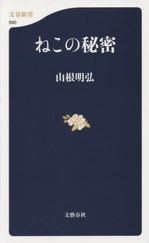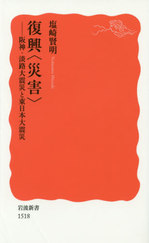「その顔を、いつも、太陽のほうに向けていなさい。あなたは、影を見る必要などない人だから」(ヘレン・ケラー)――。
ヘレン・ケラーとアン・サリバンの物語を、明治時代の青森に移し変え、弱視をかかえた去場安(さりばあん)と三重苦の介良(けら)れんの物語として描く。それにれんの初めての幼な友だちとなる盲目の津軽三味線・人間国宝となる狼野キワが加わる。何とも言えない感動が広がり、涙した。
原初的な感覚――生きるということ、人間に備わった無限の可能性、生の肯定から噴出する愛の力、最初に教えた「祈り」、差し込む光、生きる希望・・・・・・。見えざる世界を知り、感ずるところに人生が始まり、そこを開示悟入するには師弟がいる。思考が垂直に心に迫ってくる。

日本の防災・減災、復興を世界に発信――。3月15日、仙台市で開催されている第3回国連防災世界会議に出席し、閣僚級会議で発言をしました。
この会議は、今後15~20年間の国際的な防災戦略を議論する国連主催の会議。約190か国から首脳、閣僚級が参加し、日本で開催する国際会議としては過去最大級のものです。特に今回は、東日本大震災の被災地、仙台で開催されることもあり、復興が着実に進んでいる姿を世界各国から集まった参加者に示すことでも極めて重要です。
私が参加した閣僚級会議のテーマは「災害からのより良い復興(Build Back Better)。40か国、5つの国際機関の閣僚や代表者が3時間にわたり活発な議論を行いました。
私は、我が国がこれまで経験してきた阪神淡路大震災、東日本大震災、水害等の教訓と、防災・減災のさまざまな取組みについて発言。「最悪の事態も想定して、ハード・ソフト一体となった防災・減災対策を行うこと」「過去の教訓を活かし、より安全な地域づくりを進めるための予防的投資を行うこと」の重要性を訴えました。
また、マレーシアのムヒディン・ヤシン副首相、トルコのクルトゥルムシュ副首相、中国の李立国・民生部長と個別に会談。会議前には、アイスランド、ケニア、フィリピン、ニュージーランド、カタールの閣僚、代表者と次々と言葉を交わしました。
世界各国で洪水や渇水などが頻発しており、災害から命を守ることは世界共通のテーマです。我が国の防災・減災対策と東北の復興の現状を世界に向けてアピールする有意義な機会となりました。
14日、北陸新幹線金沢駅出発式に出席しました。朝5時、地元の知事や市町村長はじめ多数の関係者が集った金沢駅は喜びに包まれ、式典・テープカットが行われました。スタートを見ようと各ホームに地元の方々があふれるほど集まりました。午前6時、次のNHK朝のドラマの主役・土屋太鳳さんの発声で、一番列車が、まばゆいフラッシュと大きな歓声のなか、出発しました。実に40年以上にわたる悲願達成の瞬間です。
最速の「かがやき」は、金沢・東京間を、従来の3時間47分から2時間28分で、金沢・大宮間を、従来の3時間27分から2時間4分で結びます。かなりの短縮です。
これにより、北陸と首都圏は大きく近づき、沿線地域での企業活動や企業立地の活発化、生活圏の拡大など、地域の振興や経済活性化に大きな効果がもたらされます。また、新たな観光資源の発掘や観光ルートの形成などに取り組むことで、文化と伝統、雄大な自然と海の幸、温泉など多くの観光資源をもつ北陸の魅力がさらに高まり、国内外から多くの観光客を呼び込むことにつながります。
今年1月には、地元から非常に強い要望のある福井県の敦賀までの延伸開業についても、財源などを工夫することにより、3年前倒して2022年度とすることを決定しました。
北陸新幹線の開業は北陸・信越を発展させる大きなチャンスです。
「猫の手も借りたい」「猫なで声」「猫のひたい」「ねこ背」「猫に小判」「ねこ舌」「猫の目のように変わる」・・・・・・。一方で猫は「媚びない」「群れない」「あせらない」「気まぐれ」「マイペース」「気高く」「神秘的」・・・・・・。そこがまたねこの魅力であることは、わが家でも「ねこ」がいるからよくわかる。
山根さんは、ねこの誕生から恋、出産、子育て、老い、そして祖先のリビアヤマネコ、家畜化、農耕と定住とネズミ、ノラネコとイエネコ、オスとメスと恋愛などの「ねこの生き方」について、動物学、生態学、遺伝学などをも含めて解き明かしてくれる。その観察は大変だったことがうかがえるが、納得した。
しかし「毎年10万匹が殺処分されている」日本だ。2012年は123,420匹にのぼる。ねこを飼うには覚悟がいる。餌やりが悲劇を招く。「ひと」と「ねこ」が仲良く暮らしていける社会をどうつくるか。山根さんは「ヒントは昔の日本にある」という。そして「"ねこ"という生き物が、昔からこれほどまでに日本人の生活や文化、そして芸術にまで深く関わってきたことを、みなさんに知って頂きたかった」と語る。
「阪神・淡路大震災と東日本大震災」と副題がついている。阪神・淡路大震災から20年――塩崎さんは、「神戸大学で住宅問題やまちづくりを専門としていた立場から、住宅の被害調査や、復興まちづくり、仮設住宅や復興住宅などの調査研究に取り組み、いつのまにか20年が経つ。そして、いまなお震災を引きずり、復興が成し遂げられない人々が存在する・・・・・・」という。「住宅復興が極めて重要で、かつ容易ならざる難問である」「災害そのもので助かった命が、その後の復旧・復興過程で失われるという不条理な『復興災害』を避けることは、人間の努力次第で可能なはずである」と指摘する。
視点は、被災者の生活に貫かれている。復旧・復興が「まち」の復興にとどまってはならない。常に被災者の生活再建の一点から目を放すな。避難所、仮設住宅、復興公営住宅、借上げ公営住宅、復興まちづくりのなかで、コミュニティの崩壊、忘れられてきた震災障害者、孤独死、中小企業や商店主の苦しみ・・・・・・。阪神・淡路大震災の教訓は生かされたのか。それとは全く違う面を多くもつ東日本大震災で、進んだもの、全く対応できていないもの。そうした課題を整理している。