昨日20日、「スポーツ庁」を設置する法案を閣議で決定。いよいよ念願のスポーツ庁が動き出すことになりました。これは、文部科学省のスポーツ・青年局、国土交通省の運動施設部門、厚生労働省の健康増進事業を統合して、スポーツ行政を統合。スポーツ立国に向けてのエンジンとなるもので、五輪に向けて選手強化、国際貢献にも力を入れるものです。
「スポーツ庁設置を」――私が長い間、主張し続け、働きかけたことです。世界ではスポーツ省やスポーツ庁がほとんどあるなかで、これほどスポーツが盛んで、勇気と希望を与えているのに日本にはそれがない。トップアスリートを育てる「ナショナルトレーニングセンター」(写真)を推進し、実現させてきたスポーツ人間の私としては、「いよいよ」「やっと」の思いです。
多くの人がスポーツを楽しみ、スポーツ人口が広がる――すそ野の広がりが山の高さを決める。まさにトップアスリートもスポーツが広がり盛んになってこそ育つものです。
後藤さんの平成政治史の3巻目。第一次安倍内閣に始まり、民主党が政権を奪取、そして野田内閣での解散・総選挙までを描く。「幻滅の政権交代」と副題が付いている。まさに渦中にいた私だが、思い起こしつつ(起こされつつ)読んだが、なぜか当時よりも息が詰まった。
この6人の内閣はいずれも苦しんだ。関わった1つ1つの事象に、私自身「ここは書いてない」ことなどがあるのは当然だが、本書はその骨格部分を真っすぐに書いている。政局話によくありがちな脚色や思い込みがないのは、本人に直接会って話を聞いているからだ。まさに「平成政治史」となっている。貴重だ。
後藤さんがいうように、平成の日本政治は激動・混乱・混迷の連続だった。また多党化も特徴だ。さらに国際情勢の激変にもさらされ、大きく影響を受けた。そして改めて「政治は人が成すもの」だと思う。「平成時代に常態化した『激動の政治』の終わりはまだ見えない」というが、世界の激動が続く以上、日本政治の激動も続くことになる。政治家にもジャーナリストにも「人間学」と「動体視力」がますます大事になると思う。
2月16日、昨年10~12月期のGDP速報値が発表されました。前期比0.6%増、年率換算で2.2%増と、3四半期ぶりにプラスに転じました。また17日の閣議では、住宅取得を支援する給付措置(「すまい給付金」)の対象期間を平成31年6月まで1年半延長することを決定。安倍総理とも景気・経済の回復と住宅着工について話をしました。
GDPのプラス成長は、昨年4月の消費税増税以降初めて。個人消費は小幅ながら持ち直して輸出も伸びており、デフレ脱却に向けて弾みがつくことが期待されます。そのなかで唯一マイナスだったのが民間住宅投資──。消費増税に伴う反動減の影響もあり、3四半期連続でマイナスとなっています。
住宅は景気・経済に大きな役割を果たします。かつてはGDPの5~6%を占めていましたが、3%台となった今でも家を建てたりリフォームすれば、資材の生産や家具の購入など大きな波及効果があります。このため住宅着工を活性化させるため、経済対策や補正予算で様々な手を打っているところです。
税制面では、若年層の住宅取得を促進するため贈与税非課税限度額を過去最大の1500万円に拡充。予算面では、住宅金融支援機構の長期固定住宅ローンであるフラット35Sの金利引下げ拡大や、省エネ住宅に対する住宅エコポイントの創設などです。住宅エコポイントは3月10日から受付を開始することを16日に発表しました。これらは中古住宅やリフォームにも使えます。
17日は朝から大臣室で住宅着工の現状や対策について打ち合わせをしました。住宅着工は消費税増税以降減少が続いていましたが、増加へ転じる動きも出てきています。住宅投資を喚起し、景気・経済の再生につなげていくために、これからもしっかり取り組んでいきます。
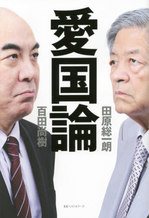
田原さんと百田さん――どんなバトルかと思ったが、結構かみ合っている。いつの間にか、田原さん百田さんに、読者たる私自身が加わって3者対談ともなっていた。二人とも言い過ぎというほど率直に語っている。
田原さんは「百田尚樹さんは対談で、期待に違わず、私の考え方に鋭く斬り込んでくれた。大東亜戦争、戦後日本を支配した自虐史観、韓国や中国とのつき合い方、朝日新聞の問題、愛国心とは何かについてなど、互いの一致点と相違点がくっきり浮き彫りとなった」という。百田さんは「私は『右翼』でも『保守』でもない。もちろん『左翼』でも『リベラル』でもない。私は『愛国者』である。右も左もない。私が愛するのは、祖国『日本』であり、この国を愛する人たちである。反対に私が憎むのは『反日』と『売国』である」といっている。
中心論点は「いまのややこしい問題はすべてが自虐思想に端を発していると思う(百田)」ということだ。









