 経済、政治、教育、社会保障、エネルギーについて、各分野の若き研究者がそれぞれ語る。従来の大上段の分析、理論、解決策の提示とは全く違う。若い、新しい、自らつかんだ現場のデータを駆使、具体的、実行している側に立ってのもので、刺激的だ。
経済、政治、教育、社会保障、エネルギーについて、各分野の若き研究者がそれぞれ語る。従来の大上段の分析、理論、解決策の提示とは全く違う。若い、新しい、自らつかんだ現場のデータを駆使、具体的、実行している側に立ってのもので、刺激的だ。
一般の風説に惑わされない。的はずれの一点突破ではない。理屈をいっても動きをつくれなければ意味はない。データを積み上げなければ行政は動かない。そうしたクールな世界が開示される。
エネルギーでも小規模分散型の自然エネルギーを事業として成立させるにはどうするか。地域から現場から具体例を示しつつ打開策をたんたんと語る。「ひきこもり」に対しても原因を示すだけでなく、実際に行なっている大学のひきこもり支援政策と成果を示す。経済では従来からの経済学ではなく、現実の制度を修正・設計していく「マーケットデザイン」「ゲーム理論」を紹介する。大野更紗さんは本人の生を尊重するQOLの向上について述べる。
新しい理念、理論と行動を提示しており、そこには情緒やイデオロギーによる思考停止はない。
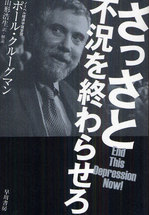 今年2月、ポール・クルーグマンが書いたもの。米の経済政策の誤り、オバマ大統領やバーナンキの中途半端さ、欧州危機の本質、種々の経済理論の誤りや歪みを指摘し、「ミンスキーの瞬間」「流動性の罠」等を実例に即して語っている。
今年2月、ポール・クルーグマンが書いたもの。米の経済政策の誤り、オバマ大統領やバーナンキの中途半端さ、欧州危機の本質、種々の経済理論の誤りや歪みを指摘し、「ミンスキーの瞬間」「流動性の罠」等を実例に即して語っている。
「緊縮をすべきなのは好況時であって不況時ではない」
「今は政府支出を増やすべきときで、減らすべきではない。民間セクターが経済を担って前進できるようになるまで続けるべきだ」――と。
「今は流動性の罠にはまっていて、短期金利がゼロ近いのに経済が停滞したままだから、インフレ突発にならない。FRBの購入が通常は好況やインフレを引き起こすというプロセスがショートしてしまっている」
「好況にならなければインフレは起きない。お金の印刷がインフレにつながるのは経済の過熱につながる好景気を通じてなのだ」
「デフォルトの恐れのあるギリシャ、イタリアと米国、日本は違う」
「景気刺激策があまりに小さく、支出削減を打ち出したオバマの政策は誤りだ」
「補償のみの支出増ではなく、景気刺激策を」
「2009年の米国は金融救済はしたがそれも甘く(厳しい条件をつけていない)、肝心の実体経済に対する救済策がなかった」
「規制のない金融システムが必ず起こす危険信号にもかかわらず、政治システムが規制緩和と無規制にこだわり続けた」
「格差と危機」――。
日本についても、日銀についてもふれている。10年ほど前にバーナンキが日本について指摘したことは正しい。それを今、米国は、バーナンキはなぜやろうとしないのか。なぜやれないのか。
増税や支出削減は今やることではないのだ。経済を破壊する通説にまどわされるな――訳者の山形浩生さんも、クルーグマンの主張、嘆息、諧謔をよく解説してくれている。
 こんにちは、太田あきひろです。
こんにちは、太田あきひろです。
猛暑が続きますが、「どうなっているんだ。政治は。国をしっかりさせてよ」――現在の対話でまず出る言葉です。
今日23日、都内で東京都本部の政経懇話会が行われましたが、そこで私が発言したこと。それは「太田さん、何とかしてください。どういう国にするか方向を示してくれ」と言われることがありますが、今やるべきことは明確。それは外交の再建が急務であるとともに、「景気・経済がリーマン・ショック後よりも厳しく、企業の基礎体力も含めて根本的に崩れかけてきている」「高齢社会が進むなかで社会保障は大丈夫か」「首都直下地震がきて大丈夫なのか」――という3つの崩れ、3つの不安を中長期的(一過性でなく)に、建て直すことです。現場を踏まえないビジョンを机上でつくっている場面ではない。切迫した、日本の底が抜けたかのような深刻な問題を中長期的に建て直す、再建へのダッシュが大事なことだと思います。
「景気・経済の再建」は私自身ずっと強調していることです。この3年間の民主党の経済無策・デフレ脱却への意思の欠如は「普天間」同様、本当に取り返しのつかないことだと思います。私は(1)金融政策(2)財政政策(3)産業支援政策――を総動員せよ。財政政策は「防災・減災ニューディール」「再生エネルギー」「介護をはじめとする社会保障」の3つを柱にせよ。その活性化によって雇用をつくれ――と主張しています。日本再建に向けて、全力で頑張ります。

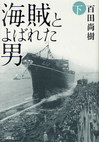 「ならん!ひとりの馘首もならん」――何もかも失った日本と日本人の昭和20年9月、国岡鐡造(出光佐三)は言い切る。「わが社には何よりも素晴らしい財産が残っている。一千名にものぼる店員たちだ。......社是である『人間尊重』の精神が今こそ発揮されるときではないか」「もしつぶれるようなことがあれば......ぼくは店員たちとともに乞食をする」――。「融資が受けられないのは、なぜなのかわかるか。......君の真心が足りないからだ。至誠天に通じると言うではないか」――。
「ならん!ひとりの馘首もならん」――何もかも失った日本と日本人の昭和20年9月、国岡鐡造(出光佐三)は言い切る。「わが社には何よりも素晴らしい財産が残っている。一千名にものぼる店員たちだ。......社是である『人間尊重』の精神が今こそ発揮されるときではないか」「もしつぶれるようなことがあれば......ぼくは店員たちとともに乞食をする」――。「融資が受けられないのは、なぜなのかわかるか。......君の真心が足りないからだ。至誠天に通じると言うではないか」――。
どこもやらない、誰もやれない海軍燃料タンクの底に残った残油を浚う作業をやり抜く国岡商店の決死のサムライたち。そして石油の時代を予測し、時の覇権たるメジャーとも米英とも大企業や官僚とも戦い屈することのなかった国岡鐵三。
「GHQ」「公職追放」「石統との戦い」「士魂商才(武士の心を持って商いせよ)」「スタンダードとの戦い」「セブン・シスターズとの戦い」「極秘のイラン石油と日章丸」......。
「日本人の力。こういう日本人がいるかぎり、日本は必ず復興する」「楽しい50年ではなかった。苦労に苦労を重ねた50年であった。死ななければ、この苦労から逃れることはできないのではないかと思われるほどの苦労の50年だった」「全財産を投げうち、挫けそうになった鐵三を、頑張れ、諦めるな、共に乞食をしてもええと支えてくれた日田重太郎」「日本人の誇りと自信を失わなければ、何も怖れることはない」――「人間尊重、戦い続けた国岡鐵三の70年の道は正しい日本人の大道であった」と、百田さんは結んでいる。石油を武器に変えて世界と闘ったすさまじい男の歴史経済小説。



