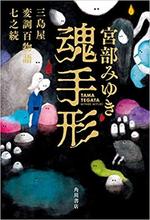 三島屋変調百物語七之続。江戸・神田の筋違御門先で袋物屋を商う三島屋で行われている風変わりな百物語。「語って語り捨て、聞いて聞き捨て」が原則で、心のわだかまりや澱が吐き出される。「百物語なんかしていると、この世の業を集めますよ」――。従妹のおちかから引き継いだ「小旦那」の富次郎は、語られた話を墨絵に描いて封じ込める。江戸の町人文化、人の情や業が描かれる。さすがと思わせる筆致。
三島屋変調百物語七之続。江戸・神田の筋違御門先で袋物屋を商う三島屋で行われている風変わりな百物語。「語って語り捨て、聞いて聞き捨て」が原則で、心のわだかまりや澱が吐き出される。「百物語なんかしていると、この世の業を集めますよ」――。従妹のおちかから引き継いだ「小旦那」の富次郎は、語られた話を墨絵に描いて封じ込める。江戸の町人文化、人の情や業が描かれる。さすがと思わせる筆致。
「火焔太鼓」――。美丈夫の勤番武士・中村新之助(幼名・小新左)が、国許では語れぬ大加持藩に伝わる火災を制する神器「火焔太鼓」「太鼓火消し」の由来と驚くべき真実を吐露する。「火事という火事が小火で消し止められてきたのは、お太鼓様が火気を喰らって封じて下さるからだ」・・・・・・。
「一途の念」――。馴染みの串団子の屋台の娘・おみよから母・お夏の話を聞く。「おっかさんが死んだんです」「おっかさん、気がふれちまって、自分の目ン玉を指で、ほ、ほじくりだそうとして」・・・・・・。お夏は15歳の時、名を「夏栄」と改め、格式の高い料理屋「松富士」の仲居となり、料理人の伊佐治とも結婚する。美男美女だった。しかし松富士の名だたる包丁人・喜久造が闇討ちにあって命を落とし、女将も倒れ「松富士」は沈んでいく。格式どころか「女」まで売る店へと転落していく。肺病で伏せていた伊佐治の看病をしつつ夏栄は「客」の相手までさせられ、次々と子供が生まれる。それが皆、男3人とも伊佐治にそっくりだった。4人目の子がおみよ。そして夏栄が死んで・・・・・・。驚くべきお夏の「一途の念」が・・・・・・。
「魂手形」――。深川の蛤町の北にあった木賃宿「かめ屋」を営んで父母と弟2人の5人で住んでいた吉富15歳のお盆の頃。「正真正銘のお化けがお客として泊まったっていうのが、この話の始まりでござんす」「きっちゃん、昔、お盆の最中にかめ屋に泊まった、なくなった人の魂が見えるって鳥目を病んでいたお客さんのこと、覚えているかい? うん覚えているよ。母ちゃんも覚えてたんだね」「あれは『魂手形』(たまてがた)と呼ばれるもので、お上から魂の里の水夫だけに下される特別な通行手形なんだ」「魂さんの行きたがるところへ案内するのが水夫の務めだ」「あたしら里に寄りつく魂さんはみんな、魂見に道理を説いてもらって、形をつくって落ち着くんだ。あたしらが迷魂や哀魂で済むか、怒魂や怨魂になってしまうか、それも魂見の説教と、あとは水夫の面倒見次第さ」・・・・・・。
不可視の「業の世界」「あわいの世界」を、人はどの時代においてもせめて一人に「語り」「聞いてほしい」と思うものだ。死んでも・・・・・・。
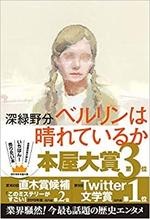 1945年7月、2か月前にヒトラー総統は自殺し、ナチス・ドイツが降伏、戦争に敗れ荒廃したベルリン。米英仏ソの4か国の統治下におかれたが、ソ連と米英仏は対立状況にあった。街は完全に破壊され、生活は極度の困窮。ナチスに弾圧・虐殺されたユダヤ人や共産主義者は、絶望から脱する窓は開いたもののその傷は回復できないほど深く、心に絶望の刃を突き刺したままだった。破壊され絶望のベルリン――。そんななかでドイツ人で17歳の少女アウグステ・ニッケルの恩人であったクリストフ・ローレンツが、ソ連領域で米国製の歯磨き粉に含まれた青酸カリによって不審死を遂げる。ソ連のNKVD(内務人民委員部)大尉ドブリギンはアウグステに不審の眼を向けつつ、クリストフの妻フレデリカの甥エーリヒ・フォルストに訃報を伝えるよう仕向け、元俳優で泥棒のファイビッシュ・カフカを道連れ役とする。事件の真相は・・・・・・。街も人心も破壊され尽くしたベルリンを舞台に、二人は思惑を胸に秘し不安な旅を始める。
1945年7月、2か月前にヒトラー総統は自殺し、ナチス・ドイツが降伏、戦争に敗れ荒廃したベルリン。米英仏ソの4か国の統治下におかれたが、ソ連と米英仏は対立状況にあった。街は完全に破壊され、生活は極度の困窮。ナチスに弾圧・虐殺されたユダヤ人や共産主義者は、絶望から脱する窓は開いたもののその傷は回復できないほど深く、心に絶望の刃を突き刺したままだった。破壊され絶望のベルリン――。そんななかでドイツ人で17歳の少女アウグステ・ニッケルの恩人であったクリストフ・ローレンツが、ソ連領域で米国製の歯磨き粉に含まれた青酸カリによって不審死を遂げる。ソ連のNKVD(内務人民委員部)大尉ドブリギンはアウグステに不審の眼を向けつつ、クリストフの妻フレデリカの甥エーリヒ・フォルストに訃報を伝えるよう仕向け、元俳優で泥棒のファイビッシュ・カフカを道連れ役とする。事件の真相は・・・・・・。街も人心も破壊され尽くしたベルリンを舞台に、二人は思惑を胸に秘し不安な旅を始める。
敗戦直後のベルリン。ありとあらゆる狂気が全ての人の人生を奪い去っていた。戦争と敗戦の荒廃した街と人心。ユダヤ人や障害をもつ者への想像を絶する弾圧・虐殺。裏切り・告発で生き残ろうとする者たちとスパイ・陰謀・・・・・・。極限、極致の姿が描写されて息苦しい。戦争と狂気が何をもたらしたか。そしてこの毒殺の思わぬ結末が明かされる。空を見る余裕もない人々・・・・・・。「ベルリンは晴れているか」の表題が読み終えた時に、「確かに・・・・・・」と思えてくる。スケールの大きい傑作。
 困窮世帯へ最大30万円の給付金――。コロナ禍で収入が減少し、生活が困窮している世帯に対し、政府は無利子の特例貸付として、「緊急小口資金(20万円)」「総合支援資金(180万円)」を上限200万円まで実施しています。しかし、緊急事態宣言が延長され、困窮が厳しく続いていることを注視、公明党が「6月末までの申請期限を延長」「貸し付けが上限に達している人に新たな支援金を」と提唱してきました。28日、これが実現、政府決定となりました。申請期限は延長、新たな支援金は、単身世帯で月額6万円、2人世帯で8万円、3人以上世帯で10万円で、7月以降の3か月間給付されます。
困窮世帯へ最大30万円の給付金――。コロナ禍で収入が減少し、生活が困窮している世帯に対し、政府は無利子の特例貸付として、「緊急小口資金(20万円)」「総合支援資金(180万円)」を上限200万円まで実施しています。しかし、緊急事態宣言が延長され、困窮が厳しく続いていることを注視、公明党が「6月末までの申請期限を延長」「貸し付けが上限に達している人に新たな支援金を」と提唱してきました。28日、これが実現、政府決定となりました。申請期限は延長、新たな支援金は、単身世帯で月額6万円、2人世帯で8万円、3人以上世帯で10万円で、7月以降の3か月間給付されます。
また、企業・事業主支援の最重要の柱となっている雇用調整助成金も、緊急事態宣言下となることもあり、7月以降も延長されることが決定されました。各方面から切実な要望が寄せられており、これを実現したものです。
生活支援、企業・事業主支援に、しっかり頑張っていきます。
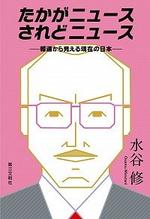 「夜回り先生」と呼ばれ、子どもたちの非行防止や薬物汚染防止、さらには教育のあり方等々、現場で幅広く闘い続けている水谷修氏が、この2年、話題となった事件・出来事の報道について、その考察を語る。軸がきわめて明確。「ネットニュースのみで情報を得てしまうことになれば、情報量は増えるが、1つひとつの事件や社会現象についての深い分析と理解ができなくなる」「集めた情報を自分なりに分析し、自分の知識とする、これが重要」「報道には2つの『一線』がある。1つは『必ず越えなければいけない一線』――権力からの圧力や暴力などの危険があっても報道する。それには『正義』の心」「もう1つは『決して越えてはいけない一線』――報道してはいけないことがある。これを守るのはメディアや記者の『愛』の心」「そして情報を受け取るこちら側が、知るべき情報と知ってはいけない情報を『正義』と『愛』の心で取捨選択する賢明さを持つ」ということの必要性を語る。この2年、多くの人が知るところとなった事件・出来事について「観る」べき軸を明示する。
「夜回り先生」と呼ばれ、子どもたちの非行防止や薬物汚染防止、さらには教育のあり方等々、現場で幅広く闘い続けている水谷修氏が、この2年、話題となった事件・出来事の報道について、その考察を語る。軸がきわめて明確。「ネットニュースのみで情報を得てしまうことになれば、情報量は増えるが、1つひとつの事件や社会現象についての深い分析と理解ができなくなる」「集めた情報を自分なりに分析し、自分の知識とする、これが重要」「報道には2つの『一線』がある。1つは『必ず越えなければいけない一線』――権力からの圧力や暴力などの危険があっても報道する。それには『正義』の心」「もう1つは『決して越えてはいけない一線』――報道してはいけないことがある。これを守るのはメディアや記者の『愛』の心」「そして情報を受け取るこちら側が、知るべき情報と知ってはいけない情報を『正義』と『愛』の心で取捨選択する賢明さを持つ」ということの必要性を語る。この2年、多くの人が知るところとなった事件・出来事について「観る」べき軸を明示する。
「車は走る凶器――あおり運転防止」「同僚教員へのいじめ問題――いじめではない。立派な犯罪。教育委員会は調査・公表すべき」「中2女子生徒の担任による拉致・監禁事件――守るべきは被害者・生徒であり、学校の体裁や教員ではない」「高2生徒が教員による個別指導後に自殺した哀しい事件――生徒は教室で一人残され、どれだけ苦しんだか」「田代、槇原の覚せい剤所持逮捕――ドラッグは2つの言葉で定義できる。①やったらやめられない依存性物質(1回目の使用から強烈な快感)②やったら捕まる違法物質」「児童相談所が深夜に女児を追い返した事件――児相は子どもたちの命の最後の砦だ」「女性殺害事件――被害者の報道に人権への配慮を」「コロナと学校のリモートワーク――学校は仮想空間で十分ではない。社会性や人格形成に文化祭・体育祭などは大切な行事」「いじめ防止対策推進法の改正――暴力・金品要求・脅しは人権侵害。それはいじめではなく犯罪。無視や悪口・陰口はいじめ」「相模原障がい者施設殺傷事件――障害者は社会のお荷物ではない」「8050問題――政治の無策で生み出された問題」「教育者とは――少なくない家庭が教育の場として崩壊しつつある現在、学校の教員が担うしかない。子どもたちのことを心配する1人の人間として」・・・・・・。
大切な子どもたちを心配して守り、闘い続けている毅然たる声が伝わってくる。
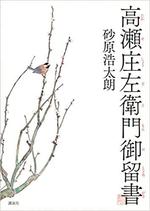 江戸から離れた地方の神山藩で、農民の管理や徴税などを扱う郡方(こおりがた)を務める髙瀬庄左衛門。五十を前にして妻・延を亡くし、息子の啓一郎も突然、崖から落ちて死んだ。息子の嫁・志穂とともに、寂寥を抱え込みながら生きてきた。二人をつなぐのは庄左衛門が手慰みに描く絵で、志穂も絵を始める。そんな時、「領内に不穏な動きあり」との投げ文。そして隣村の百姓と浪人が藩に強訴し、かつ庄左衛門が管理している藩の穀倉ともいうべき新木村を襲うという大事件が勃発する。その背景には藩に渦巻く政争があった。静謐にして厳と生きる庄左衛門の姿が、そしてひそやかに心を寄せる志穂の姿が、抑制的であるだけによりいっそう美しく迫る。
江戸から離れた地方の神山藩で、農民の管理や徴税などを扱う郡方(こおりがた)を務める髙瀬庄左衛門。五十を前にして妻・延を亡くし、息子の啓一郎も突然、崖から落ちて死んだ。息子の嫁・志穂とともに、寂寥を抱え込みながら生きてきた。二人をつなぐのは庄左衛門が手慰みに描く絵で、志穂も絵を始める。そんな時、「領内に不穏な動きあり」との投げ文。そして隣村の百姓と浪人が藩に強訴し、かつ庄左衛門が管理している藩の穀倉ともいうべき新木村を襲うという大事件が勃発する。その背景には藩に渦巻く政争があった。静謐にして厳と生きる庄左衛門の姿が、そしてひそやかに心を寄せる志穂の姿が、抑制的であるだけによりいっそう美しく迫る。
喧噪の現代とは異なり、江戸時代の地方の藩に流れるゆったりとした時間。朝が明け、人々が動き始め、仕事に精を出し、日が暮れる。静寂と静謐、風のかすかなそよぎ、光のきらめきと陰、木漏れ陽の美しさ、蝉しぐれ、人の気配、女の揺れる声、揺らめく灯、ゆるやかな弧を描く山の稜線。そして生老病死、日々に訪れるかすかな喜怒哀楽、心にとどめおいた過去のしがらみや記憶・・・・・・。丁寧に美しく自然と人心を描く。巧みな文体、描写は時代小説らしい余韻を漂わせ、老武士の誇りと襟度を際立たせる。世を"明らかに観る"諦観の定置の重さを感じさせる。

