10日、公益財団法人動物環境・福祉協会Evaの代表理事であり女優の杉本彩さんから動物虐待防止に関する要望を受けました。これには高倉良生(都議選予定候補=中野区)、長橋けい一(都議選予定候補=豊島区)両都会議員が同席しました。
今年3月、高円寺で車の中に犬2匹が3日以上閉じ込められる事件が発生。また武蔵村山市では、猫を多頭飼育していた高齢女性が死後数日経過した状態で発見され、そのまま猫が家の中に閉じ込められるという事件が起きています。こうした動物虐待や放置などの事件が相変わらず多く、私の事務所にも「助けてください」との緊急連絡が寄せられます。いずれも、動物愛護相談センターと地方自治体、警察の連携がうまくいかず、この連携強化が、重要です。この日のEvaからの要請は、「国(環境省)や地方自治体、警察の連携をスムーズに行い、動物をいち早く救出できるように」というものです。
動物虐待の厳罰化、動物飼育の環境整備などの動物愛護管理法の抜本改正が行われたのが、2年前の6月ーー。その法改正の1年前に、杉本代表理事から、「動物愛護管理法において、動物の虐待に対する刑罰が低すぎる」との要望を受けて、法改正に尽力。この法改正で動物を虐待死させたときの刑罰を懲役2年以下から懲役5年以下に大幅に引き上げ、杉本さんを始め動物愛護団体の悲願である、動物虐待の厳罰化が実現しました。その後もこの法律の内容整備と具体化に努め、Evaと連携をとってきました。「動物は"もの"ではなく、『家族』」との考えが、猫を長く飼っていた私の信念です。
今回の要望を受け、各行政間の連絡がスムーズに行くように、都議会と連携し、更なる改善に取り組んでいきます。
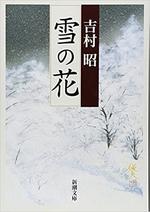 コロナ禍でワクチンが「切り札」として期待され、接種が始まっている。石井健・東大医科学研究所教授が「コロナ禍でのワクチン開発 その破壊的イノベーションの課題と展望」でワクチン開発の現状を詳説しているが、そのなかで推奨している本が、この「雪の花(吉村昭著)」だ。「福井藩の医師が、種痘の打ち方と育て方を学び、福井に持ち帰るという苦労話。その苦労に加えて、それを普及するのがいかに大変だったか・・・・・・この本からひしひしと伝ってくる」と述べている。
コロナ禍でワクチンが「切り札」として期待され、接種が始まっている。石井健・東大医科学研究所教授が「コロナ禍でのワクチン開発 その破壊的イノベーションの課題と展望」でワクチン開発の現状を詳説しているが、そのなかで推奨している本が、この「雪の花(吉村昭著)」だ。「福井藩の医師が、種痘の打ち方と育て方を学び、福井に持ち帰るという苦労話。その苦労に加えて、それを普及するのがいかに大変だったか・・・・・・この本からひしひしと伝ってくる」と述べている。
時は江戸末期の福井藩――。全国で天然痘が猛威を振るい、死亡した者を運ぶ大八車が日に何度も車輪の音を響かせて走り、そのたびに人々は恐怖に襲われて逃げまどった。人々が頼みにするのは神仏のみ、藩をあげて祈祷する有様であった。ジェンナーが牛の天然痘を人間に植える種痘法を創始したのが1796年。その噂を蘭方医から伝え聞いた福井藩の町医・笠原良策は一大発心をする。京都の蘭方医・日野鼎哉に師事し、「牛痘法による種痘」を試みようとする。その肝心である「牛痘の苗」(痘苗)を求めて私財を投げ打っての悪戦苦闘、そして京都から種痘をした子供を伴っての痘苗を絶やさずに運ぶ雪山越えの決死行、そして福井に入ってからも自らの子供に"恐ろしい"種痘を拒む親、漢方医や役人の妨害・・・・・・。想像を絶する苦難が続くこと数年。苦境を乗り越えられたのは、藩主の松平春嶽、側用人・中根雪江、春嶽の侍医・半井元冲らの開明的理解者、まさに諸天善神が現われたからであった。
この福井藩が入手した痘苗は、江戸や北陸の各藩に広まっていったのだ。
暑い日が続いた7日、8日、9日――。大田区、中野区、地元の北区・豊島区などで都議選の支援拡大を訴えました。
大田区では、かつまたさとし区議、玉川ひでとし区議の新人2人が立候補予定。7日、かつまたさとし区議(都議選予定候補)の時局講演会に出席。かつまた候補は、「新成人にピロリ菌検査を導入」「多摩川の洪水防止へ川底を2m掘削」などの実績を報告。またワクチン接種の加速へ戦っていることを力強く訴えました。
8日は中野区の時局講演会に出席。高倉良生都議は「妙正寺川と神田川の洪水防止へ環七地下調節池の設置・広域化」「動物愛護センターの新設と、地方自治体・警察の連携強化」などの実績を訴えました。
いずれも仕事ができる、豊富な実績をもつ人です。勝利めざして頑張ります。
 「日本経済復活への最強戦略」が副題。今DXが語られ、「決定的な変化」が起きている。「DXの要諦は『抽象化』にあり、世界は『レイヤー構造』へ進んでいる」「現在のデジタル化の発展の基礎にハードウェアの急速な進化があり、生み出されるデータ量も指数関数的に増大した。しかし、現代の産業の大きな変化、IXをハードウェアの発達、データを含めた『量』の増加だけで説明するのは正しくない。それはたかだか話の半分に過ぎない。同時に、世界の実課題とコンピュータの物理的基盤をつなぐエコシステムが進化し、精巧になったこと、つまりは『質』の変化が決定的に重要だ」「それを実現しているのは、レイヤー構造をしたソフトウェア群である」「関係する技術は、半導体、ソフトウェア、インターネット、ディープラーニング、クラウド、5G等々・・・・・・。それらが計算能力、処理加工が可能なデータ量を向上・拡大させて、ゼロイチの物理的な処理と人間の実課題や経験とが連結するまで、サイバー空間の水位を押し上げた。しかし、本当のスタートラインは、『これをやればなんでも一気に解決してしまうのではないか』という人間側の発想であり、ロジックである。抽象化のもつ破壊力が今日の世界をかたち作っている。そして、その発想と技術とがもたらしたサイバー・フィジカル融合が、ビジネスのあり方、産業全体のありよう、社会のありようを変えている」・・・・・・。まさにDXの「思考法」、本質をさまざまな例を示しつつ、語り、呼びかける。
「日本経済復活への最強戦略」が副題。今DXが語られ、「決定的な変化」が起きている。「DXの要諦は『抽象化』にあり、世界は『レイヤー構造』へ進んでいる」「現在のデジタル化の発展の基礎にハードウェアの急速な進化があり、生み出されるデータ量も指数関数的に増大した。しかし、現代の産業の大きな変化、IXをハードウェアの発達、データを含めた『量』の増加だけで説明するのは正しくない。それはたかだか話の半分に過ぎない。同時に、世界の実課題とコンピュータの物理的基盤をつなぐエコシステムが進化し、精巧になったこと、つまりは『質』の変化が決定的に重要だ」「それを実現しているのは、レイヤー構造をしたソフトウェア群である」「関係する技術は、半導体、ソフトウェア、インターネット、ディープラーニング、クラウド、5G等々・・・・・・。それらが計算能力、処理加工が可能なデータ量を向上・拡大させて、ゼロイチの物理的な処理と人間の実課題や経験とが連結するまで、サイバー空間の水位を押し上げた。しかし、本当のスタートラインは、『これをやればなんでも一気に解決してしまうのではないか』という人間側の発想であり、ロジックである。抽象化のもつ破壊力が今日の世界をかたち作っている。そして、その発想と技術とがもたらしたサイバー・フィジカル融合が、ビジネスのあり方、産業全体のありよう、社会のありようを変えている」・・・・・・。まさにDXの「思考法」、本質をさまざまな例を示しつつ、語り、呼びかける。
「ピラミッドでなくレイヤー構造(お菓子のミルフィーユのような、重箱が幾重にも重なるような構造)」「ウェディングケーキの形」「会社がアルゴリズムで動く時代」「IX時代の経営のロジック、デジタル化のロジックを、個人と組織の身体に刻み込む。それがDXの本質である」「特殊から一般、具体から抽象への発想の転換。デジタル化の核心がここにある」「十分に抽象的に発想したうえで、その後に初めて具体化する」「ゼロイチで表現できる計算というコンピュータの処理と、人間が解いてほしい実課題の距離を埋める発展過程、レイヤー構造をしていてレイヤーが増えることで連結して距離を縮める」「アリババはレイヤーを増やすことで成長した。そのレイヤーを支えるのがAPI(ソフトウェアどうしが情報をやりとりするために定められた接続や操作に関する仕様)」「DXで覇権を握ったネットフリックス」「第4次産業革命とは『万能工場』をつくることだ」「DX力とは垣根を越えてパターンを見出す能力のことだ」「夜食のラーメン作りはどう説明されるべきか」「インディア・スタックの本当の凄み」・・・・・・。
冨山さんは「DX→IX→CXの連鎖の先にはSX(社会の変容)、LX(個人の生き方変容)が不可避的に起きていく」「組織能力的にトップから現場まで、その力が高い人材によって構成されているということ、すなわちアーキテクチャ認識力、思考力を持つ人材に恵まれていることが、IX時代において決定的な重要性を持っている」と指摘。「本書は著者と私からすべてのビジネスパーソンへ、IX時代の生き残りと飛躍的成長をかけた応援的挑戦状なのだ」といい、IXの衝撃の実相を実感せよと、体当たりで呼びかけ、結んでいる。
都議選の投票日まで1か月弱――。4日、5日、6日と荒川区、地元の北区・豊島区、町田市の各地域で支援拡大を訴えました。コロナ禍においても、都議選への関心の高まりを感じます。
 荒川区では4日、けいの信一都議の事務所開きに出席。けいの都議はこの4年間での「荒川、隅田川の堤防強化や監視カメラ設置」「公園を利用しての保育所設置」「ワクチン接種を要介護の高齢者へ医師・看護師が訪問して行う『ドクター・タクシー』」など、現場の知恵による政策実現を報告。私も「政治家は仕事ができるかどうか」「結果を出せるかどうか」「けいの都議の日々の『結果を出す政治』は凄いものがある」と訴えました。
荒川区では4日、けいの信一都議の事務所開きに出席。けいの都議はこの4年間での「荒川、隅田川の堤防強化や監視カメラ設置」「公園を利用しての保育所設置」「ワクチン接種を要介護の高齢者へ医師・看護師が訪問して行う『ドクター・タクシー』」など、現場の知恵による政策実現を報告。私も「政治家は仕事ができるかどうか」「結果を出せるかどうか」「けいの都議の日々の『結果を出す政治』は凄いものがある」と訴えました。
 町田市は定数4に有力9人が戦う大乱戦。こいそ善彦都議は町田市で「最も頼りになる人」「明るくて確かな実現力をもつ人」と評価されている人。「公・私立の高校授業料無償化の対象外となった多子世帯に、授業料の一部補助を実現」「暗い場所も多く犯罪も多かった町田市に、大型交番やスーパー防犯灯を設置した」「円滑なワクチン接種のために、相談窓口を公共施設に増やした」など、時局講演会(6日)で訴えました。私も、30年以上前から町田市をよく知っていることから、「市全体の課題をこいそ都議は着実に解決してきた」「町田市にはなくてはならない『確かな力』だ」と訴えました。
町田市は定数4に有力9人が戦う大乱戦。こいそ善彦都議は町田市で「最も頼りになる人」「明るくて確かな実現力をもつ人」と評価されている人。「公・私立の高校授業料無償化の対象外となった多子世帯に、授業料の一部補助を実現」「暗い場所も多く犯罪も多かった町田市に、大型交番やスーパー防犯灯を設置した」「円滑なワクチン接種のために、相談窓口を公共施設に増やした」など、時局講演会(6日)で訴えました。私も、30年以上前から町田市をよく知っていることから、「市全体の課題をこいそ都議は着実に解決してきた」「町田市にはなくてはならない『確かな力』だ」と訴えました。





