 高校時代は青春ドまん中。友情も恋も葛藤も本格化する。我々の時代は、受験勉強を中心とする普通高校と、高卒として社会に出る商業高校・工業高校・農業高校が生きており、社会に旅立つ前の貴重なエネルギー溢るる時、それが高校時代だった。「赤い夕陽が校舎を染めて・・・・・・」の舟木一夫の「高校三年生」は、私の高校三年生の時でドンピシャ。今も同級生が集まるとこのヒット曲を皆で歌う。
高校時代は青春ドまん中。友情も恋も葛藤も本格化する。我々の時代は、受験勉強を中心とする普通高校と、高卒として社会に出る商業高校・工業高校・農業高校が生きており、社会に旅立つ前の貴重なエネルギー溢るる時、それが高校時代だった。「赤い夕陽が校舎を染めて・・・・・・」の舟木一夫の「高校三年生」は、私の高校三年生の時でドンピシャ。今も同級生が集まるとこのヒット曲を皆で歌う。
さて今の高校生の青春は――これをジャニーズの加藤シゲアキが書くというのだから興味が湧く。よくある富裕と貧困、暴力、セックス、屈折の青春群像ではない。「オルタネート」という高校生限定のマッチングアプリを軸として、調理・園芸・音楽等のクラブとアプリで繋がる青春物語。全国に配信される「料理コンテスト」と「文化祭」がクライマックスになる。
円明学園高校を舞台に、調理部部長の新見蓉(いるる)、オルタネートを心奉する伴凪津(なづ)、大阪の高校を中退してかつてのバンド仲間の豊と会いに上京するドラムが命の楤丘尚志の三人が主人公。三人三様の青春が、料理甲子園のような「ワンポーション」と「文化祭」に収斂されていく。恋とともに、確執のあった友や家族との関係も融けていく。SNSを介した現代的な「繋がり」と、イベントに協力して挑むなかで生まれる「繋がり」。この二つの「繋がり」を通して、成長していく高校生の姿はすがすがしい。
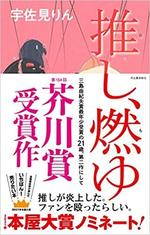 芥川賞受賞作。「推しが燃えた。ファンを殴ったらしい。・・・・・・それは一晩で急速に炎上した」――。主人公の高校生「あたし(あかり)」は、5歳の頃からアイドルグループ「まざま座」のメンバー上野真幸のファンで、いまや徹底した命にかかわるほどの推し。「理由なんてあるはずがない。存在が好きだから、顔、踊り、歌、口調、性格、身のこなし、推しにまつわる諸々が好きになってくる」「皆が推しに愛を叫び、それが生活に根付いている」「推しを推すことがあたしの生活の中心で絶対で、それだけは何をおいても明確だった。中心っていうか、背骨かな」「推しから発されたもの、呼吸も、視線も、あますことなく受け取りたい。・・・・・・朝、推しくんが耳許でおはようと言うんですよ。目が覚めて最初に聴くのが真幸くんの声なんですよ」「体からだるさが溶け出していって、芯から温もって、ああ、きょう、わたしなんとか生きていけるなって思います」「推しは命にかかわるからね」・・・・・・。日常も勉強もバイトも、みんなのようには全くできない「あたし」。そんな生き辛さ、他との拭い難き違和感、孤独感をなんとか凌いで進めるのは唯一、「推しを推すこと」だ。その推しが、ファンを殴り、グループは解散して芸能界から去っていく。「あたし」は推しがいなくなる衝撃を受け「生きていけない」と思いつつも、周りの大人の顔色をうかがい続けた彼が「自分で光を発し始め」、そして今、引退を自ら決断したことに思いを馳せる。なぜ推しが人を殴ったかはわからない。しかし推しの決断を思うなかで「今までの自分自身への怒りを、かなしみを、叩きつけるように振り下ろす」と思うのだ。著者もテーマも若いがリズム感ある熟練の文体。
芥川賞受賞作。「推しが燃えた。ファンを殴ったらしい。・・・・・・それは一晩で急速に炎上した」――。主人公の高校生「あたし(あかり)」は、5歳の頃からアイドルグループ「まざま座」のメンバー上野真幸のファンで、いまや徹底した命にかかわるほどの推し。「理由なんてあるはずがない。存在が好きだから、顔、踊り、歌、口調、性格、身のこなし、推しにまつわる諸々が好きになってくる」「皆が推しに愛を叫び、それが生活に根付いている」「推しを推すことがあたしの生活の中心で絶対で、それだけは何をおいても明確だった。中心っていうか、背骨かな」「推しから発されたもの、呼吸も、視線も、あますことなく受け取りたい。・・・・・・朝、推しくんが耳許でおはようと言うんですよ。目が覚めて最初に聴くのが真幸くんの声なんですよ」「体からだるさが溶け出していって、芯から温もって、ああ、きょう、わたしなんとか生きていけるなって思います」「推しは命にかかわるからね」・・・・・・。日常も勉強もバイトも、みんなのようには全くできない「あたし」。そんな生き辛さ、他との拭い難き違和感、孤独感をなんとか凌いで進めるのは唯一、「推しを推すこと」だ。その推しが、ファンを殴り、グループは解散して芸能界から去っていく。「あたし」は推しがいなくなる衝撃を受け「生きていけない」と思いつつも、周りの大人の顔色をうかがい続けた彼が「自分で光を発し始め」、そして今、引退を自ら決断したことに思いを馳せる。なぜ推しが人を殴ったかはわからない。しかし推しの決断を思うなかで「今までの自分自身への怒りを、かなしみを、叩きつけるように振り下ろす」と思うのだ。著者もテーマも若いがリズム感ある熟練の文体。
豊島区巣鴨に「徳川慶喜・屋敷跡の碑」ミニパークが完成――。20日、岡本みつなり衆院議員とともに現地を視察、中村安次商店会会長と懇談をしました。ここは、徳川幕府15代将軍・徳川慶喜が明治30年から4年間住んだ地。現在の17号に面したところに門があり、広い屋敷がありました。今回、慶喜の碑をリニューアルオープン、さらに道路沿いにミニパークをつくり、水戸にちなんで、偕楽園からの梅の苗木が植えられました。この日も、道行く人が足を止め、碑文を読んでいる姿が見られました。
現在、NHK大河ドラマ「青天を衝け」で、渋沢栄一と徳川慶喜の出会いの場面がちょうど放映されていますが、渋沢栄一を最初に引き上げてくれた重要人物が徳川慶喜です。渋沢栄一が終の棲家とした北区飛鳥山と、巣鴨は大変近いところにあり、因縁を感じさせるミニパークです。
 「命の経済」への転換を訴える。昨年10月の出版だから、「コロナ」のデータは7月頃までが中心だと思う。2021年3月の現在、欧州では「変異株が急増」、日本では「首都圏の緊急事態宣言が21日まで延長、下げ止まらない」「コロナのダメージが長期となり、観光・飲食・航空等の交通機関、そして医療体制と、持ちこたえられない所(倒産等)が出ている」「年内の完全終息は見込めない、重傷者も時々は出る(尾身茂会長)」と厳しい状況にある。アタリ氏は、昨年夏頃までのデータを使ってだが、その本質と未来を観ようとしている。その背後にある分析は「現在のパンデミックが過ぎ去っても別のパンデミックが訪れるだろう」「今回のパンデミックを外出禁止措置等で乗り切ろうとしても、疲弊した企業や医療等は、元に戻らないことがある」ということだ。だからこそ「命の経済」への転換を図ろうというのだ。
「命の経済」への転換を訴える。昨年10月の出版だから、「コロナ」のデータは7月頃までが中心だと思う。2021年3月の現在、欧州では「変異株が急増」、日本では「首都圏の緊急事態宣言が21日まで延長、下げ止まらない」「コロナのダメージが長期となり、観光・飲食・航空等の交通機関、そして医療体制と、持ちこたえられない所(倒産等)が出ている」「年内の完全終息は見込めない、重傷者も時々は出る(尾身茂会長)」と厳しい状況にある。アタリ氏は、昨年夏頃までのデータを使ってだが、その本質と未来を観ようとしている。その背後にある分析は「現在のパンデミックが過ぎ去っても別のパンデミックが訪れるだろう」「今回のパンデミックを外出禁止措置等で乗り切ろうとしても、疲弊した企業や医療等は、元に戻らないことがある」ということだ。だからこそ「命の経済」への転換を図ろうというのだ。
パンデミックの歴史を語り、今回の未曾有のパンデミックに対して、中国には厳しく、ロックダウンの欧米のやり方を批判、"三密""マスク""手洗い"等の韓国・台湾等を褒める。そして、今後の世界は「米中両国が衰退し、覇権国なき世界に向かう変化が加速する」とし、EUの使命に言及する。そして、今回のことで「自己と向き合う貴重な機会を得た」「テレワークの増大」「非営利活動の発展」「情報リテラシー」「心地よい時間こそ大切」など、新しい動き、価値観が生まれていることを指摘する。
そして「命の経済」――。「我々は、組織構造、消費、生産の形態を抜本的に見直す必要がある。経済活動を新たな方向に誘導しなければならない」という。優先課題は「治療薬とワクチン開発」「医療、予防、健康増進のヘルスケアの強化」「新たな対話の形、食生活を改める(少肉多菜、少糖多果、地産地消)」「密集型都市からの脱却」「医療とともに教育に力を入れる(遠隔教育、再就職の職業訓練、生涯学習、遠隔授業、失う社会性やグループ活動、スポーツ、社会活動への支援)」「文化と娯楽の未来」・・・・・・。パンデミック後の成長分野、健康・食糧・住宅・文化・スポーツ・教育等々、そして環境も国土保全も視野に入れた市場では満たせない莫大な需要へのシフト。それが「命の経済」だという。そして「自動車、航空機、工作機械、ファッション、化学、プラスチック、化石燃料、ぜいたく品、観光などの企業が過去の市場を取り戻すことはない」と指摘する。別のサービスへの移行を模索する一方で、「観光業を救え」「持続可能な観光を模索せよ、一部の観光地への過剰観光ではなく、近場の観光も」と提唱する。さらに地球温暖化が人類に危機を及ぼす一方で、それがパンデミックを引き起こす、リンクしていることを指摘する。こうしたパンデミックが100年に1回でなく、たびたび起きるとすると、全くその通りだ。警告と提唱の本。
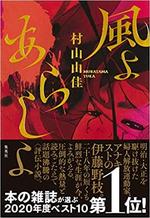 「吹けよ あれよ 風よ あらしよ。強い風こそが好きだ。逆風であればもっといい。吹けば吹くだけ凧は高く上がり、トンビは悠々と舞うだろう。その年、大正2年9月20日――祝いどころか用意もしてやれない困窮の中で、野枝は長男・一を産み落とす」――。明治・大正を激しく駆け抜け、手塚らいてうの「青鞜」に参画し、アナキスト大杉栄とともに憲兵に連れ去られ殺害された婦人解放運動家・作家の伊藤野枝の28年の生涯(1895年~1923年)。
「吹けよ あれよ 風よ あらしよ。強い風こそが好きだ。逆風であればもっといい。吹けば吹くだけ凧は高く上がり、トンビは悠々と舞うだろう。その年、大正2年9月20日――祝いどころか用意もしてやれない困窮の中で、野枝は長男・一を産み落とす」――。明治・大正を激しく駆け抜け、手塚らいてうの「青鞜」に参画し、アナキスト大杉栄とともに憲兵に連れ去られ殺害された婦人解放運動家・作家の伊藤野枝の28年の生涯(1895年~1923年)。
福岡の糸島郡今宿村の貧しい家に育つ。色は浅黒く、小柄で、黒々とした眼光は強いが澄んでいる。野育ち少年のようで、激しく、これほどまでというほどの負けず嫌いで、頭脳明晰。出て来た東京は、近代化・産業化の轟音、日清・日露の戦争を経て、政治・思想闘争は過激を究めていた。幸徳秋水らが処刑された大逆事件が1910年(明治43年)、平塚らいてうの「青鞜」創刊は1911年(明治44年)。10代後半の伊藤ノエはそのど真ん中を疾走した。教師の辻潤と恋愛関係になり、2度目の結婚。そして大杉栄をめぐって妻・堀保子、神近市子、野枝との四角関係は泥沼化し、神近が大杉を刺す日陰茶屋事件に行き着くが、結局は大杉と野枝が結ばれていく。赤貧洗うがごとくの生活で、家賃も払えず家も転々、同志も変転するが、大杉との間では同志的絆も強く、相性も良く、毎年のように5人もの子を成す。そして関東大震災後の混乱のなかで、官憲に捕われ共に殺される。
明治維新から50年――世界も第一次世界大戦、ロシア革命。日本の近代化、労働運動や女性解放・人権運動の勃興期。社会も人間も荒削り、欲望むき出しの時代であったことが、伊藤野枝の激しい生涯(たった28年)を通じてよくわかる。「叔父夫婦をはじめ野枝には苦労のかけられ通しだったろう」「もとより大杉は、行動・実行にこそ重きを置いている。思想を広めるだけで呑気に満足している連中を横目に見ながら・・・・・・」「世の多くの人々は大杉栄を無鉄砲だと思っている。近藤の見る大杉はそうではない。何をするにも計画は細心にして緻密、ただし、いざ心を決めたら算盤を捨てて立ち上がる。計画と実行の間が人より短いだけだ」・・・・・・。どんな思いで死んでいったのだろう。「これでもう失わなくていいのだ。与り知らぬところでひとの命が奪われ、自分ひとり遺されて生きながらえる恐怖に、二度と怯えなくていい。追い求める理想と、炉辺の幸福の間で板挟みになる必要もない」「あらしの時は去っていった。ここには風すら吹かない。この穴よりもなお深い、安堵」・・・・・・。凄まじい評伝小説。



