 「真説 本能寺」が副題。新たな史料を基に、「信長と光秀の確執」などではなく、「信長包囲網」や「世界の大航海時代の植民地獲得、鉄砲、キリスト教」などの動きから「本能寺の変」を解読する。迫力ある書。「光秀単独犯行はありえない」「謎だらけの明智光秀」「革命家信長の光と闇」「戦国時代はグローバル社会だった」「戦乱の日本を覆うキリシタンネットワーク」「『本能寺の変』前と後」の6章より成る。
「真説 本能寺」が副題。新たな史料を基に、「信長と光秀の確執」などではなく、「信長包囲網」や「世界の大航海時代の植民地獲得、鉄砲、キリスト教」などの動きから「本能寺の変」を解読する。迫力ある書。「光秀単独犯行はありえない」「謎だらけの明智光秀」「革命家信長の光と闇」「戦国時代はグローバル社会だった」「戦乱の日本を覆うキリシタンネットワーク」「『本能寺の変』前と後」の6章より成る。
「本能寺の変」前夜の日本の空気――。「天皇を超える『太上天皇』になろうとした信長に対して、朝廷と足利幕府の再興を狙った近衛前久」「信長に仕えながらも忠誠心を持ちきれず、もともと身を置いていた幕府勢力についた明智光秀」「信長打倒計画を知りながら防ごうとせず、その計画を利用し、キリシタン勢力と組んで天下を取ろうとした豊臣秀吉」「残虐性、人の情には無頓着、合理的で先進的な信長は、国内的な視野しかもたぬ者とは違って、中央集権と重商主義の政策をとり、突き進んだ」・・・・・・。国家観、世界観がまるで違うのだ。歪み、激突は自然の帰結ともいえる。
「織田軍挟み撃ちの黒幕は近衛前久」「足利幕府は元亀4年(1573年)には滅亡しておらず、義昭が幕府を移した鞆の浦で権勢を保っていた」「光秀も組み込まれた信長謀殺計画」「富士宮市の日蓮宗西山本門寺に"信長の首"が祀られており、"明智に誅される"(上が罪ある者を成敗する)とある」「光秀の積もりに積もった鬱屈――信長に命じられる長宗我部元親の四国問題、家康の接待、秀吉への援軍、そして転封。そこへ前久から朝廷を守るために討てという"勅命"。光秀のもつ正義」「京都の阿弥陀寺に運び出された信長の遺骨」「戦国時代の100年間はグローバル社会だった(鎖国史観で消された)」「戦乱の日本を覆うキリシタンネットワーク」「信長を利用し、育てたイエズス会(ルイス・フロイス、ヴァリニャーノ)」「イエズス会(スペイン)と決別し、急速に不安定化した信長政権」「天下人になった秀吉はスペインのいう"明国出兵"をのんだ」「イエズス会を後ろ盾としたゴッドファーザー黒田官兵衛」「日本最大の価値・石見銀山をもつ毛利輝元もキリシタン大名派に寝返った」「大情報網となっていたキリシタンネットワーク。信長暗殺計画も近衛前久→吉田兼和→細川幽斎→黒田官兵衛→秀吉政権樹立」「石見銀山の銀と鉄砲や南蛮貿易、それに介在するイエズス会の布教と貿易」「信長・秀吉の中央集権・重商主義が朝鮮出兵で敗北し、家康は地方分権体制と農本主義政策に転じた」「官兵衛の天下取り狙い」・・・・・・。
真実への探索のエネルギーは今も続いている。面白い。
29日、沖縄県那覇市で行われた「那覇空港第2滑走路供用セレモニー」に出席し、挨拶をしました。
これには、菅義偉官房長官、赤羽一嘉国交大臣、岸田文雄・自民党政調会長、衛藤晟一沖縄・北方担当大臣、遠山清彦衆院議員をはじめ、国会議員、地元有識者が出席しました。
私は、この第2滑走路の起工式に国交大臣として出席しており、この程の完成には感無量のものがあります。挨拶で私は「当時の仲井真知事から一刻も早い完成を強く要請され、工期を当初の7年から5年10ヶ月に大幅短縮した」「海に突き出た滑走路なので台風などで工事の遅延が心配されていた。工事関係者のご努力に感謝申し上げたい」「那覇空港は、観光をはじめ、国内外の人の往来や生活物資・農水産物の輸送の拠点として、経済活動を支える重要な社会インフラである。この第2滑走路が、人・モノ・カネの活性化に大きく貢献し、観光をはじめ、沖縄経済復活の光明になる」「さらに渋滞解消など必要なインフラ整備に努めたい」などと述べました。
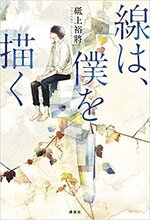 なんとも美しい小説。水墨画のもつ奥深さと宇宙・生命の哲理の美しさ。師弟の峻厳な美しさ。青春の美しさ。それが際立つ作品。
なんとも美しい小説。水墨画のもつ奥深さと宇宙・生命の哲理の美しさ。師弟の峻厳な美しさ。青春の美しさ。それが際立つ作品。
高校時代に突然、両親を交通事故で失った大学生の青山霜介。喪失感のなか抜け殻のような日々を送っていたが、バイト先の展覧会場で水墨画の巨匠・篠田湖山と出会う。水墨画に関して感想を聞かれた霜介は、なぜか湖山に気に入られて内弟子となる。卓越した観察眼の持ち主だと見抜かれたのだ。全くの素人の霜介だが、一気に水墨画の世界に魅入られていく。湖山門下の西濱湖峰、斉藤湖栖、そして湖山の孫の千瑛ら、いずれも超一流の芸術家であり凛として優しい。
「水墨というのはね、森羅万象を描く絵画だ。宇宙とは現象、現象とはいまあるこの世界のありのままの現実ということだ。・・・・・・現象とは外側にしかないものなのか? 心の内側に宇宙はないのか? 自分の心の内側を見ることだ」「墨と筆を用いて、その肥痩、潤渇、濃淡、階調を使って森羅万象を描くのが水墨画だが、絵画であるにも拘らず着彩を徹底的に排する。そもそも我々の外側にある現象を描く絵画ではない」「水墨画は確かに形を追うのではない、完成を目指すものでもない。生きているその瞬間を描くことこそが、水墨画の本質なのだ」「命を見なさい。青山君。形ではなくて命を見なさい。・・・・・・私は花を描け、とは言っていない。花に教えを請え、と君に言った」「勇気がなければ線が引けない」「僕は線を思い浮かべていた。今日この場所にたどり着くまでに描いた線のこと、そこから多くの人が紡ぎ合っている線のこと。・・・・・・僕は長大で美しい一本の線の中にいた。・・・・・・線は僕を描いていた」・・・・・・。
諸法実相、如実知見。水墨画の一筆と線が「命」に向き合う。喪失感に沈んだ一青年が、水墨画が1本の線から描かれ姿を見せていくように成長の姿として描かれる。作者の砥上裕将氏は若き水墨画家。
東京を水と緑の都に――。26日、公明党東京都本部の「水と緑の回廊PT」(顧問=太田昭宏、座長=竹谷とし子参院議員)は、衆議院第一議員会館でPTを開き、国交省、東京都、「玉川上水・分水網を生かした水循環都市東京連絡会」(代表=山田正・中央大学教授)の三者が集合し、打ち合わせや意見交換を行いました。関係者が一堂に会し、非常に画期的な日となりました。これには、竹谷としこ参院議員、岡本三成衆院議員、都議会から小磯善彦、谷村孝彦、上野和彦、古城まさお各都議会議員らが参加しました。
このPTは「水の都・東京」をめざし、水質の悪い外濠を浄化し、あわせて日本橋川などの水流を舟運・観光のできるものにしようと取り組んできたもの。この日、「外濠・日本橋川を浄化するには玉川上水域等からの導水が必要なこと」「上水道、下水道と水量の関連」「水利権や、工業用水との兼ね合いなどの問題」「ひどいアオコを除去する方法」などの議論ができ、大変良いスタートとなりました。
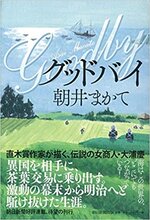 時は幕末から明治の大激動期――。長崎の油商・大浦屋を継いだ女あるじ・お希以、のちの大浦慶。黒船来航で激震が走る日本。安価な油が広がって老舗の経営も厳しくなるなか、一発勝負の異国との茶葉交易に打って出る。茶葉には全くの素人、"女性"というだけで侮られる商人の世界。しかし、お希以は佐賀嬉野の茶葉と連携、イギリスの若き商人ヲルトから大量の注文をもらい、巨万の富をつかむ。幕末の動乱期の長崎には坂本龍馬や近藤長次郎、大隈重信、岩崎弥太郎、イギリス商人のガラバア(グラバー)ら、回天・革新の空気が充満する。胆がすわり、一直線に進む大浦慶は商人として信頼され、志士に対して資金面で手助けもする。「おなごが国事にかかわって何が悪かか」・・・・・・。しかし、明治となり、詐欺事件に巻き込まれて全てを失い巨額の借金を背負い込む。長崎中から嗤われる。「逃げようとは思わない。『今こそ私の正念場、戦たい』雨の中で、大声を発していた」――。縁あって"横浜製鉄所"の乗り出し再起する。「鉄製蒸気船」まで所有する。一直線というか、根性というか、情熱というか、女性の逞しさと強さが噴出する。凄い。
時は幕末から明治の大激動期――。長崎の油商・大浦屋を継いだ女あるじ・お希以、のちの大浦慶。黒船来航で激震が走る日本。安価な油が広がって老舗の経営も厳しくなるなか、一発勝負の異国との茶葉交易に打って出る。茶葉には全くの素人、"女性"というだけで侮られる商人の世界。しかし、お希以は佐賀嬉野の茶葉と連携、イギリスの若き商人ヲルトから大量の注文をもらい、巨万の富をつかむ。幕末の動乱期の長崎には坂本龍馬や近藤長次郎、大隈重信、岩崎弥太郎、イギリス商人のガラバア(グラバー)ら、回天・革新の空気が充満する。胆がすわり、一直線に進む大浦慶は商人として信頼され、志士に対して資金面で手助けもする。「おなごが国事にかかわって何が悪かか」・・・・・・。しかし、明治となり、詐欺事件に巻き込まれて全てを失い巨額の借金を背負い込む。長崎中から嗤われる。「逃げようとは思わない。『今こそ私の正念場、戦たい』雨の中で、大声を発していた」――。縁あって"横浜製鉄所"の乗り出し再起する。「鉄製蒸気船」まで所有する。一直線というか、根性というか、情熱というか、女性の逞しさと強さが噴出する。凄い。
苦境に陥っても次に進む。敗北しても次に進む。「ああ、よかね。皆を乗せて、大海原に漕ぎ出そう。宗次郎しゃん、友助。空も海も、どこまでも青かね。ほら波濤が白く輝いとうよ。あんたがたにこの景色を捧げて、私はようやく心から告げよう。グッドバイ」「人生なるもの、人との縁こそが風であり、帆であると思ったりする」「野心や見栄や恨みつらみ、悔いも山と抱えて、今、何をし遂げたかと己に問えば、まだ途半ばだとしか言えぬだろう。なれど、生きている間は精一杯を尽くすとよ」・・・・・・。そして本書は「遠くで海の音が鳴る。今日もまた、誰かが漕ぎ出すのだろう。遥けき世界へと」と結んでいる。





