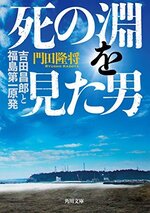 3.11東日本大震災から9年。新型コロナ感染症との戦いで、「追悼の式典」も中止された。しかし、本書原作の映画「Fukushima50(フクシマフィフティ)」がこの3月6日に公開され、書店には本書が店頭に並んでいる。「吉田昌郎と福島第一原発」「現場に残った勇気ある50人を世界はこう呼んだ」とあるが、本書を読み、「東日本大震災」「原発」に対して、多くの被災された方々、これに戦いを挑んだ方々に思いを致し、人間の「慢心」を戒め、復興に努めることが大事だと思う。
3.11東日本大震災から9年。新型コロナ感染症との戦いで、「追悼の式典」も中止された。しかし、本書原作の映画「Fukushima50(フクシマフィフティ)」がこの3月6日に公開され、書店には本書が店頭に並んでいる。「吉田昌郎と福島第一原発」「現場に残った勇気ある50人を世界はこう呼んだ」とあるが、本書を読み、「東日本大震災」「原発」に対して、多くの被災された方々、これに戦いを挑んだ方々に思いを致し、人間の「慢心」を戒め、復興に努めることが大事だと思う。
迫真のギリギリの局面が次々と甦る。大地震、大津波の襲来、そして全電源喪失。「人命と原子炉を守る」――吉田昌郎所長、伊沢郁夫中央制御室当直長(1号機、2号機)らの死に物狂いの戦い。原子炉へ水のラインを開けるべく突入。格納容器の圧力の異常上昇とベント。「俺が行く」――誰が原子炉建屋に突入するか。「われを忘れた官邸」と菅首相の乱入、「なんでベントをやらないんだ!」。自衛隊の消防車への"出動要請"。原子炉建屋への突入、ベント操作。ベントへの再チャレンジ。1号機で水素爆発、建屋の5階が吹き飛ぶ。海水注入。海水注入中止の命令(官邸の介入と混乱)。3号機の原子炉建屋で水素爆発。水が入っていかず最大の危機を迎えていた2号機。「全員撤退」問題と菅首相の東電での発言。2Fへの退避と残った69人(フクシマフィフティ)。協力企業のなかにも現場に戻る必死の男、決死の自衛隊。凄まじい執念の注水作業で暴走するプラントも冷却へ。「家族」「七千羽の折鶴」「運命を背負った男・吉田昌郎と地涌菩薩。チェルノブイリ事故×10」・・・・・・。
「決死の仲間」「人間の"慢心"と"侮り"」「現場のわからない中央のリーダー」「人間には命を賭けなければならない時がある。その命を賭けて毅然と物事に対処していく人がいる」・・・・・・。土壇場における「現場の底力と信念」が日本の本当の力である。そして日本を救った。感謝。
 3・11東日本大震災から9年――。それを前にして福島県・双葉町で初めて避難指示が解除され、14日には常磐線が全線再開となります。双葉駅、大野駅、夜ノ森駅の周辺が一部解除され、真新しい駅舎や役場連絡所が常磐線とともに動き始めます。伊沢史朗・双葉町長が「時間がかかったがようやくここまできた」「ただ、今回の解除がイコール『住民帰還』となるわけではない」と語っているように住民帰還の2年後の春を目指しての新たな戦いが開始されます。9日、赤羽かずよし国交大臣とも話し合いを行いましたが、復興支援への強い決意を述べていました。
3・11東日本大震災から9年――。それを前にして福島県・双葉町で初めて避難指示が解除され、14日には常磐線が全線再開となります。双葉駅、大野駅、夜ノ森駅の周辺が一部解除され、真新しい駅舎や役場連絡所が常磐線とともに動き始めます。伊沢史朗・双葉町長が「時間がかかったがようやくここまできた」「ただ、今回の解除がイコール『住民帰還』となるわけではない」と語っているように住民帰還の2年後の春を目指しての新たな戦いが開始されます。9日、赤羽かずよし国交大臣とも話し合いを行いましたが、復興支援への強い決意を述べていました。
2015年3月1日、常磐道が全通。安倍総理とともに、国交大臣であった私は開通式典に参加。内堀雅雄・福島県知事や多くの市町村長とともに喜びを分かち合いました。今回の常磐線全線再開は関わりを持ってきた私としても感慨があり、復興の大きな節となると思います。
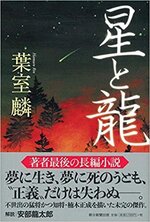 葉室麟の最後の長編で、未完のもの。楠木正成を描く。後醍醐天皇の建武の新政までは描いたが、足利尊氏らの九州への駆逐、反撃に転じた足利軍と楠木・新田義貞連合軍との湊川の戦い、正成の最後は書かれていない。本当に残念だ。
葉室麟の最後の長編で、未完のもの。楠木正成を描く。後醍醐天皇の建武の新政までは描いたが、足利尊氏らの九州への駆逐、反撃に転じた足利軍と楠木・新田義貞連合軍との湊川の戦い、正成の最後は書かれていない。本当に残念だ。
北条得宗家の命を受け、同じ悪党を討伐することで正成は名を上げる。築城・籠城・情報戦・電撃戦と縦横無尽の軍才をもった正成だが、その精神の骨格を成したものが、夢窓疎石の弟子・無風から受けた朱子学であった。中国・南宋の「夷敵を撃つ精神」「帝によってこの世を作り替える」「天子は徳によって世を治めてこそ天子なのだ」「悪党であるがゆえに正しきことをなそうと若きころ心に思い定めた」「正成の生き方は生涯で正しきことをなしたいということであった」――。
安部龍太郎が、末尾に「夢と希望と作家の祈りと」との心に浸み入る解説を載せ、「複雑怪奇な南北朝時代・・・・・・。そのシンボルとして葉室さんが選んだのが、理想の象徴としての星である後醍醐天皇と、天に駆け昇ろうとする龍に見立てた楠木正成だった」と言っている。正成は後醍醐天皇を隠岐島から脱出させ、反幕勢力の布陣を整え、自ら千早城に幕府の大軍を引きつけ、ついに倒幕を成し遂げる。しかし、理想と現実は当然異なる。足利によって護良親王は殺害され、その背後には帝自身がいる。足利尊氏の台頭、新田義貞の巻き返しがある。「楠木ならばいずれ足利を退治いたすこともできよう。朕をしのごうとするものは護良であれ、尊氏であれ、天罰を被るのじゃ。後醍醐天皇は満足げに嘯いた」と描いている。正成と志を共にした鬼灯には「どのような敵にも打ち勝つ、魔神のごとき戦上手の楠木様の一番の弱みは正しき道を求めるところでございますな」と語らせている。「天と天皇」「朝廷と武士」「南宋における朱子学と貿易」「日宋、日元貿易と宋銭」など、根源的問題が自然のうちに剔り出されている。
 「SNSが変えた1400年の宗教観」が副題。「日本人はイスラム教を危険だ、怖いと思っているが違う。イスラム教は平和な宗教なのだ」ということが通説となっている。しかし現実には、ヨーロッパなどで性犯罪や暴力、価値観の違いに由来する問題が多発している。「なぜ」との問いも「平和の宗教」という通説がその思考を遮断している。飯山さんは「2000年以降、ジハード主義が世界中で急速に拡大した背景にあるのはイスラム2.0であると考えている」「2000年初頭からIT、SNS、動画サイトが登場。一部の宗教エリートのものだった『コーラン』『ハディーズ』の知識が、容易に直接触れられるようになり、ここ10年ほどのイスラム教徒たちの行動を大きく変えた」「イスラム2.0時代は、一般信徒が徐々に啓示に忠実な『真に正しい』信仰に覚醒し、原理主義化していく時代。多くのイスラム教徒が近代的価値観に違和感を持ち、異議を唱え、よりイスラム的な価値の実現を求める時代だ」という。
「SNSが変えた1400年の宗教観」が副題。「日本人はイスラム教を危険だ、怖いと思っているが違う。イスラム教は平和な宗教なのだ」ということが通説となっている。しかし現実には、ヨーロッパなどで性犯罪や暴力、価値観の違いに由来する問題が多発している。「なぜ」との問いも「平和の宗教」という通説がその思考を遮断している。飯山さんは「2000年以降、ジハード主義が世界中で急速に拡大した背景にあるのはイスラム2.0であると考えている」「2000年初頭からIT、SNS、動画サイトが登場。一部の宗教エリートのものだった『コーラン』『ハディーズ』の知識が、容易に直接触れられるようになり、ここ10年ほどのイスラム教徒たちの行動を大きく変えた」「イスラム2.0時代は、一般信徒が徐々に啓示に忠実な『真に正しい』信仰に覚醒し、原理主義化していく時代。多くのイスラム教徒が近代的価値観に違和感を持ち、異議を唱え、よりイスラム的な価値の実現を求める時代だ」という。
そして、「ヨーロッパのイスラム化とリベラル・ジハード(移民人口が急増、定住すれども同化せず、ポピュリズム政党は極右?、教育現場でも激しい対立)」「インドネシアにみるイスラム教への『覚醒』(世俗法よりもイスラム法、州知事が冒瀆罪で実刑判決、宗教マイノリティへの寛容度低下)」「イスラム・ポピュリズム(ジョコウィ大統領の選挙戦略、反LGBTが活発化、男と女と夫婦)」「イスラム教の『宗教改革』(エジプトの状況、コプト教徒への迫害と融和策、女性と子供)」など、ヨーロッパ、インドネシア、エジプト等の問題の複雑さ、困難さが述べられる。
最終章「イスラム教徒と共生するために」で、対立・衝突を避けて「どうにか共生を成立させること」「多様性社会への粘り強い知的営為」の努力を求めている。



