 藤沢周平が描くのは市井の庶民、下級の武士たちである。英雄、英傑ではなく、「暗い宿命のようなものに背中を押されて生き、あるいは死ぬ」「負を背負い、世の片隅でもがく人」たちだ。しかしまた、単に平凡に穏やかに生きて死ぬのではない。挫折を繰り返すが意地がある。一矢報いようと心の奥底に小さいが消えることのないマグマをもつ粘り強い人々である。高尚とも思われる俳諧師とは真逆で、貧しさのなかをしたたかに"俗"を生き抜いた一茶はそういう人物だ。「やせ蛙まけるな一茶ここにあり」である。
藤沢周平が描くのは市井の庶民、下級の武士たちである。英雄、英傑ではなく、「暗い宿命のようなものに背中を押されて生き、あるいは死ぬ」「負を背負い、世の片隅でもがく人」たちだ。しかしまた、単に平凡に穏やかに生きて死ぬのではない。挫折を繰り返すが意地がある。一矢報いようと心の奥底に小さいが消えることのないマグマをもつ粘り強い人々である。高尚とも思われる俳諧師とは真逆で、貧しさのなかをしたたかに"俗"を生き抜いた一茶はそういう人物だ。「やせ蛙まけるな一茶ここにあり」である。
小林一茶は1763年(宝暦13年)北信濃の北国街道柏原宿(長野県上水内群信濃町大字柏原)の農家に生まれる。名は弥太郎。3歳の時に母を亡くし、継母には冷たく扱われ、長男であるにもかかわらず15歳で江戸に奉公に出される。「我と来て遊べや親のない雀」だ。いつ頃からか二六庵竹阿の葛飾派の門人となるが、俳諧師として食える訳もなく、豪商・夏目成美の庇護を受ける。貧乏生活だ。「秋の風乞食は我を見くらぶる」である。望郷の念はあるが、一茶の名のごとく(さすらいの身で茶の泡のように消えやすい者)、身を立てているわけでもなく、帰っても居づらい。義弟・仙六との遺産争いが長期化し、悪どい手法は醜いほどだ。
50歳の頃は故郷に帰り、結婚もするが、生まれた子供も次々に死に、58歳の頃には脳卒中で半身不随、妻まで病死する。再婚を二度するが、中風もちの老人の悲哀は悲惨でさえある。「是がまあつひの栖か雪五尺」だ。65歳で死ぬ。「2万句じゃぞ。日本中さがしても、そんなに沢山に句を吐いたひとはおるまい」――藤沢周平は一茶にそう語らせて本書を結んでいる。「わしはの、やお(最後の妻)。森羅万象みな句にしてやった。月だの、花だのと言わん。馬から虱蚤、そこらを走りまわっているガキめらまで、みんな句に詠んでやった。その眼で見れば虱も風流、蚊も風流・・・・・・」「誰もほめてはくれなんだ。信濃の百姓の句だと言う。だがそういうおのれらの句とは何だ。絵にかいた餅よ。花だと、雪だと。冗談も休み休み言えと、わしゃ言いたいの。連中には本当のところは何も見えておらん」・・・・・・。意地、自負、自嘲、ひがみ、鬱懐、疲労、すね・・・・・・。「よろよろは我も負けぬぞ女郎花」「やれ打つな蠅が手を摺り足をする」・・・・・・。「人間がうとましくなると、物言わぬ動物や草木が好ましくなった」と開き直った一茶は自然と人間を詠みまくった。
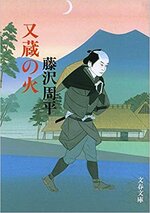 藤沢周平の初期の作品集。昭和48年直木賞受賞作「暗殺の年輪」の前後に書かれた短編。「又蔵の火」「帰郷」「賽子無宿」「割れた月」「恐喝」の5編でとてもいい。「話の主人公たちは、いずれも暗い宿命のようなものに背中を押されて生き、あるいは死ぬ」「読む人に勇気や生きる知恵を与えたり、快活で明るい世界をひらいてみせる小説が正のロマンだとすれば、ここに集めた小説は負のロマンというしかない」と藤沢氏自身が語っている。
藤沢周平の初期の作品集。昭和48年直木賞受賞作「暗殺の年輪」の前後に書かれた短編。「又蔵の火」「帰郷」「賽子無宿」「割れた月」「恐喝」の5編でとてもいい。「話の主人公たちは、いずれも暗い宿命のようなものに背中を押されて生き、あるいは死ぬ」「読む人に勇気や生きる知恵を与えたり、快活で明るい世界をひらいてみせる小説が正のロマンだとすれば、ここに集めた小説は負のロマンというしかない」と藤沢氏自身が語っている。
「又蔵の火」は、素行が荒れて放蕩者、一家の面汚しとして殺されるに至った兄、死ぬことでかえって皆に安堵された兄に対して、「兄に代わって一矢報いたいと仇討ちをする又蔵」。その心に宿る"火"を描く。「帰郷」の宇之吉、「賽子無宿」の喜之助、「割れた月」の鶴吉、「恐喝」の竹二郎。まさに負を背負い、かすかな善意を人一倍感じて命を差し出す"名もない""世の片隅に追いやられた"男の宿命、悲哀が描かれる。もの悲しいが心に浸り入る。
「帰郷」は今年1月、映画化され全国で上映されている。主演は仲代達也、監督は杉田成道。舞台となる信州・木曽福島は御岳、木曽駒ケ岳などの美しいアルプスの山々と空、キリっと引き締まった空気が、家族を捨てた老境の男の懺悔と贖罪を際立たせる。映画も原作もともに秀逸。小説がいいと映像が見劣りすることが多いが、この映画は作品に奥行きと美しさと苦悶や切なさが明らかに付加されている。
「一矢報いる」「自らの人生に決着をつける」――。最終の命の火を誰かの為に使いたいと人は思う。その負のロマンに心を揺さぶられる。
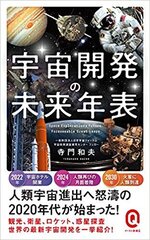 宇宙空間は大変なことになっている。凄まじい激しい競争になっている。この1、2年でも次々と歴史を画する打ち上げ、それも多数の民間企業の参入によって、イノベーションが次々と起こり、「人類宇宙進出へ怒濤の2020年代」が始まった。宇宙観光旅行がスタートし、宇宙ホテルも2022年開業となる。2024年には人類が再び月面着陸をめざすアルテミス計画、月の周回軌道上のステーション「ゲートウェイ」の建設や火星への有人着陸計画も動き出している。
宇宙空間は大変なことになっている。凄まじい激しい競争になっている。この1、2年でも次々と歴史を画する打ち上げ、それも多数の民間企業の参入によって、イノベーションが次々と起こり、「人類宇宙進出へ怒濤の2020年代」が始まった。宇宙観光旅行がスタートし、宇宙ホテルも2022年開業となる。2024年には人類が再び月面着陸をめざすアルテミス計画、月の周回軌道上のステーション「ゲートウェイ」の建設や火星への有人着陸計画も動き出している。
宇宙にはいまや1万9000個もの物体があるという。衛星が約5000個、衛星を打ち上げたロケットの上段が約2000個、ミッション機器が約2000個、ゴミ破片のスペースデブリがなんと約1万個もある。宇宙交通管理が不可欠だし、安全保障の問題もある。安全保障では2007年に中国が行ったASAT(衛星破壊)実験によって状況が一転し、自国の衛星をどう守るかは、気象観測・通信・安全保障・経済全般にかかわる重大な問題となっている。米、ロ、日、ヨーロッパの宇宙開発先行組に中国、インド、そして新興国が、あらゆる可能性を探って宇宙開発新時代の幕が開いたのが今だ。
「2020年は宇宙観光元年――サブオータビル宇宙旅行から宇宙ホテル、そして商業宇宙ステーションへ(ブルー・オリジン社の商業宇宙旅行、アクシオン・スペース社の宇宙ホテル、スペースX社は月旅行、低軌道は民間に任せるというアメリカの政策)」「2024年、アメリカが再び月着陸を目指す『アルテミス計画』――月着陸のカギは国際協力で建設するゲートウェイ、オバマ時代の空白の8年間を取り戻す」「人工衛星はコンステレーションの時代(低軌道小型衛星群)へ――地球観測衛星もコンステレーションの時代」「大型ロケットも小型ロケットも群雄割拠の時代に――ロケット・ラボ社の成功とヴェクター社の失敗、空中発射式の衛星打ち上げも実現間近」「独自の路線で開発を進める宇宙新興国――急進する中国、インド」「宇宙と安全保障――衝撃与えた中国の衛星破壊実験、衛星破壊の手段、SSAからSDAへ、商業衛星のデータを偵察任務にも活用」「進む太陽系探査計画――太陽、水星、金星、月、火星、木星、土星、小惑星」――。
日本は技術も高く、ベンチャーも生まれている。激しい協力と競争の世界に目を向けなければならない。





