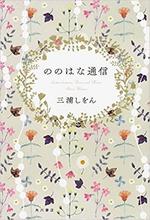 横浜の女子高で出会った野々原茜(のの)と牧田はな。庶民的な家庭で育ち、しっかり者で頭脳明晰な「のの」と、エリート外交官の娘で優しく感じやすい心と芯の強さが同居する「はな」。二人は友情から愛情、そして恋へと進み、関係は行くところまでいく。高校、大学、そして40代と、深い恋がゆえの挫折・別離を繰り返し、時をそのつど置きながらも心の奥の奥を露わにする往復書簡・メールがずっと続く。秘めた魂の交流書簡は、息苦しいほどだ。
横浜の女子高で出会った野々原茜(のの)と牧田はな。庶民的な家庭で育ち、しっかり者で頭脳明晰な「のの」と、エリート外交官の娘で優しく感じやすい心と芯の強さが同居する「はな」。二人は友情から愛情、そして恋へと進み、関係は行くところまでいく。高校、大学、そして40代と、深い恋がゆえの挫折・別離を繰り返し、時をそのつど置きながらも心の奥の奥を露わにする往復書簡・メールがずっと続く。秘めた魂の交流書簡は、息苦しいほどだ。
運命、業の次元の交流のなかで、女性のキメ細やかさと、突っ込む直進の力、胆の決め方には驚嘆する。普通の男性ではとても及ばぬ激しさだ。生老病死の世界に生きる女性の切実さと靭さが、往復書簡の行間を埋め尽くす。淡い女子学生の往復書簡から始まるが、一気に大地が揺らぐような衝撃を受ける。心の奥底のマグマを開け続ける濃密な書だ。
日本の「食」を支える国際物流拠点が誕生――11月23日、北海道の釧路市に行き、国内初の国際バルク戦略港湾・釧路港の国際物流ターミナルを視察。同ターミナル完成式に出席し挨拶をしました。これには、蝦名大也釧路市長、釧路地域の国会議員、経済界や各種団体など多くの来賓が参加しました。
釧路港は全国約4割の生乳を生産する食料生産拠点ですが、水深12mと不足して飼料用穀物を載せた北米からの大型船が入港できませんでした。今回釧路港は、水深を14mにするなど新たに国際物流ターミナルを構築し、東日本の穀物輸入の一大拠点となりました。大型船の寄港で輸送コストが6割になったり、民間投資が誘発されるなど多くの経済メリットが期待されています。これは私が国交大臣の時に全国で初めて整備を開始したものです。
私は挨拶のなかで「パナマ運河の拡張、北極海航路など新しい国際物流時代を迎えるなか、国際バルク港湾として稼働する釧路港の役割は計り知れない」「釧路港を軸とした道東のさらなる発展のために、道路をはじめとしたインフラ整備を進めることが重要。またクルーズ船の対応など観光産業戦略が益々必要になる」と述べました。
また、その後行われた公明党主催の「明日の釧路を考える会」の会合で講演をし「バルク国際港湾としてスタートした釧路港を拠点として、先人が築き上げた歴史と文化の北海道を、世界の北海道として国際社会に大きく展開することが重要」と述べました。
 「インターネット以来の『革命』に乗り遅れるな」「IT革命は、ブロックチェーンによって完成される」「インターネットの世界では経済的な価値を簡単に送ることができなかった。そして真正性の証明ができなかった。このインターネットに欠けていた2つ(経済的な価値を送ること、信頼を確立すること)を我々はいま、ブロックチェーンによって手に入れようとしている」――。ビットコイン等の仮想通貨とその基礎技術であるブロックチェーンの世界は、インターネットの衝撃と同じくらいの重要性をもち社会を変える、という。そして、「人間の仕事の価値が高まる」「コンピュータが得意な仕事はAIやブロックチェーンに任せ、人間は人間にしかできないことをする」という世界が期待される。
「インターネット以来の『革命』に乗り遅れるな」「IT革命は、ブロックチェーンによって完成される」「インターネットの世界では経済的な価値を簡単に送ることができなかった。そして真正性の証明ができなかった。このインターネットに欠けていた2つ(経済的な価値を送ること、信頼を確立すること)を我々はいま、ブロックチェーンによって手に入れようとしている」――。ビットコイン等の仮想通貨とその基礎技術であるブロックチェーンの世界は、インターネットの衝撃と同じくらいの重要性をもち社会を変える、という。そして、「人間の仕事の価値が高まる」「コンピュータが得意な仕事はAIやブロックチェーンに任せ、人間は人間にしかできないことをする」という世界が期待される。
ブロックチェーンは従来の集中型情報処理システムと異なり、事業でいえば経営者がいない「分散自律型組織(DAO)」で、管理者や経営者がおらず自動的に事業が実行される。「シェアリング・エコノミーには仲介者がいるが、それ自体が過渡的な仕組みで、サービスを提供する人と受けたい人が、ブロックチェーンで直接結びつく。そうなるとウーバーもAirbnbも不要となる」という。「ビットコイン型の仮想通貨が普及すると、従来の金融システムや国家システムの外で通貨が流通するようになる。すると、金融政策が効かないとか、税の徴収に支障が生ずるなどの問題も発生し、国家の構造にも影響を与える可能性がある」――。地殻変動をもたらす大変な時代が始まろうとしている。
 二歳の次男・遼を脳腫瘍で失い、そのことも因となって離婚、実家のある宮崎に長男・悠人とともに帰った里枝。ほどなく「谷口大祐」と再婚して、幸せな家庭を築いていた。ところがわずか3年9か月、物静かで優しい大祐が事故で死亡してしまう。しばらくしてその死を群馬・伊香保の兄・谷口恭一に伝えたところ、写真を見た兄からは「これは大祐ではない。全然別人」との衝撃的な事実を告げられる。里枝からこの「ある男」について相談を受けた弁護士の城戸章良は、真相に迫ろうと動く。
二歳の次男・遼を脳腫瘍で失い、そのことも因となって離婚、実家のある宮崎に長男・悠人とともに帰った里枝。ほどなく「谷口大祐」と再婚して、幸せな家庭を築いていた。ところがわずか3年9か月、物静かで優しい大祐が事故で死亡してしまう。しばらくしてその死を群馬・伊香保の兄・谷口恭一に伝えたところ、写真を見た兄からは「これは大祐ではない。全然別人」との衝撃的な事実を告げられる。里枝からこの「ある男」について相談を受けた弁護士の城戸章良は、真相に迫ろうと動く。
身許を隠さねばならない人間の境遇。無戸籍、戸籍交換。出自の業苦、そしてネット等に顕著な「なりすまし」・・・・・・。残酷な宿命を乗り越える家族の愛。心の奥底に迫るキメ細かな品のある文章が、何とも優しく浸み込んでくる。あの3年9か月がいかに幸福であったか、ずっと心に残る。







