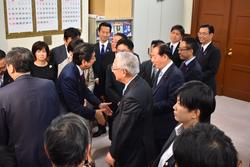全12篇。世界を襲う戦争のために人生・生活を切断される人々。米国で、ヨーロッパで、アジアの国や小さな島々で、日本で、貧しさを乗り越えて、ささやかな幸せを感じてきた人々の戦争による別離と淋しさ。「国政を私物化して共栄を騙る強欲な徒党のために人はあらぬ方向へ歩かされるものだと思いながら、やはり儚いさだめを負わされて大地にうつぶす人を思いやらずにいられなかった」「丹精した畑が見る影もなく寂れたように、夫婦が睦まじく語らい、慰め合うときはもう二度とあるまいと思った。シャオシアも精一杯の微笑を浮かべて、終幕の淋しさに耐えていた」(こんな生活)・・・・・・。
全12篇。世界を襲う戦争のために人生・生活を切断される人々。米国で、ヨーロッパで、アジアの国や小さな島々で、日本で、貧しさを乗り越えて、ささやかな幸せを感じてきた人々の戦争による別離と淋しさ。「国政を私物化して共栄を騙る強欲な徒党のために人はあらぬ方向へ歩かされるものだと思いながら、やはり儚いさだめを負わされて大地にうつぶす人を思いやらずにいられなかった」「丹精した畑が見る影もなく寂れたように、夫婦が睦まじく語らい、慰め合うときはもう二度とあるまいと思った。シャオシアも精一杯の微笑を浮かべて、終幕の淋しさに耐えていた」(こんな生活)・・・・・・。
「歩調はこつこつと生きてきた人の強さのようであり、時代を憎む人の地団駄のようでもあった。雨上がりの石畳はひっそりと輝き、婦人の後ろ姿にも雨のあとがあった。その貧弱なようすが今日の彼には美しく見えて、うつろな視野から消えてゆくまで目をあてていた。するうち唇が震えて、思ってもみない寂寥が押し寄せてきた」(足下に酒瓶)など、描写はなんともキメ細やかで美しく、心の襞に広潤な幅があることを感じさせる名文が続く。「貧しい街から抜け出し、やっと築いた生活とジャズを奪われる若者」(どこか涙のようにひんやりとして)、「小説を書くことを共に志した恋人とも別れる女性――『次々と大切なものをなくしてゆく女の前途に確かなものなどなかったが、傷んだ心の皮を剝いてしまうと、皮肉なことに生きてゆく目的だけが残った』」(万年筆と学友)、「あまりの貧しさから抜け出すために軍隊を志願する兄と残る妹」(とても小さなジヨイ)、「美しい島で一生を送れるはずが、文明と戦争で切断され、お腹の子を宿している新妻と別れて征く夫」(ニキータ)、「戦争は移住者のアイデンティティを引き裂く。完璧なアメリカ人になれる者、なれない者」(みごとに丸い月)、「戦争で別離するも現実に生きる生死の女性と煩悩の男性の淡い違いを明らかにする」(アベーロ)、「無学でも非力でも生きてゆく人の闘い方がある。そのかすかな力が家族たちにも希望の灯となる」(ミスターパハップス)、「見送ることも、(言葉を交さず)早速に去ることも、甘美な記憶と未練を断ち切ることであった」(隔日熱病)、「猫と暮らし、ささやかな幸せを街中で感じていた若者が別れの時を迎えた」(十三分)・・・・・・。
「黙聴と静思を忘れた自己主張の渦から一流の文学は生まれない」「人間を書けない文学は無力である」「報道には報道のための平明な文章があるように、文学には永遠を組み立てる美しい文章があって、後者はどこからか不意に生まれてくる」・・・・・・。なるほどと納得する。
 建設現場も花火大会もアイドルの握手会でも、各々の施設でも、身辺を守ることでも、いまや警備員が支えている日本。その数9000社、54万人。しかし、4K(きつい、汚い、危険、くさい)の職場で給料も低く、高齢者も多い。人手不足だが、2020年東京オリパラなど、ますます必要性は増すが、万全の警備体制を整えることは簡単ではない。その警備業の歴史と課題、今後のAI・ロボット時代へと進むなかでの未来の姿を本書はあます所なく示す。
建設現場も花火大会もアイドルの握手会でも、各々の施設でも、身辺を守ることでも、いまや警備員が支えている日本。その数9000社、54万人。しかし、4K(きつい、汚い、危険、くさい)の職場で給料も低く、高齢者も多い。人手不足だが、2020年東京オリパラなど、ますます必要性は増すが、万全の警備体制を整えることは簡単ではない。その警備業の歴史と課題、今後のAI・ロボット時代へと進むなかでの未来の姿を本書はあます所なく示す。
業務は「施設を守る――1号警備業務」「不特定多数の人や車両を誘導する――2号警備業務」「貴重品や危険物を運ぶ――3号警備業務」「身辺を守る――4号警備業務」となり、警備員となるには欠格要件をクリアし、プロとしての教育がされている。歴史をたどると、まさに昭和39年の東京オリンピックを中心とした高度経済成長の申し子的存在で、その頃に「ザ・ガードマン」が放映され、"用心棒的存在""隠居仕事の守衛さん"からの脱皮があり、「セコム」「ALSOK」の二強体制、機械警備が始まった。現場は二強ではあるが、9000社が示すように中小企業がほとんどだ。高齢者の雇用も日本全体にとって重要なことであるとともに、「労務単価の引上げ」「保険加入」「自家警備問題の解決に向けての徹底通知」など、私自身が行ってきた重要課題にも本書は丁寧に論及している。
「2020東京オリパラで拡大するのは人的警備の需要ではなく、ロボットやAIの需要だと予想される」「警備員という職業は残るが、ロボットやAIへの代替が進み、人的警備は縮小する。そこで重要なのは、どのような人的警備が残るのか、警備業務の専門性と警備員の専門性のどっちを優先するか」だと指摘する。
2日の衆院本会議で2018年度補正予算案を可決、参院に送付しました。
補正予算案の総額は9356億円。このうち、西日本豪雨や大阪府北部地震、台風21号、北海道胆振東部地震などからの復旧•復興費用として合計7275億円。河川や道路などの公共土木施設の修復のほか、被災中小企業の資金繰り支援、被害を受けた農家への支援、関西国際空港連絡橋の復旧支援などが含まれます。
学校の安全対策では、今夏の記録的な猛暑を踏まえ、熱中症対策として公立小中学校などの普通教室全てにエアコンを設置するため、822億円を計上しました。対象は未設置の約17万教室。公立小中学校などの倒壊の危険があるブロック塀の改修には259億円を充てます。
また、採決に先立ち、安倍総理と短時間懇談しました。
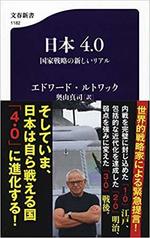 米国の戦略家エドワード・ルトワック氏。日本人は戦略がないどころか、歴史的にみるときわめて高度な戦略文化を駆使してきた。家康は戦国時代の内戦を完全に封じ込める「ガン・コントロール」で敵対者を消滅させ、江戸システムを作った(1.0)。明治維新と近代化と産業化を達成した(明治2.0)。そして1945年、軍事的敗北を経済成長国家へと変貌させた(戦後3.0)。
米国の戦略家エドワード・ルトワック氏。日本人は戦略がないどころか、歴史的にみるときわめて高度な戦略文化を駆使してきた。家康は戦国時代の内戦を完全に封じ込める「ガン・コントロール」で敵対者を消滅させ、江戸システムを作った(1.0)。明治維新と近代化と産業化を達成した(明治2.0)。そして1945年、軍事的敗北を経済成長国家へと変貌させた(戦後3.0)。
今、北朝鮮問題があり、戦争の文化が変わり、米中が戦う地経学的紛争の時代へと進み、日本国内では少子高齢化が進んでいる。どうやってこの国を守るのか。世界の現実を直視しての「日本4.0」に踏み出すことだという。
「日本のチャンスは北朝鮮の非核化が本格的に開始されてからだ。(援助の王)」「北朝鮮問題ではなく朝鮮半島問題だ」「日本は核武装はいらない。先制攻撃能力、リアリスティックな戦闘能力だ」「本物の戦争における特殊部隊論」「現在、世界を脅かすような大国は存在せず、"偉大な国家目的のために戦われる戦争"は起こりにくくなっている」「そこでは犠牲者を出すリスクが過剰なまでに回避される『ポスト・ヒロイック・ウォー』となっている。新しい"戦争文化"を必要としている(総力戦の衰退)」「ポスト・ヒロイック・ウォーの逆説」「地政学から地経学へ」「国家という野獣は地経学的な役割を獲得する衝動に駆り立てられる」「主戦場は軍事的領域から、地経学的な経済、知的財産権、テクノロジーをめぐる紛争に移行しつつある」「イノベーションは小企業で起こる。シリコンバレーの黄昏とテキサス州のオースティンへ」・・・・・・。まさに世界観を変えること、副題の「国家戦略の新しいリアル」を鋭角的に語る。