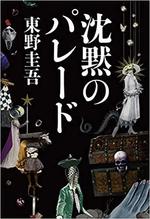 3年前に行方不明となっていた歌手志望の若い女性(並木佐織)の遺体が発見される。容疑者はなんと、20年ほど前に起きた少女殺害事件(本橋優奈ちゃん事件)と同じ蓮沼寛一。しかし犯行確実と思われた両事件はともに、完黙の末「無罪」「証拠不十分」で釈放されてしまう。「あいつがやった」「犯人間違いなし」と思われているのに、司法の場では裁けない無念。遺族や街の人々の憎悪が噴出し、秋祭りのパレードの日、ある計画が挙行される。
3年前に行方不明となっていた歌手志望の若い女性(並木佐織)の遺体が発見される。容疑者はなんと、20年ほど前に起きた少女殺害事件(本橋優奈ちゃん事件)と同じ蓮沼寛一。しかし犯行確実と思われた両事件はともに、完黙の末「無罪」「証拠不十分」で釈放されてしまう。「あいつがやった」「犯人間違いなし」と思われているのに、司法の場では裁けない無念。遺族や街の人々の憎悪が噴出し、秋祭りのパレードの日、ある計画が挙行される。
二件の殺人事件を担当しながら起訴できず、悔しい思いを抱く草薙。米国から帰って人情味が増した感のある湯川(ガリレオ)。並木の家族や友人・戸島、新倉夫妻、佐織の恋人・高垣智也、警察の草薙の同僚・内海薫等・・・・・・。二転三転、絶妙のタッチで真実に迫り、心音を聞いていく。
11月9日、福岡市に行き、高瀬弘美参議院議員の政経セミナーに出席・挨拶をしました。これには、下野六太・参院選予定候補らが参加しました。
挨拶のなかで私は「公明党は常に真っ先に現場に駆けつけ、現場の声を聞き、それを具体的に政策実現することによって、今やすべての政策に公明党が関わっている」「現在国会で論議中の外国人労働者受け入れ問題で大事なことは、まず今の職場をしっかりさせること。そして、日本の若者が入って来られるような環境――『給料がいい、休暇がある、希望がある』の新しい3K、にすることだ」「大きな変革期にある日本において公明党は、変革の渦の先頭に立って、社会保障や防災・減災の対応をしていかなくてはならない」などと述べました。
政経セミナーに先立ち、有料老人ホームを訪問。翌10日は、公明党福岡県本部の幹事会に出席し、明年の統一選・参院選の勝利に向けての日常活動について話しました。
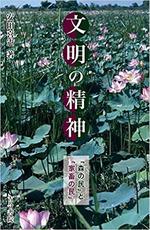 前著「森の日本文明史」に続いて、世界・宇宙をも視野に入れて新しい「生命文明の時代」が来ることをダイナミックに語る。その背景には「この広大な宇宙に生命の惑星地球が存在するだけで奇蹟にちかい。その地球に人類が生きているのはなおさら奇蹟である」との感動があり、一神教の人間中心主義に立つ「物質エネルギー文明」が死を迎え、生命の循環システムに立脚した「生命文明の時代」が構築される、という。前者は自然を支配し人間の王国をつくろうとしたが、これ以上自然の収奪が続けば、現代文明崩壊の闇が迫る。しかも、前者の制度・組織・装置系に憧れ、それを受容している間に、内核としての価値観や心も変わっている。それが今なお破局的に進行している。宇宙・自然の豊かな生命が失われ、人間が壊れていっていると危機感を発する。ましてや日本は、「生命を畏敬する多神教的な世界観と仏教的世界観を温存している」のではないか。それは「池田大作氏とトインビー博士の"21世紀の対話"」でも明らかではないか、という。そして、欧州と違って、城壁を持たない東洋の稲作漁撈型都市を「農村文明」として提唱する。ヨーロッパは「家畜の文明」であり、日本には誇るべき里山があり「森の文明」なのだ。つまり、これからの未来社会は再生力ある「自然=人間循環型の文明」を創造することだ、と強調する。
前著「森の日本文明史」に続いて、世界・宇宙をも視野に入れて新しい「生命文明の時代」が来ることをダイナミックに語る。その背景には「この広大な宇宙に生命の惑星地球が存在するだけで奇蹟にちかい。その地球に人類が生きているのはなおさら奇蹟である」との感動があり、一神教の人間中心主義に立つ「物質エネルギー文明」が死を迎え、生命の循環システムに立脚した「生命文明の時代」が構築される、という。前者は自然を支配し人間の王国をつくろうとしたが、これ以上自然の収奪が続けば、現代文明崩壊の闇が迫る。しかも、前者の制度・組織・装置系に憧れ、それを受容している間に、内核としての価値観や心も変わっている。それが今なお破局的に進行している。宇宙・自然の豊かな生命が失われ、人間が壊れていっていると危機感を発する。ましてや日本は、「生命を畏敬する多神教的な世界観と仏教的世界観を温存している」のではないか。それは「池田大作氏とトインビー博士の"21世紀の対話"」でも明らかではないか、という。そして、欧州と違って、城壁を持たない東洋の稲作漁撈型都市を「農村文明」として提唱する。ヨーロッパは「家畜の文明」であり、日本には誇るべき里山があり「森の文明」なのだ。つまり、これからの未来社会は再生力ある「自然=人間循環型の文明」を創造することだ、と強調する。
家畜を核とするヨーロッパの農耕社会は、自然搾取型の地域システムをつくり、これが世界を席巻するに至った。そして日本は「森の民」としての文明的伝統を維持してきたが、戦後のとくに昭和30年代から40年代、山村が急速に崩壊を始めた。「森の民」日本人の危機である。稲作漁撈民は、森の下草等、海の海藻等の資源を利用し、生命の水を核とする循環システムをつくりあげた。森を破壊し、自然から収奪する欧米文明ではなく、「自然を生かし己をも生かす」自然=人間循環系の縄文の文明原理にこそ真の価値を見い出す時だ、という。そして「里山・里海の生命の水の循環を守り通してきた祖先の生活様式(ライフスタイル)に感謝し、未来を想い描かねばならない」と強く主張し結んでいる。
この8月、豊島区が「東アジア文化都市」に選定されました。これを受け、7日(水)、キックオフとなる「東アジア文化都市2019豊島」シンポジウムが開催され、挨拶しました。
「東アジア文化都市」とは、日本・中国・韓国の3か国から、文化芸術による発展を目指す都市を毎年1都市選定し、年間を通して、3か国の文化交流を図る国家的プロジェクトです。2019年は日本の「豊島区」が選定され、「中国・西安市」「韓国・仁川広域市」とともに、文化の発信を行います。シンポジウムには、主催者である高野之夫豊島区長をはじめ、国会・都議会・区議会の各議員、町会・自治会・各種団体のリーダー、各企業のトップなど多数出席し、盛大に行われました。
私は「2019年は重要な年になる。その先駆的役割を豊島区が担う。ともに頑張っていきたい」と挨拶しました。





