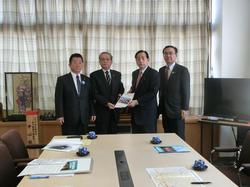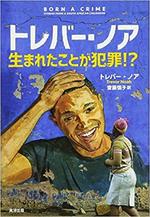 副題は「生まれたことが犯罪!?」。全米で人気の政治コメディ番組「ザ・ディリー・ショー」の司会を務めるトレバー・ノア。ユーモアによって新しい風を吹き込む存在といわれるトレバー・ノアは、アパルトヘイトの南アフリカで、「黒人の母と白人の父から生まれる」という"犯罪"から人生が始まったという。白人と黒人との差別以上に、カラードの矛盾がよりいっそう差別に拍車をかける。「自分が何者か」というアイデンティティにもかかわる問題でもある。壮絶な逆境、毛虫を食べるほどの極貧、全てを覆い尽くす差別と偏見、生き抜くための闇商売、父親からの暴力、荒涼たる人々の心と貧しい喧噪の街・・・・・。不条理きわまりない環境を、"佐賀のがばいばあちゃん"以上のユーモアと生命力で突っ切っていく母(かあさん)あればこそ、トレバー・ノアの今がある。「世間は守ってくれない。きつく叱ったり、たっぷり説教したりするのは、あんたを守ってやりたいから、愛しているから」「世界は好きなように生きられる」との母の愛のこもった声を全身で受けて活躍する彼の姿は、弱き生命力の時代と化した近代社会に、骨太の"笑い"の力を叩き込んで来る。たくましい。
副題は「生まれたことが犯罪!?」。全米で人気の政治コメディ番組「ザ・ディリー・ショー」の司会を務めるトレバー・ノア。ユーモアによって新しい風を吹き込む存在といわれるトレバー・ノアは、アパルトヘイトの南アフリカで、「黒人の母と白人の父から生まれる」という"犯罪"から人生が始まったという。白人と黒人との差別以上に、カラードの矛盾がよりいっそう差別に拍車をかける。「自分が何者か」というアイデンティティにもかかわる問題でもある。壮絶な逆境、毛虫を食べるほどの極貧、全てを覆い尽くす差別と偏見、生き抜くための闇商売、父親からの暴力、荒涼たる人々の心と貧しい喧噪の街・・・・・。不条理きわまりない環境を、"佐賀のがばいばあちゃん"以上のユーモアと生命力で突っ切っていく母(かあさん)あればこそ、トレバー・ノアの今がある。「世間は守ってくれない。きつく叱ったり、たっぷり説教したりするのは、あんたを守ってやりたいから、愛しているから」「世界は好きなように生きられる」との母の愛のこもった声を全身で受けて活躍する彼の姿は、弱き生命力の時代と化した近代社会に、骨太の"笑い"の力を叩き込んで来る。たくましい。
11月16、17日と宮崎県に行き、道路などインフラの現状調査、ジビエ処理加工施設の視察、首長らとの要請懇談などを行いました。これには、遠山清彦衆議院議員、河野敏嗣・宮崎県知事、高千穂・日之影・五ヶ瀬の各町長らが参加しました。
高千穂・日之影・五ヶ瀬の町長からは、高千穂日之影道路と五ヶ瀬高千穂道路の整備促進の要請を受けました。この道路は、宮崎と熊本を結ぶ九州横断自動車道の一部をつくる自動車専用道路で、すでに事業が着手されています。大雨など災害発生時に国道218号の代替道路となったり、救急医療用として、また東九州自動車道の開通によって増加する観光客のためのルートとして、大きな役割が期待されています。途中立ち寄った高千穂峡は絶景で、今後訪れる多くの観光客にとっても、道路は重要なインフラになることを実感しました。
また延岡市では、ジビエ処理加工施設の落成祝賀会に出席し、テープカット・挨拶をしました。この施設は、国の鳥獣被害防止総合対策のもと、ジビエ倍増モデル整備事業の指定を国から受けて設立されたもの。この施設では新鮮なまま加工施設に持ち込まれた猪や鹿を、解体→加工→梱包処理を一括で行うなど国内屈指の施設が揃っており、鳥獣被害防止や近年高まるジビエ需要を満たすことなど、大きな注目を浴びています。宮崎のマスコミも多数来ており、大きな話題となっていました。私も試食しましたが、想像以上に肉質が柔らかく、今までのジビエとは格段に違うことに驚きました。
 「ロマン的魂と商業」が副題。仏文学者の鹿島茂さんの「悪の箴言(マクシム)」を読んだあとだけに、本書に驚いたが、「じつは、創業者や企業家の自伝や伝記を読むのが大好きで、・・・・・・明治・大正期の創業者列伝も書いている」「『破天荒に生きる』『大衆をつかんだ実業家』『名経営者 人を奮い立たせる言葉』の著書・著作を加筆・修正したもの」と知って、納得した。実に面白い。そして明治のリーダーの破天荒、波瀾万丈、猛烈、パッション、ロマンチシズム、すさまじいエネルギーに改めて感心した。
「ロマン的魂と商業」が副題。仏文学者の鹿島茂さんの「悪の箴言(マクシム)」を読んだあとだけに、本書に驚いたが、「じつは、創業者や企業家の自伝や伝記を読むのが大好きで、・・・・・・明治・大正期の創業者列伝も書いている」「『破天荒に生きる』『大衆をつかんだ実業家』『名経営者 人を奮い立たせる言葉』の著書・著作を加筆・修正したもの」と知って、納得した。実に面白い。そして明治のリーダーの破天荒、波瀾万丈、猛烈、パッション、ロマンチシズム、すさまじいエネルギーに改めて感心した。
高島嘉右衛門、浅野総一郎、雨宮敬次郎、根津嘉一郎、福沢桃介、松永安左ヱ門から小林一三、鮎川義介、野間清治に至るまで、近代国家・日本の礎を築いた25人の実業家たちの物語。「明治・大正の巧成り名を遂げた実業家たちの伝記をひもといていくと、心に『浪漫的な冒険』の精神と『詩』を抱えた人物でないかぎり、語の正しい意味での革新者(イノベーター)たりえないことがわかってきた」「その強欲さ、猛烈さにおいて、一種のロマンチシズムを有していない人物でないと、実業家としては成功しえない」という。
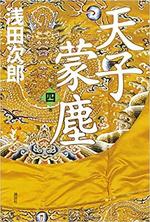 1931年9月、満洲事変が勃発。翌32年3月1日、満洲国の建国が宣言され、執政にラストエンペラー・溥儀が就き、「王道楽土」「五族協和」が謳われる。34年3月1日、溥儀が帝位に就き、満洲国は満洲帝国となる。青空の下で挙行された式典に至るまでの激動、争覇の2年間。日本と中国、そのなかで各人の思惑は異なり、絡み合う。
1931年9月、満洲事変が勃発。翌32年3月1日、満洲国の建国が宣言され、執政にラストエンペラー・溥儀が就き、「王道楽土」「五族協和」が謳われる。34年3月1日、溥儀が帝位に就き、満洲国は満洲帝国となる。青空の下で挙行された式典に至るまでの激動、争覇の2年間。日本と中国、そのなかで各人の思惑は異なり、絡み合う。
大清の復辟だと信じて即位する溥儀は、「祖宗の地たる満洲において足元を固め、いつか長城を越えて喪われた紫禁城を取り返し、太和殿の龍陛を昇って王座に就く」と志す。側につく梁文秀や李春雲等々。欧州から帰還した満洲の覇者・張作霖の息子・張学良は「漢卿、中国には君が必要なのだ」「30万の東北軍を」との声を受け、襲う刺客を葬っていく。蒋介石の思惑、周恩来の思考、そして日本では満洲国建国を推進した石原莞爾、その関東軍とは異なる見解をもつ永田鉄山の信念と現実的判断等々が、生々しく描かれる。そして時代の濁流のなか騒然たる世相も。
「第1部蒼穹の昴」から始まったシリーズ。「珍妃の井戸」「中原の虹」「マンチュリアン・リポート」に続いて「第5部天子蒙塵」が、これで完結する。