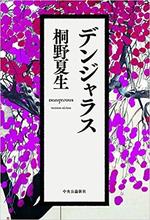 谷崎潤一郎を支え、葛藤・嫉妬する3人の女性。妻の松子、その妹の重子、松子の前夫の子であり、重子の養子となった清一の妻・千萬子。狭い家族の人間模様は谷崎との距離感に起因し、谷崎はその時々に最も望む人間関係をやんわりとつくり貫く。「細雪」の中心的モデルとなり、それを誇る重子が静かに語る。その迫りくる緊迫感には隙間がない。
谷崎潤一郎を支え、葛藤・嫉妬する3人の女性。妻の松子、その妹の重子、松子の前夫の子であり、重子の養子となった清一の妻・千萬子。狭い家族の人間模様は谷崎との距離感に起因し、谷崎はその時々に最も望む人間関係をやんわりとつくり貫く。「細雪」の中心的モデルとなり、それを誇る重子が静かに語る。その迫りくる緊迫感には隙間がない。
戦後の奔放さを身につけ谷崎に寵愛される若い千萬子への嫉妬は、3人の老いともあいまって苦しいほどだ。「松子姉の嫉妬は、私の嫉妬。松子姉の懊悩は、私の懊悩。そして、松子姉の狭量は、私の狭量でした」「結局、兄さんが1番好きなんは兄さん自身、てことですやろか」「兄さんは本当に大きな心で、誰にもよくしてくれました。・・・・・・でも、兄さんは、王国には必要ないと思った人間には、根本のところで冷酷です」――。そして谷崎は「夢と現のあわいを行ったり来たり。あなた(重子)ほど、僕の書く小説の中に生きた人はいませんでしたね」という。
「細雪」「痴人の愛」「鍵」「瘋癲老人日記」・・・・・・。久し振りに谷崎潤一郎の"業"の世界にふれた。
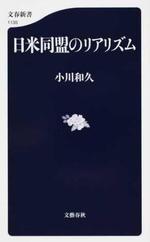 現時点の日米同盟、北朝鮮、中国の戦略・軍事力をきわめてリアルに分析し、「日米同盟の徹底した活用を抜きに、自分の国を自分で守れない」「米国にとって日米同盟の戦略的価値は"死活的に重要"」「"自立"できない構造の自衛隊」であることを論証する。
現時点の日米同盟、北朝鮮、中国の戦略・軍事力をきわめてリアルに分析し、「日米同盟の徹底した活用を抜きに、自分の国を自分で守れない」「米国にとって日米同盟の戦略的価値は"死活的に重要"」「"自立"できない構造の自衛隊」であることを論証する。
論旨はきわめて明確。日米同盟の米国側からの戦略的位置は「世界最強の日米同盟」「日本を失った米国は世界のリーダーの座から転落」「日本は駐留経費負担のお手本」であり、日本の「自主防衛は幻想」「核武装論の虚妄」を解き明かす。ミサイル発射を繰り返す対北朝鮮では、「94年北朝鮮危機の真相」「北朝鮮の軍事力と日・米・韓の"戦争力"と米朝チキンゲーム」「金正恩の"狙い" "メッセージ"と"怯え"」「北朝鮮はインド、中国型経済成長を目指す」「核の配備は通常戦力・兵力を削減し、国家建設志向の意図」を最近の各事案を分析しつつ語る。また中国では「東シナ海で中国を抑え込む日米同盟」「中国の戦略は『三戦(輿論戦、心理戦、法律戦)』と『A2・AD(接近阻止・領域拒否)』」等々について述べる。
暑い日が続いていますが、夏の公明党議員研修会が始まりました。22日(土)、横浜で開催された神奈川県本部の夏季議員研修会に出席しました。
議員の発言をめぐる問題、政治とカネの問題、日常の議員活動の甘さの問題等々、見識等とは程遠い議員の姿が問題となっている最近です。公明党の「大衆とともに語り 大衆とともに戦い 大衆のなかに死んでいく」との立党精神は、「庶民・大衆の心を代弁する議員はいないのか」との噴き上がる声のなかで生まれたものです。
「バッチをつけているだけでは政治家ではない。政治は仕事ができるかどうかだ」「地域を守る灯台たれ」「行動第一の生活現場主義で戦い抜け」「信頼され、愛される議員たれ」「公明党は公平に平等に庶民を照らす『太陽の党』だ」「身近なことから大きなことまですぐやる男」「政治は結果」――。立党精神を胸に、現場を一生懸命走る議員の姿を、私は自分の今の行動を通じて話をしました。











