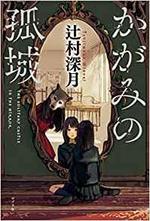「経済成長なくして財政再建なし」――。見るべきものは、「債務対GDP比」であり、それが国際標準的な基準だ。「日本の財政規律についての国際公約(G20サンクトペテルブルク首脳宣言)は『債務対GDPの引き下げ』であって、PB黒字化はそのための"手段"にすぎない」という。ところが日本は97年からデフレに沈むことになるが、税収がふえるといつも政府債務を削ろうとしてきた。消費税を上げ、小泉内閣の時の海外特需にも財政的ブレーキを踏み、安倍内閣でも消費税を上げてアベノミクスにダメージを与えた。常にPB改善が財政健全化の中核であったからだ。財政健全化のためには「増税によるPB改善」ではなく、必要だったのは「政府支出を据え置かないこと」「高成長」だったという。
「経済成長なくして財政再建なし」――。見るべきものは、「債務対GDP比」であり、それが国際標準的な基準だ。「日本の財政規律についての国際公約(G20サンクトペテルブルク首脳宣言)は『債務対GDPの引き下げ』であって、PB黒字化はそのための"手段"にすぎない」という。ところが日本は97年からデフレに沈むことになるが、税収がふえるといつも政府債務を削ろうとしてきた。消費税を上げ、小泉内閣の時の海外特需にも財政的ブレーキを踏み、安倍内閣でも消費税を上げてアベノミクスにダメージを与えた。常にPB改善が財政健全化の中核であったからだ。財政健全化のためには「増税によるPB改善」ではなく、必要だったのは「政府支出を据え置かないこと」「高成長」だったという。
「実態」市場で循環するマネーが「アクティブ・マネー」、「金融」市場に退蔵しているマネーは「デッド・マネー」。「経済成長とは金融市場から大量のマネーが実態市場に注入され、実態市場が活性化していく現象であり・・・・・・。一方、デフレ下では実態→金融市場へとマネーが"逆流"し、アクティブ・マネーが縮小していく」とし、そのためにも日銀の政策である「金融政策」と政府のPB赤字拡大政策である「財政政策」が求められるという。
「財政規律」は当然必要、しかしPBを目標にするなと、激しく「プライマリー・バランス亡国論」をいう。
 奨学金が徐々に拡充し、給付型奨学金もスタートした。日本学生支援機構(JASSO)は、2016年度は132万人に対して1兆944億円が貸し出し、大学生の2.6人に1人(38.5%)が奨学金を利用している。しかし、一方で「奨学金でローン地獄に突き落とされる若者たち」の現実の問題もある。現状と問題点を世界の高等教育も見つつ、現場から提起している。
奨学金が徐々に拡充し、給付型奨学金もスタートした。日本学生支援機構(JASSO)は、2016年度は132万人に対して1兆944億円が貸し出し、大学生の2.6人に1人(38.5%)が奨学金を利用している。しかし、一方で「奨学金でローン地獄に突き落とされる若者たち」の現実の問題もある。現状と問題点を世界の高等教育も見つつ、現場から提起している。
「奨学金返済の実態(非正規からブラック企業へ)(親族の借金が突然降りかかる)」「過酷な取り立ての実態」「"延滞金地獄"のパターン分析」「世界に逆行する日本の教育費政策」等々を解説する。仕組み自体をしっかり理解することから始まり、雇用・労働環境の大変化、「返せなくなったときの対処法」など、詳述する。
最も重要なのは、卒業後にブラック企業などではなく、返済できる雇用を得ること。若者の雇用問題こそ、きわめて重要だ。
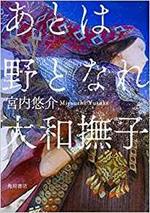 中身を知ると驚く。舞台は中央アジアのかつてアラル海と呼ばれた砂漠と塩の過酷な土地に建国された小国・アラルスタン。カザフスタン、ウズベキスタンなどの大国に囲まれ、米国やロシアの影響も大きく、イスラム過激派の運動もある。「世に文化や信仰は数あれど、その思いだけは万国共通だ。人は世界に関わりたいと願い、そして世界から疎外されつづける。大国に囲まれ、政治も9分9厘まで決められてしまうこのような小国では、なおのこと」・・・・・・。
中身を知ると驚く。舞台は中央アジアのかつてアラル海と呼ばれた砂漠と塩の過酷な土地に建国された小国・アラルスタン。カザフスタン、ウズベキスタンなどの大国に囲まれ、米国やロシアの影響も大きく、イスラム過激派の運動もある。「世に文化や信仰は数あれど、その思いだけは万国共通だ。人は世界に関わりたいと願い、そして世界から疎外されつづける。大国に囲まれ、政治も9分9厘まで決められてしまうこのような小国では、なおのこと」・・・・・・。
その小国・アラルスタンで信頼を得ていたパルヴェーズ・アリー大統領が暗殺され、政府要人は次々と逃亡していく。立ち上がったのが後宮の乙女たち。側室というよりも、アリー大統領は後宮を若い女性たちの高等教育の場と改革した。そのなかにリーダー役のアイシャ、日本人少女ナツキ、その友ジャミラの3人がいた。自分たちでこの国を担うしかない。今の危機を突き破って進むしかない。
"大和撫子"ではなく、まさにダイナミックに荒野を駆けて戦う少女ナツキの純粋な"あとは野となれ大和撫子"だ。国家存亡の危機、人心不安、多民族国家のなかで走る姿を、ハイテンポで次々変化する映像を観るかのごとく活きいきと描く。