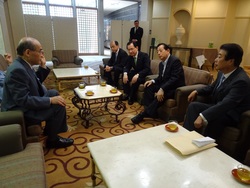いよいよ参院選――。4日、兵庫県姫路市で開かれた公明党兵庫県本部の時局講演会に出席、挨拶をしました。これには伊藤たかえ参院選予定候補(兵庫選挙区)、石見利勝・姫路市長、濱村進衆院議員らが出席しました。
今回の参院選は公明党として7つの選挙区で挑戦。兵庫、福岡は24年ぶり、愛知は9年ぶりです。なかでも兵庫選挙区は大激戦。新人の伊藤たかえさんは弁護士、阪神・淡路大震災の被災経験を原点に建物や地盤の強度問題の専門家として懸命に戦ってきた「被災者に寄り添う弁護士」「生活に親身で相談に乗ってきた弁護士」です。行動派でもあり、先日は熊本地震にも駆けつけ、熊本県弁護士会から要請を受け「義援金の差し押さえ禁止法」の実現にも頑張ってきた人です。講演会では自らの志を訴えるとともに「兵庫で唯一の女性国会議員を」と決意を述べました。
私は、伊藤たかえさんの素晴らしさを訴えるとともに「この3年半、株価は2倍、有効求人倍率は24年ぶりの1.34の高水準、国・地方の税収は21兆円増、高校・大学の就職率はこの数年で最高」「脱デフレ宣言のできる所まで、景気・経済のエンジンをふかす」などを示しました。また「観光はインバウンドで昨年1974万人。産業にまで押し上げた。綺麗になった姫路城にもっともっと多くの人に来てもらうよう頑張りたい」と述べ、支援を訴えました。
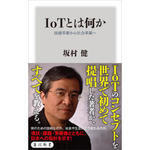 IoT時代が来る。IoT社会が始まっている。技術革新ということの段階を越えて、クローズではなくオープンに。それゆえに技術以外の社会的課題、安全を含めた哲学議論、法的な制度問題が、とくに日本の場合は立ちはだかっている。ドイツの「インダストリー4.0」、米国の「インダストリアル・インターネット・コンソーシアム」の志向するものも同じだが、経済成長の鍵・イノベーションで、日本が遅れをとるわけにはいかない。明確に新段階に突入したIoT社会、IoT時代に、それを引っ張ってきた坂村さんが、IoTの意味するもの、課題(とくに日本の)について述べつつ、総決起を促す書と感じた。それゆえ副題は「技術革新から社会革新へ」だ。
IoT時代が来る。IoT社会が始まっている。技術革新ということの段階を越えて、クローズではなくオープンに。それゆえに技術以外の社会的課題、安全を含めた哲学議論、法的な制度問題が、とくに日本の場合は立ちはだかっている。ドイツの「インダストリー4.0」、米国の「インダストリアル・インターネット・コンソーシアム」の志向するものも同じだが、経済成長の鍵・イノベーションで、日本が遅れをとるわけにはいかない。明確に新段階に突入したIoT社会、IoT時代に、それを引っ張ってきた坂村さんが、IoTの意味するもの、課題(とくに日本の)について述べつつ、総決起を促す書と感じた。それゆえ副題は「技術革新から社会革新へ」だ。
「イノベーションを起こすには、技術だけでなく、制度やものの考え方といった文系的な力もあわせ持つことが重要なのだ。粘り強く議論を続け、ゼロリスクの罠に陥らず、IoT社会に向けた大改革ができるかどうかが問われている。IoTを社会規模で実装して、全体としての高効率化や、安全性向上と個々の利便性の向上の両立という果実を得るのに必要なものは、技術や生産設備よりむしろそういう社会の強靭性だ」「技術的に見ればIoT化が産業機器や家電など、組込みシステムのネットワーク化、高度化の先にある未来にあることは確かだ。しかし、そこには、技術よりもむしろガバナンスチェンジという大きなステップアップが必要で、これについて日本ははなはだ心もとない。・・・・・・ガバナンスも"集中から分散に""クローズからオープンに"する必要があるということだ」「現在の日本は、社会基盤の老朽化やエネルギー危機、災害の脅威、医療体制の懸念、高齢化社会、食の脆弱化・・・・・・。オープンデータにより解決、もしくは緩和される課題は多い・・・・・・。しかし、今までの日本のICT戦略は、技術で始まり技術で終わることが多く、出口戦略がなく、結果として使われないものになっている」。
ロボット、スマートウェルネスシティ、自動運転、ドローン、シェアリングエコノミー、電力自由化・・・・・・。個々がクローズされる中ではなく、あらゆるものが今、クローズからオープン、連携革命の新しい社会への新段階に突入しようとしている。その意識と意欲をもって挑めという。
6月1日、通常国会が閉幕、いよいよ7月10日の参院選へ向けて、全力の戦いとなります。私はただちに今日2日は、激戦の沖縄県議選(5日投票)に来ており、全国の参院選激戦区を中心に走ります。
通常国会では27年度補正予算、28年度本予算が成立。景気回復のために早期執行に努めています。さらに4月の熊本地震対策の補正予算を5月中旬に成立させ、復旧・支援に全力をあげています。また、待機児童対策、介護休業の給付率引き上げ、ヘイトスピーチの解消推進法の成立、女性の再婚禁止期間を短縮する改正民法、衆議院の定数削減と「アダムズ方式」による選挙制度改革関連法の成立などを公明党主導で実現させました。
いよいよ参院選です。この参議院選挙のテーマは何よりも「アベノミクスの加速」です。安倍自公政権の3年半、株価は倍増、有効求人倍率は24年ぶりの1.34、高卒や大卒の就職率はこの10年で最高、国と地方の税収は21兆円増加、年金の積立金も30兆円以上の運用益です。アベノミクスは成果をあげており、これを地域・家計に波及させることが大事です。しかし、デフレ脱却と宣言するまでには至っていないために、何としても経済再建に力をさらに投入することが不可欠です。安倍総理が世界経済の不安定の中で"消費増税の延期"を宣言したのもそのためです。デフレ脱却への背水の陣です。
今日、沖縄県議選のため、沖縄・浦添市へ直行。これからさらに1か月以上、全国を勝利のために走る決意です。
29日、金沢市で開かれた公明党石川県本部(増江啓代表=県議)の時局講演会に連続して出席、挨拶をしました。これには浜田まさよし参議院議員(参院選予定候補=比例区)らが出席しました。
時局講演会に先立ち谷本正憲石川県知事と懇談。知事からは、新幹線効果は全く同じように続いていて、衰えていない。人の流れも3倍となっている。港湾についても物流は急増し、クルーズ船も今年は30隻がすでに予定されている。また、能登の方でも道路の拡幅が進捗している。石川県全体が喜びの中で前進しているという報告がありました。「さらに前進していきたいので支援してほしい」と要望がありました。
時局講演会で私は、北陸新幹線で観光客が急増。人流・物流をさらに拡大するよう全力投球して行く。また、「公明党は現場第一で、庶民や中小企業の心情に寄り添って戦っていく」「政府に対してアクセルとブレーキ役が公明党だ」と訴えました。