 大正関東地震(震災の名は関東大震災、1923年、M7.9)、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災、M7.3)、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)・・・・・・。この20年、今回の熊本地震までに、新潟中越地震等を含め、ほぼ5年に1回は大きな地震に日本は襲われている。
大正関東地震(震災の名は関東大震災、1923年、M7.9)、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災、M7.3)、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)・・・・・・。この20年、今回の熊本地震までに、新潟中越地震等を含め、ほぼ5年に1回は大きな地震に日本は襲われている。
首都圏の地震は「プレート境界で発生するM8クラスの巨大地震と、必ずしもプレート境界ではないが、プレートの沈み込みに伴うM7クラスの大地震の二種類」があり、M8クラスの地震発生間隔はきわめて長い(約390年)。
「東京都を中心とする150k㎡の範囲に、M7程度の地震が100年間で5回程度の頻度で発生している」――明治以降でいえば、明治東京地震(1894年、M7.0)、茨城県南部の霞ヶ浦付近(1895年、M7.2)、茨城県南部の龍ヶ崎付近(1921年、M7.0)、浦賀水道付近(1922年、M6.8)、千葉県東方沖(1987年、M6.7)だ。M8クラスの地震は1923年大正関東地震とその余震(M7以上が複数回発生)、1703年の元禄関東地震(M8.2)などがあるが、このプレート境界地震は発生間隔が長いのでこれを除いて、「30年以内に発生する確率が約70%」という数字が算出されている。1995年の兵庫県南部地震のような危険に備えるということだ。
「首都直下地震とは何か」「予想される被害」「想定から外された東京湾北部地震」「プレート境界の関東地震」「プレート内部での地震(スラブ内地震)(都心南部直下地震)」「30年以内、70%の意味」などが詳述され、「首都圏を守るために」として、耐震化と出火対策、帰宅困難者への対策、自主防災組織の重要性、新しいコミュニティの創出、防災教育などが提唱されている。
10日、地元北区の荒川右岸河川敷で大規模な「平成28年度 第五消防方面・北区合同総合水防訓練」が行われました。
この訓練は毎年、出水期に備えて行われており、東京消防庁第五消防方面本部、北区、赤羽・王子・滝野川の各消防団、町会・自治会、東京消防庁災害時ボランティアなどの多くの方々が参加しました。
会場では河川堤防や地下鉄やビル等への浸水を具体的に想定。「鋼板防護工法」「地下浸水防止工法」「月の輪工法」「地下鉄の排水活動」「土のうを活用した浸水防止工法」など、実践的な訓練が次々と行われました。こうした実践的訓練はきわめて重要なもので、地域にも広げる必要があります。
私は「昨年9月の関東・東北豪雨による常総市鬼怒川の氾濫や4月の熊本地震などが起きており、災害は常に切迫している。協力・連携をいただいて、東京の大規模水害や首都直下地震への備えに万全を期していきたい」と挨拶をしました。
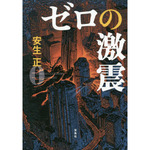 すさまじい、壮絶。安生正「ゼロシリーズ(生存者ゼロ、ゼロの迎撃)」の最新作。最悪の危機は"観たくないから考えない"と甘い想定で思考停止に陥るものだが、あえて関東消滅の危機に迫る。
すさまじい、壮絶。安生正「ゼロシリーズ(生存者ゼロ、ゼロの迎撃)」の最新作。最悪の危機は"観たくないから考えない"と甘い想定で思考停止に陥るものだが、あえて関東消滅の危機に迫る。
栃木県・金精峠で土砂崩れが発生し、足尾町で突然3000人もの町中の住民が謎の死を遂げ、続いて群馬県富岡市が火炎弾等で火の海となる。原因を探ると、マグマの上昇、南下の諸現象であることが判明、物理・土木の技術者・木龍に阻止の任務が下るが失敗する。怒りとも思える自然の力にはかなわない。文明の宿命、人類の無力・・・・・・。そして更にマグマは埼玉県秩父を大噴火による火砕流で飲み込み、新宿区や中野区を壊滅させ、東京全域へ。
東京壊滅をもたらしたこのカルデラ破局噴火。調査の結果、それを誘発したのは、今回新たに地下40kmに建設された東京湾浦安沖のマグマ熱を使った夢の東京湾第一発電所。その立坑に、対岸にある京葉第三発電所から発生する二酸化炭素を地下貯留させるよう結んだことにあるようだ。
技術者の誇りと死をもいとわぬ使命感。政治家の全うな責任と胆の決め方。「自然の怒りを前にして、お前にできることなどなにもない。災害から人々を救うのは技術者の仕事だ。お前ではない。俺だ」「東日本大震災で・・・・・・被爆の危険をものともせず瓦礫の撤去を行った者たちがいた。・・・・・・事故を起こした罪の意識に苛まれながらも、困難に立ち向かった職員たちの献身は、痛みの記憶以外の何物でもない」――。学び、考え、打ちのめされ、成長する。「技術者の誇りはどんな困難も乗り越える」――。現場の力、技術者の誇りと心意気が描かれる。それに"命"を見る政治家の胆が加わってはじめて日本の底力といえる。
5月8日、先月発生した熊本地震で深刻な被害を受けた、熊本県西原村、益城町、熊本市内を訪れ、被害状況を調査。また日置和彦西原村長、西村博則益城町長、蒲島郁夫熊本県知事と要請・懇談を行いました。現地では今も余震が続いており、この日も何度か余震があり、不安な状況が続いています。
西原村は九州の村のなかで唯一と言っていいほど、人口増加をしている村で、市町村経済指標ランキング(内閣府発表)で全国1位を誇る成長著しい村です。ここはちょうど布田川断層帯が通っていることもあり、家屋の損壊は激しく、そのほか、道路、橋、トンネルが崩壊し、村民の生活インフラを根こそぎ奪っています。仮設住宅がやっと着工したところですが、まず復旧が大切です。
益城町でも、家屋の損壊が激しいうえに、今も約4500人の方々が、倒壊の恐れのある自宅に帰れずにいます。水道もまだ3割の世帯で回復しておらず、また漏水も心配されるなど、住民の方の不安はまだまだ解消されていません。西原・益城の両首長からそれぞれ話を伺いましたが、「これだけ甚大な被害を復活させるのは、国の特別措置等の財政支援、全面的支援が不可欠だ」との要望を受けました。
熊本市内では、健軍商店街で破損したアーケードを視察、商店街の理事長などから被害の状況を伺いました。約4割の店が営業を再開できず、アーケードの修復や売り上げの急落を危惧していました。そのあと、甚大な被害を被った熊本城に行きました。約400年前に加藤清正によって建てられた熊本城は、熊本県の文化と観光の大きな柱です。予想をはるかに超えたお城の損壊は、長年このお城に親しんできた地元市民に、はかり知れないショックを与えており、再建が急務です。
そのあと、蒲島県知事と会い、被害の実情、今後の対応などについて懇談。知事からは「熊本の財政がやっと立ち直りかけていたこの時期に、今回の地震があったことは衝撃的だ。この被害に対して、国が財政措置などで支援する、というアナウンスをすることによって、不安に喘ぐ市民に安心感を与えて欲しい」との要望を受けました。
西原村、益城町、熊本市と、同じ地震でも、それぞれの地域にそれぞれ被害状況があり、それぞれに即した対応策が必要です。そうした実情に即した敏速な対応に全力をあげます。
このほか、被害のあった熊本空港を視察したほか、熊本港で給水やお風呂を提供して頑張っている海上保安庁の隊員を激励しました。
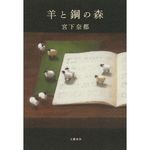 17歳の高校生であった外村は、ピアノの調律に出会い、衝撃を受け、調律師を志す。自らの素質に悩みながらも先輩の暖かさに囲まれ、素直に真正面から取り組み成長していく。音にかかわる深い世界を、素朴に、繊細に、心に沁み入るように描いている。静謐さ、しっとりした湿度、透明感が伝わってきていい。
17歳の高校生であった外村は、ピアノの調律に出会い、衝撃を受け、調律師を志す。自らの素質に悩みながらも先輩の暖かさに囲まれ、素直に真正面から取り組み成長していく。音にかかわる深い世界を、素朴に、繊細に、心に沁み入るように描いている。静謐さ、しっとりした湿度、透明感が伝わってきていい。
羊のハンマーが鋼の弦を叩く。それが音となり、音楽となり、静謐で安らぎのある森の世界へと導く。「明るく静かに澄んで懐しい。甘えているようで、きびしく深いものを湛えている。夢のように美しいが現実のようなたしかな音(原民喜の文体の表現を使っている)」――外村が調律で目指そうとしたものだ。「家の中のどこにいてもなんだか安まらなくて・・・・・・すぐ裏に続いていた森をあてもなく歩き、濃い緑の匂いを嗅ぎ、木々の葉の擦れる音を聞くうちに、ようやく気持ちが静まった。・・・・・・どこにいても落ち着かない違和感が、土や草を踏みしめる感触と、木の高いところから降ってくる鳥や遠くの獣の声を聞くうちに消えていった」「ギリシャ時代、学問といえば、天文学と音楽。音楽は根源なんだよ。・・・・・・無数の星々の間からいくつかを抽出して星座とする。調律も似ている。世界に溶けている美しいものを掬い取る。その美しさをできるだけ損なわないようそっと取り出して、よく見えるようにする」「外村くんみたいな人が、根気よく、一歩一歩、羊と鋼の森を歩き続けられる人なのかもしれない」・・・・・・。沁み入るようだ。












