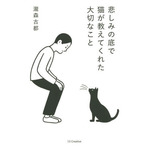 私は「目に見えない縁とか、天の仕業を感じるようになって初めて人生を知る」「諸天善神に守られているという実感を得る人生でありたい」と思う。また「運は連鎖だ」と松下幸之助は言っている。
私は「目に見えない縁とか、天の仕業を感じるようになって初めて人生を知る」「諸天善神に守られているという実感を得る人生でありたい」と思う。また「運は連鎖だ」と松下幸之助は言っている。
「ネコは、ごはんを何回食べなければ死にますか?」と、パチンコ店の前に置かれた一冊の「里親探しノート」の"ぎこちない字"から物語が始まる。五郎、宏夢、弓子、門倉たちの運命が動き出す。
「今生きていることは、奇跡なのよ」「今こうやって生きていること自体が『奇跡』なんじゃないかなって・・・・・・。会いたい人に会えることも、再開したいペットに会えることも、みんな『奇跡』なんだと思うの」「会いたい―― 一目でいいから、宏夢に会いたい――」「五郎ちゃん、俺・・・・・・生まれてきてよかったのかなぁ」――。その奇跡を黒猫のシロが起こし、縁の結び役になる。悲しみの底をさまよった人々に、猫たちが諸天となり、縁の結び役となり、大切なことを教えてくれた。猫も縁あって家族の一員となる。いや猫こそが、かも知れない。感動作。
首都直下地震対策は進んでいるのか――。こうした多くの方の声を受け、27日、公明党首都直下地震対策本部を開催しました。国土交通省や内閣府防災、気象庁から現状報告を受け、打ち合わせを行いました。
東京都心南部直下地震(M7.3)が起きた場合の被害想定は、全壊・消失家屋は最大約61万棟、死者は最大約2.3万人、要救助者は最大約7.2万人、被害額は資産等の被害が47.4兆円、経済活動への影響が約47.9兆円となっています。さらに東京都で490万人を超える帰宅困難者が出ると試算されています。
私が国土交通大臣の27年3月に、首都直下地震緊急対策推進基本計画を改定し、減災目標等を設定しました。今後10年で、想定される最大死者数、建築物全壊・消失棟数を概ね半減、さらに少なくしていこうという計画です。
対策の柱は、防災とともに応急対策活動です。具体的な応急対策活動は、常日頃より緊急出動体制を備えておくもので、(1)救急輸送ルート、防災拠点 (2)救助・救急、消火 (3)医療 (4)救援物資 (5)燃料 (6)帰宅困難者――となっています。とくに首都直下地震では、帰宅困難者への対策が他県とはケタ違いに大きくなります。
また、国土交通省からは、(1)あらゆる対策の大前提としての耐震化と火災対策(建物の耐震化の加速目標、密集市街地対策) (2)深刻な道路交通麻痺対策等(緊急輸送の要となる道路――八方向作戦) (3)膨大な数の避難者・帰宅困難者――などについて報告を受け打ち合わせをしました。
首都直下地震が切迫している今、対策を加速させなければなりません。
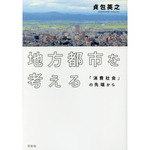 「『消費社会』の先端から」と副題にあるが、大都市の従属としての地方都市ではなく、大都市以上に地方都市が「消費社会」の先端にあると指摘する。問題意識は"人口減少・高齢化"とか"地方消滅"ではなく、より深く「わたしたちが幸福であるために、地方都市は本当に必要か」「わたしたちにとって望ましい暮らしは地方都市の存在と深くむすびついているようにみえる」「大切になるのは、地域に固有とされる伝統や、地方生活のたんなる経済的気楽さではない。それ以上に重要なのは、消費社会の浸透とともに、地方都市に私的な欲望の追求を肯定する場がますます拡がっていることである」という。
「『消費社会』の先端から」と副題にあるが、大都市の従属としての地方都市ではなく、大都市以上に地方都市が「消費社会」の先端にあると指摘する。問題意識は"人口減少・高齢化"とか"地方消滅"ではなく、より深く「わたしたちが幸福であるために、地方都市は本当に必要か」「わたしたちにとって望ましい暮らしは地方都市の存在と深くむすびついているようにみえる」「大切になるのは、地域に固有とされる伝統や、地方生活のたんなる経済的気楽さではない。それ以上に重要なのは、消費社会の浸透とともに、地方都市に私的な欲望の追求を肯定する場がますます拡がっていることである」という。
そこでY市を具体的にモデルとしつつ、「空き家問題」「都市の感覚水準――高層マンション(新しい設備を備えたマンション・家がほしい)」「鉄道」「自動車と街の更新」「メディアや観光やまちづくり」「ロードサイドビジネスやショッピングモールと消費社会」「ローカル経済」「流動化する労働」などを分析。地方都市の消費にかかわる多様な「現在」の姿をあきらかにしている。
「コンパクト+ネットワーク」「対流促進型国土形成」を考えてきた私として、現状を如実知見する考察は学ぶもの大だった。
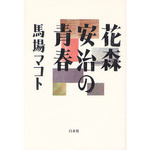 NHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」は、ヒロイン小橋常子が練り歯磨きを作って家族のために儲けようとするところに来ている。そのモデルは、戦後に「暮しの手帖」を立ち上げ、国民的雑誌に押し上げた名物編集長・花森安治と苦楽を共にした盟友・大橋鎭子だ。
NHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」は、ヒロイン小橋常子が練り歯磨きを作って家族のために儲けようとするところに来ている。そのモデルは、戦後に「暮しの手帖」を立ち上げ、国民的雑誌に押し上げた名物編集長・花森安治と苦楽を共にした盟友・大橋鎭子だ。
花森安治は1911年(明治44年)、神戸に生まれ、神戸三中、松江高校、東大の美学に進む。デザイン、カット、挿画、キャッチコピー、文章、宣伝、編集――その卓越さは、生来のものに更に磨きをかけた比類なきものといえる。しかし、その人生はくっきりと戦前・戦後と分かれ、断絶と継続。その陰影が本書の「花森安治の青春」だ。背景には、戦争、言論統制、滝川事件・美濃部事件、そして赤紙一枚で招集されて受けた兵隊いじめの「なぐる、なぐる、なぐる」「貴様らの代りは一銭五厘で来る」との私刑の毎日がある。
「欲シガリマセン勝ツマデハ」「足ラヌ足ラヌハ工夫が足ラヌ」・・・・・・。大政翼賛会宣伝部時代、広告制作を担った宣伝技術家・花森安治は日本宣伝道を走ってしまった。そして「人間は戦争に反射し、発熱し、疾走する動物なのだ」「戦争が起こってしまえば・・・・・・、人は戦争に加担する動物だ。一生懸命やってしまう動物だ」と・・・・・・。
そして戦後、大橋鎭子と妹たちと「暮しの手帖」を立ち上げる。「女性が太陽の暮し。女性が真ん中にある暮し。それが続けば戦争は二度と起こらないはずだ」「女性が太陽の暮し。それを実現するための暮しの工夫や暮しの提案をしよう」「もう時代と並走するのはやめよう。これからは揺るぎない暮しを作っていくのだ」・・・・・・。そして花森安治の国への批判、反戦意識は強く、激しくなっていった。青春時代の筆舌に尽くせぬ苦しい体験、にがい体験と反省、「女性が太陽」に込められた思い等がケタ違いに深く、内奥に刻まれていたことが伝わってくる。





