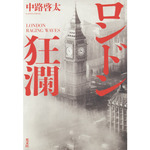 1929年7月、田中政友会内閣が、張作霖爆殺事件(1928年6月)の処理に失敗して総辞職、民政党の浜口雄幸内閣が誕生する。1927年3月の金融恐慌の始まり(東京渡辺銀行)、1929年10月のニューヨーク株式市場の大暴落(暗黒の木曜日)でいよいよ世界恐慌へと突き進む。一方、1928年8月にはパリで不戦条約が調印される。そして1931年9月18日、奉天の郊外・柳条湖付近で満鉄の線路が爆破され(満州事変)、暴走が始まる。
1929年7月、田中政友会内閣が、張作霖爆殺事件(1928年6月)の処理に失敗して総辞職、民政党の浜口雄幸内閣が誕生する。1927年3月の金融恐慌の始まり(東京渡辺銀行)、1929年10月のニューヨーク株式市場の大暴落(暗黒の木曜日)でいよいよ世界恐慌へと突き進む。一方、1928年8月にはパリで不戦条約が調印される。そして1931年9月18日、奉天の郊外・柳条湖付近で満鉄の線路が爆破され(満州事変)、暴走が始まる。
そうした世界の激動のなか、1930年1月からロンドンにおいて日米英仏伊が参加して行われたのがロンドン海軍軍縮会議だ。浜口首相、幣原喜重郎外相が、主席全権として選んだのが首相経験者・若槻礼次郎。拒む若槻を説得し、随員としてピタッと付いたのが雑賀潤外務省情報部長だった。米英列強との激しい攻防のなか、雑賀は激しくも巧みな外交戦を展開し、起死回生の案をまとめ、ついに4月には海軍軍縮条約の調印に迄もっていった。
欧米列強との激烈な攻防、日本国内での軍部との軋轢(随員のなかでも山本五十六ら)、浜口内閣の「緊縮財政」と「協調外交」の2大柱への批判――。それは「弱腰外交だ」「緊縮財政が日本経済にもたらしたのは景気悪化だ」、さらには軍令部の反対を無視して軍縮条約を調印したことは「統帥権干犯」であるとの犬養毅率いる政友会等の追及を浴びる。批准をめぐって、元帥・軍事参議官会議、枢密院の審査の関門はさらに厳しかったが、浜口、幣原そして走り回る雑賀はそれを突破する。「外交は、武器を使わない戦争だ」「交渉を決裂させてはならない」との気迫、そして「これほどの不景気となりながらも、国際協調と平和、国民負担の軽減を謳う民政党政権と、そのためのロンドン海軍条約の成立を大衆は支援した。とりわけ国民が信頼したのは、浜口首相その人の清廉さと不退転の意思であった」という。国民の強い支持あっての成果だ。
しかし、浜口首相は11月14日、東京駅で狙撃され重傷を負い、31年4月内閣総辞職、8月に死去する。若槻礼次郎が組閣するが、関東軍の暴走を収拾できず12月には総辞職。あとを継いだ政友会の犬養も32年5月15日、射殺される。「二大政党制」「国際協調」「緊縮財政」は急転し、日本は戦争へと進んでいく。本書は日本の分水嶺となった浜口内閣の2年弱と最重要案件のロンドン海軍軍縮会議を緊迫感をもって描く。
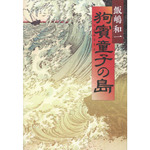 幕末を、松江藩の圧政下にあった日本海に浮かぶ隠岐「島後」から、じつに綿密に描いた重厚な書。時代の激流に離島であるがゆえに翻弄される島民。しかもその地に、大塩平八郎の挙兵(天保8年、1837年)に連座した西村履三郎の息子・数え15歳の常太郎が流人として到着するところから物語は始まる。
幕末を、松江藩の圧政下にあった日本海に浮かぶ隠岐「島後」から、じつに綿密に描いた重厚な書。時代の激流に離島であるがゆえに翻弄される島民。しかもその地に、大塩平八郎の挙兵(天保8年、1837年)に連座した西村履三郎の息子・数え15歳の常太郎が流人として到着するところから物語は始まる。
救民の旗を掲げた大塩平八郎の挙兵だけでなく、「江州湖辺大一揆」「福知山大一揆」の関係者・杉本惣太郎や豊之助も加わり、「数万の農民を凶作と苛政の塗炭の苦から救う」「義に斃れることを栄誉と信じ、誓って奸吏を退ける」という義挙が、底流に流れ続ける。
島民は激動にさらされる。「世間は"御一新"などともてはやしていたが、やはり何ひとつ変わっていなかった」「無能で怠惰な郡代や藩役人個々を追放したかったのではない。島民が、自ら生きることのできないような治世の仕組みそのものを拒否し、それを追放しようとした」はずなのに、島民の苦難は少しも変わらない。しかも島内は「出雲党」だの「正義党・尊攘派」などと敵視しあう緊迫した状況まで生まれる。
医師となった常太郎の「維新政府なるものに対する失望ばかりが募っていた」「31年前、父履三郎が大塩平八郎とともに挙兵したのはいったい何のためだったのか」との思いは、時代を超えて続く。「民の憂い募りて国滅ぶ」「民の欲する所 天必ず之に従う」ということだ。
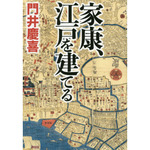 天正18年(1590年)、秀吉によって江戸に転封された家康の見たものは、低湿地の広がる江戸とそこに建つお粗末な江戸城だった。家康はそこで東京湾に注いでいた利根川を太平洋へと流す大工事に乗り出す。第一話はこの「流れを変える(利根川の東遷、荒川の西遷)」だ。これを命ぜられたのが伊奈忠次、それを継いだ伊奈忠治。第二話は「金貨を延べる(天正大判を駆遂し、貨幣を制する小判の貨幣鋳造、金座)」で後藤庄三郎。
天正18年(1590年)、秀吉によって江戸に転封された家康の見たものは、低湿地の広がる江戸とそこに建つお粗末な江戸城だった。家康はそこで東京湾に注いでいた利根川を太平洋へと流す大工事に乗り出す。第一話はこの「流れを変える(利根川の東遷、荒川の西遷)」だ。これを命ぜられたのが伊奈忠次、それを継いだ伊奈忠治。第二話は「金貨を延べる(天正大判を駆遂し、貨幣を制する小判の貨幣鋳造、金座)」で後藤庄三郎。
第三話は「飲み水を引く(七井の池―井の頭から関口、水道橋へと立体交差する神田上水工事)」の内田六次郎、大久保主水藤五郎、春日与右衛門。第四話は「石垣を積む(江戸城の石垣)」の"見えすき吾平"と"見えすき喜三太"。そして大阪夏の陣。第五話は「天守を起こす(白色の江戸城天守閣への家康、秀忠の思考)(漆喰)」は家康が何を考えたかに迫っている。
「国土」「土木工学」に携わってきた者として、また東京に住んでいる者として、きわめて面白かった。
14、15の土日。爽やかな五月晴れのなか、地元では青少年の行事が多く行われました。
14日は北区青年会議所主催の「第40回わんぱく相撲北区大会」が盛大に行われ、小学校1年生から6年生までの多くの子どもたちが参加しました。これまでで最も多い参加者で、保護者の方も含め、大変な盛り上がりでした。
15日は町会・自治会の運動会や第24回カッパまつり等、多くの行事が行われました。
子どもたちを応援しようと、様々な行事の運営をしてくださる地域の方々に感謝です。また、いずれの会場でも熊本地震から1か月となり、お見舞いとともに災害では地域のつながり、絆が大事であることが話されました。こうした地域行事がいろんな意味で大切です。







