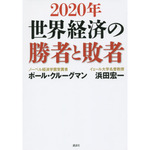 ポール・クルーグマンと浜田宏一さんが「アメリカの出口戦略」「日本のアベノミクス」「ヨーロッパの解体」「中国バブルの深度」の章を立て、それぞれが語っている。
ポール・クルーグマンと浜田宏一さんが「アメリカの出口戦略」「日本のアベノミクス」「ヨーロッパの解体」「中国バブルの深度」の章を立て、それぞれが語っている。
世界経済は年頭から荒れた。原油安、中国経済の減速、ヨーロッパ経済は統一通貨ユーロの弱点の露呈のなかにあるが、それらを分析しつつ、再建途上にある「アメリカ経済と日本のアベノミクス」の役割りが大きいことを指摘する。
アベノミクスは「金融と財政の両面から経済を刺激しよう」というものだが、「日本は世界のロール・モデルに」「インフレ・ターゲットは4%で」「女性活用で伸びる潜在成長率」「消費税10%は絶対不可」「日本のバブル以上に大きい中国バブル」「日本国債を格付けするならAAA」などとクルーグマンは語る。内閣官房参与である浜田さんは、アベノミクスを解説し、補強する。
桜花のもと諸行事、党青年委員会の「VOICE ACTION」も――。4月2、3の土日、桜が満開。桜の名所・飛鳥山公園(北区)や滝野川桜通り、石神井川の桜、滝野川さくらまつり、舎人公園の千本桜まつりに多くの人が集い、私も参加をしました。
日曜日には、「桜ウォーク2016」(桜を見ながら家族で楽しくウォーキング)に早朝から1000名を超える人が参加、多くの人と懇談しました。
スポーツ行事も活発に行われ、国立代々木競技場第二体育館で、GLOBAL POINT&K.O.第31回空手道選手権大会が行われ、北海道から九州までと、スペイン、ベルギー、モンゴルなどの諸外国から選手も参加、開会式では大会総裁として激励の挨拶をしました。足立区では西足立ソフトボール連盟リーグ戦開会式にも出席しました。その他、舞踊や建設関係の大会、町会会館の落成祝いの集いなど、多彩な行事が行われました。
また全国各地で公明党青年委員会が行っている政策アンケート 「VOICE ACTION」が足立区でも行われ、青年党員の熱意が街に広がりました。青年党員の活躍に感謝です。
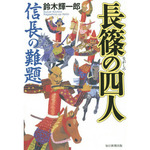 天正3年(1575年)4月、武田勝頼が長篠城を急襲する。勝頼の狙いの本丸は、三河・吉田城の奪取であり、野田城や牛久保が焼討ち等で脅かされる。たった500の軍勢で踏んばる奥平九八郎信昌。城を支配下におく家康は信長に援軍を頼み、勝頼を三河から蹴りだそうと織田・徳川連合軍が立ち上がる。そこに戦歴充分で鉄砲術の名手である明智光秀と、圧倒的な情報収集力と土木作事の名手・羽柴秀吉が信長の懐刀として派遣される。この時代を画した決戦は「鉄砲対騎馬武者の戦い」として知られるが、その真実は如何。
天正3年(1575年)4月、武田勝頼が長篠城を急襲する。勝頼の狙いの本丸は、三河・吉田城の奪取であり、野田城や牛久保が焼討ち等で脅かされる。たった500の軍勢で踏んばる奥平九八郎信昌。城を支配下におく家康は信長に援軍を頼み、勝頼を三河から蹴りだそうと織田・徳川連合軍が立ち上がる。そこに戦歴充分で鉄砲術の名手である明智光秀と、圧倒的な情報収集力と土木作事の名手・羽柴秀吉が信長の懐刀として派遣される。この時代を画した決戦は「鉄砲対騎馬武者の戦い」として知られるが、その真実は如何。
信長の無茶振りに、いつも翻弄される家康・秀吉・光秀の3人。今回は「織田軍の一兵も損せずに武田に勝て」「84日間で守り抜け」という難題だ。調子のいい秀吉、流浪が長かった還暦間際のちゃらんぽらんな老人・光秀、苦労と努力を重ね慎重な家康、それぞれが描かれ面白い。私の故郷の新城、野田城、牛久保、吉田(豊橋)、そして遠足で行った長篠城・・・・・・。なつかしい。
 訪日客2020年4000万人、2030年6000万人へーー。4月1日、党観光立国推進本部を開催。3月30日に政府が取りまとめた「明日の日本を支える観光ビジョン」について、観光庁からヒアリング・意見交換を行いました。
訪日客2020年4000万人、2030年6000万人へーー。4月1日、党観光立国推進本部を開催。3月30日に政府が取りまとめた「明日の日本を支える観光ビジョン」について、観光庁からヒアリング・意見交換を行いました。
今回のビジョンは、高い目標を掲げる一方、赤坂・京都の迎賓館など公的施設の開放、国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてのブランド化、滞在型農山漁村の体験などの観光資源の活用。さらに宿泊施設不足の早急な解消、キャッシュレス環境の改善、クルーズ船受入れで更なる拡充など、「観光先進国」へと新たなスタートが切られました。
 会合で私は「観光戦略は大事なステップアップの時を迎えている。数だけを追うのではなく、質、滞在日数から考えていかなければいけない。稼ぐ観光だ。遅れている東北の観光をインバウンド戦略、国内戦略に分けて取り組みたい。わが党としても日本の成長戦略の柱、観光をしっかりと推進していく」と述べました。
会合で私は「観光戦略は大事なステップアップの時を迎えている。数だけを追うのではなく、質、滞在日数から考えていかなければいけない。稼ぐ観光だ。遅れている東北の観光をインバウンド戦略、国内戦略に分けて取り組みたい。わが党としても日本の成長戦略の柱、観光をしっかりと推進していく」と述べました。
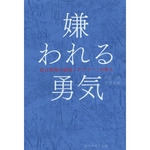 自己啓発の源流「アドラー」の教え――と副題にある。フロイト・ユングと並ぶ心理学のもう一人の巨頭・アルフレッド・アドラーの思想(アドラー心理学)を、青年と哲人の対話という形でまとめたのが本書。
自己啓発の源流「アドラー」の教え――と副題にある。フロイト・ユングと並ぶ心理学のもう一人の巨頭・アルフレッド・アドラーの思想(アドラー心理学)を、青年と哲人の対話という形でまとめたのが本書。
「アドラー心理学は、過去の"原因"ではなく、いまの"目的"を考える」「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」「われわれを苦しめる劣等感は"客観的な事実ではなく"主観的な解釈"なのだ」「承認欲求を否定せよ、他者の期待を満たすな、もっと自分本位に生きよ」「課題を分離せよ」「"あのとき殴られたから父との関係が悪くなった"というのはフロイト的な原因論発想。父との関係をよくしたくないために、殴られた記憶を持ち出していたというのがアドラー的な目的論の立場」「対人関係のゴールは"共同体感覚"」「人は"わたしは共同体にとって有益なのだ"と思えたときこそ、自らの価値を実感できる」「自己肯定ではなく、交換不能な"このわたし"をありのままに受け入れる自己受容を」「人生とは連続する刹那。"いま、ここ"を真剣に生きるべき」――。
古賀さんは、アドラー心理学を語る岸見さんにふれ、「岸見アドラー学」だという。現当二世、今ここに、自己自身に生きよ、ということだと思う。








