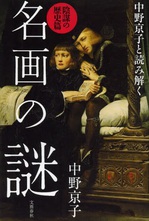花と緑は人の心を豊かに育み、生態系を支え、地球温暖化防止にも貢献する――5月24日、皇太子殿下のご臨席のもと、「第25回みどりの愛護のつどい」が徳島県鳴門市で行われました。
全国から緑化や自然環境保護の関係者、約1200名が参加。式典では、「犬ノ馬場公園愛護会(宮崎)」「ボランティア鳴門西(徳島)」「華・花倶楽部(北海道)」「アクセス通りを美しくしよう会(長野)」「フッチーほたる会(愛知)」など、日頃から地域で緑を守り育てる活動を行っている全国103の団体に、国土交通大臣表彰として感謝状をお送りしました。地域で長年にわたって努力を積み重ねてこられたグループの方々に感銘を受けました。
この日はさわやかな青空が広がり、風もなく、緑鮮やかな日となりましたが、皇太子殿下とともに記念植樹(私は鳴門市の木、モチノキ)を行いました。
その後、南海トラフ巨大地震による津波対策の現場を視察しました。
まず、鳴門市の撫養(むや)港では、海岸堤防が老朽化し、津波が来る前に地震による液状化で1mも沈下するおそれがあります。このため、堤防のかさ上げと地盤改良を行い、粘り強い堤防に作りかえています。
そして徳島市の四国横断自動車道では、盛土している高速道路の路肩に津波避難場所を整備しています。階段とスロープで駆け上がり、約800人が避難できるようになっており、全国のモデルになります。「周りには高い建物も高台もないので津波に対応できない。少しでも早く完成してほしい」と原秀樹徳島市長から要請を受けました。
この2日間、徳島県の活性化と津波対策についてさまざまな要請を受けました。
「陰謀の歴史篇」として17の絵画が取り上げられている。欧州文明の中で生きてきた者として、改めて欧州の歴史の重厚さを知る思いだ。卓越した名文、リズミカルで歯切れがよい。どんどん歴史の中に、引き込まれる。面白い。
絵画にもふれてきた。音楽にもふれてきた。そして欧州文明のなかで生活もしてきた。しかし、高校の世界史以来、学んでこなかったことを思い知る。ドラローシュの「ロンドン塔の王子たち」、スーラの「グランド・ジャット島の日曜日の午後」、ティツィアーノの「カール五世騎馬像」、ラファエロの「レオ十世と二人の枢機卿」、グレコの「ラオコーン」、ゴヤの「異端審問の法廷」・・・・・・。
その時代の権威、権力、宗教、文化、風俗、恐怖・・・・・・。面白く、息吹、臨場感が伝わってくる。
5月20日の閣議で、安倍総理から初代の水循環政策担当大臣に任命されました。今年3月に新たに成立した「水循環基本法」に基づき、水の総合的政策の司令塔を担うことになります。
水は貴重です。しかし今、世界で"油より水"と言われるほど水の争奪戦が激化しています。山紫水明といわれる日本は降水量も多く水は極めて豊富。また、漏水がない、サビ等がないなど上水道の技術が発達しており、水道の水がそのまま飲めます。さらに、農業用水、工業用水、発電などにも利用され、人々に大きな「恵み」を与えてきました。一方、洪水や土砂崩れなどの災害に見舞われるのも日本の特徴で、豪雨は集中化、局地化、激甚化している状況です。
水の「恵み」を活かし、「災い」から国民の命を守るため、水循環全体を視野に入れていくことが大事です。
これまでは関係する省庁も多く、対応もバラバラでしたが、これではいけないということで作られたのが「水循環基本法」です。同時に「雨水の利用推進法」も成立しましたが、"水は貴いもの"という理解をより深めていくことも大事です。
貴重な水が健全に循環する社会に向けて取り組みます。
「天国はいらない、ふるさとがほしい」――。ロシアの共産主義革命に批判的だった詩人・エセーニンの詩の一節だ。チェルノブイリの原発事故で汚染されてしまったナージャ村で、村を離れずに生き続けた農夫が、このエセーニンの詩を暗唱したという。
本著は松本健一さんの講演集だが、背景には東日本大震災がある。そして当然、近代、文明、歴史、日本再生、アジア、日中や日韓関係が語られ、確かなる視点、思想が示される。その核心は、パトリオティズムだ。「限界集落」「コメづくり(泥の文明と文化)」「国の自然を保全してもらうナショナル・トラストの担い手」「一所懸命のエートスをもつ民族」等を語る。
「人はパトリを失って生きていけるのか」「パトリオティズムこそ、私たちの長い歴史のなかでの人間の生き方だ」「各国ともネーション・ステート(近代の国民国家)をつくる方向で進んできたが、それはふるさと喪失のドラマでもあった。しかし若者の言語のなかにも、緑の多い風土に安らぎを感じる文化的遺伝子"ミーム"が刷り込まれている」――これからの日本の歩むべき道を根源的に示している。
5月17日、栃木県宇都宮市に行き、「利根川水系連合・総合水防演習」に参加しました。
この訓練は、毎年梅雨の出水期に入る前に実施しており、今年で63回目。今回は、国土交通省のほか栃木県、宇都宮市の警察、消防団、自衛隊など27の関係機関や地域の団体、中学生など約1000名が参加し、見学者も含めると約2万人と大規模なものとなりました。
会場となったのは鬼怒川(下流で利根川と合流。利根川はもともと東京湾に流れていたが、江戸を洪水から守るため、徳川家康が命じて1600年代に太平洋側に注ぐように改修――「利根川の東遷」)の河川敷。
決壊しそうな堤防を守るための各種水防工法の実施、中学生も参加する土のうづくり、ヘリコプターや重機を使って川の中洲にとり残された人の救出など、さまざまな訓練が次々と展開されました。
豪雨災害は局地化、集中化、激甚化しており、いざというときは地域の力で地域を守り抜くことが大事です。「多くの見学者にも実感をもって防災に活かせる実践的な訓練ができた。出水期に向けて万全の体制をとっていきたい」と私は訓練後の会見で述べました。
成果の多い訓練ができました。