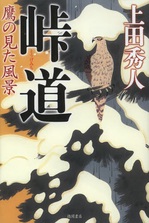6月13、14日の2日間にわたり、長崎県、佐賀県に行き、知事、市町村長、各種団体から要請を受け、また公明党結党50周年の政経セミナーに参加しました。
長崎は「観光」発祥の地といわれており、モナコ、香港と並ぶ「世界新3大夜景」に指定されています。観光振興や長崎新幹線、道路整備、IR(統合型リゾート)のほか、離島(長崎は離島の数が日本一)・半島といった長崎特有の要望を受けました。
14日午後は佐賀市内に移動。佐賀県は平成35年に「国民体育大会・全国障がい者スポーツ大会」を目指していて、そのための有明沿岸道路や防災などのインフラ整備が大きな課題となっています。佐賀は米、お茶などの農産物、豊富な海産物やお酒のほか、陶磁器(有田焼、伊万里焼、唐津焼)など日本屈指のものを産出しています。
長崎も佐賀も大きなポテンシャルをもっており、それをどう生かすか。また直面している人口減少にどのように対応していくか。それらの資源・技術を生かすためのインフラ整備の大切さを感じる2日間となりました。
「明治以後の日本人は、なに食わぬ顔をして儒学を捨てた」「(しかし)江戸時代に学問は儒学しかなかった。人文科学も社会科学も自然科学もない。だから我こそはと意気込む天下の俊秀、大天狗、小天狗は、草莽の臣であっても、こぞって儒学に向かった。・・・・・・知と知を競い合うことに鎬を削った」「その知の競い合いの頂点に立った男こそ"知の巨人、荻生徂徠"その人であった」――その江戸の250年、日本人は脳に磨きをかけたからこそ、明治以来の人文科学等をただちに"我が物"にできたのだという。
この荻生徂徠伝は、伝記的な面と徂徠学、思想の面が融合して描かれる。
「財政難」「富士山噴火や大火」「生類をいたわり、憐むこと」「学問重視」の綱吉の時代は延宝8年(1680年)から28年に及ぶ。綱吉に重用された柳沢美濃守吉保の庇護のもと猛勉強した荻生徂徠。新井白石、伊藤仁斎・東涯父子との対立感情、荻生徂徠の下に集う平野金華、太宰春台、服部南郭、安藤東野、三浦竹渓らの俊秀。学者間の鍔迫り合いは時代の空気を浮き彫りにする。
「先王の道は天下を安んずるの道なり」「礼楽刑政こそが"道"である」――。道は天下国家を平定するために、聖人が建立した道である。朱子学一辺倒の時代に、それを乗り越え、徂徠学の根本テーゼを打ち立て、実践的な「道」の概念を重視した。「名君・徳川吉宗に天下国家を治める道を説いた思想家"荻生徂徠"」だが、本書で描く両者のやり取りも"いかにも"面白い。
「終わりなき危機 君はグローバリゼーションの真実を見たか」「世界経済の大潮流」の両著の延長線上にある。
「地理的・物的空間(実物投資空間)」に見切りをつけた先進国の資本家たちは「電子・金融空間」という新たな空間をつくり、利潤極大化という資本の自己増殖を継続している。リーマン・ショックは、その無理な膨張が破裂したものだ。グローバリゼーションは「中心」と「周辺」の組み替え作業であり、「先進国(中心)と途上国(周辺)」「ウォール街(中心)と自国民(周辺)」という構造をもつ。食料価格や資源価格の高騰は、貧富の二極化、中間層の没落を引き起こす。グローバル化と格差の拡大だ。「ゼロ金利は資本主義卒業の証」「矛盾が、資本主義終焉の一歩手前まで蓄積している」「資本主義の本質は"中心・周辺"という分割にもとづいて、富やマネーを"周辺"から"蒐集"し、"中心"に集中させることだ」――。
そこでどうするか。本書の意図はそこにある。まず資本主義の暴走を食い止めて、どう"定常状態"をつくるかだ。ゼロ金利、ゼロ成長、ゼロインフレに突入している日本は、それをアドバンテージだととらえて、人口減少に歯止めをかけ、国内での安価なエネルギー創出なども含め、"定常状態"をつくるべきだ。成長市場主義から脱却しよう、という。
「砂浜を取り戻す」――6月8日、神奈川県二宮町に行き、西湘海岸保全事業着手式に出席しました。
湘南海岸の西側、小田原市から大磯町にかけての西湘海岸は、美しい景観に恵まれ、海水浴や釣りなど海のレジャーが盛んな地域。しかし一方で、深く急峻な海底谷が海岸に迫る特殊な地形のため高波が襲いやすく、海岸の砂が流出して浸食され、これまで度々被害を受けてきました。平成19年の台風9号では、高波で30mほどあった砂浜が完全になくなり、海沿いを走る西湘バイパスが約1km崩れ、3週間も通行止めになったほど。美しい景観を再生し、地域の安全を守っていくことが課題です。
海底の谷への砂の流出をくい止め、砂浜を回復するのは全国でも例がない難工事。地元からは「難工事なので、是非、国が事業を進めてほしい」と強い要望をいただいていましたが、今年度から国交省が直轄で事業を進めることになりました。
式典で私は、「工事に当たり、地域の特性に応じた新工法を採用しながら対策を実施し、早期完成に向けて最大限努力をする」と述べました。
地元の黒岩祐治・神奈川県知事、加藤憲一・小田原市長、坂本孝也・二宮町長、中﨑久雄・大磯町長から、「永年の悲願が叶った」「1日も早く昔の砂浜を取り戻したい」と感謝と期待の挨拶が続きました。
去る4日には、海岸法の改正が国会で成立したばかり。「緑の防潮堤」など新しい取り組みも始まりました。海岸の防災・減災、適切な維持管理に向けて取り組みます。
内村鑑三が「代表的日本人」で、ケネディ大統領が「尊敬する日本人政治家」としてあげた上杉鷹山(1751年~1822年)。日向高鍋藩主・秋月種美の次男で、10歳で米沢藩の第8代藩主・上杉重定の養子となる。
家康に敵対して120万石から30万石へ、さらに三代藩主・綱勝の急死によって断絶寸前で15万石に減らされた衰退の上杉を引き継いだ上杉治憲(鷹山)だが、その生涯は苦難の連続。養子、小藩の出と馬鹿にされ、寵臣の堕落、飢饉、火災、さらには幕府から課せられる手伝い普請・・・・・・。他の大名家もそうであったと思われるがとにかく財政ひっ迫、借金まみれ。米以外の漆や楮(こうぞ)、桑など殖産興業を、武士たち参加の下で生き抜こうとした。
民とともにある名君・上杉鷹山というより、寵臣をも断罪・切り捨てて進んでいく激情・苦闘の人物像を描いている。「なせば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」の名言の意味するところを知ることができた。本書では「勇をもって当たれば、何事もなせまする」と逡巡のなかで決断して進む鷹山の強さが印象深い。