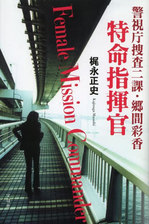「東京オリンピックに向けて世界に誇れる水辺空間を目指す」――6月23日、都内で水循環に関係する隅田川や神田川、墨田区役所などの現地を視察しました。
水循環基本法が7月1日から施行されるのを前に、水循環担当大臣としての視察です。これには中央大学理工学部の山田正教授やミス日本「水の天使」の神田れいみさんも同行、東京の治水・利水の歴史や環境など幅広く意見交換をしました。
まず墨田区役所で雨水利用施設を視察。墨田区は雨水利用を先駆的に実行。庁舎で使うトイレ洗浄水の3分の1を雨水でまかなっており、両国国技館やスカイツリーでも同様の雨水利用を行い、大変効果を上げています。
その後ボートで隅田川から神田川、さらには日本橋川を巡り、川の上から河川浄化の現状や川沿いの利用状況を確認しました。
隅田川は高度経済成長期に水質が悪化し、悪臭を放っていました。しかしその後、利根川や荒川の水を隅田川に導入したり、下水道の整備を進めることで水質がかなり改善。今では川を巡る観光船も多く、建物も川に向いて建ち、水辺が貴重な空間として利用されています。堤防も植栽が施され、水と緑で心が和む景観になっています。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックは臨海部が主な会場で、川沿いも含めた水辺空間を活かすことが大事。世界に誇れる水辺空間を実現するため、さらなる水質浄化や美しい景観づくりが必要です。
8月1日は水循環基本法で定められた「水の日」。我が国伝統の河川工学は、力で水をコントロールするのではなく、「川をなだめる」「自然と折り合う」です。防災・減災、自然との共生、良き水循環社会が大切です。水の貴さ、水循環については、何といっても、国民全体の理解と日常生活での行動が大切です。さらに理解を深めていただくよう取り組みを進めます。
副題に「時代の十歩先が見えた男」とある。「百歩先の見えるものは狂人扱いされ 五十歩先の見えるものは多くは犠牲者となる 十歩先の見えるものが成功者で 現在を見得ぬものは、落伍者である」(小林一三「歌劇十曲」)――。
明治6年、山梨県に生まれ、慶応大卒業後、三井銀行を経て、箕面有馬電気軌道の専務に。沿線開発を通じて利用者を拡大し、阪神急行電鉄とし、社長に就任。宝塚歌劇団をつくり上げ(今年、創立100周年)、阪急百貨店、東京宝塚劇場、東宝映画、阪神ブレーブス・・・・・・。次から次へと無から有を生み出していく夢と信念の稀代の事業家・小林一三は、商工大臣にも就く。
「人一倍豊かな想像力」「無理をするな――焦らず堅実に着々と」「人に頼るな。最後に頼むものは自分以外には決してない」「あれほど頭のいい人は見たことがない(白洲次郎)」「えらい人ってのは、世の中に対して貸勘定の多い人ってことだね(小林一三は、事業の面でも、大衆に楽しさ、便利さの貸勘定を残していった人だ)」「飽くなき探究心」「国民全体が働くことだ。努力することだ。努力を惜しまなければ日本は実に立派な国になる(昭和31年、梅田コマ竣工式で)」「働くことだ。人の二倍も三倍も働け。働きもしないで人が認めてくれるはずがない」「金がないから何もできないという人間は、金があっても何もできない人間である」「無から有を生み出すのは家の芸だ。枯れ木に花を咲かせましょう」・・・・・・。
さらに思うことは、豊富な人間関係、いざという時に、必ず助けてくれる人が現われていることだ。岩下清周、平賀敏、岸本兼太郎、矢野恒太、松永安左ヱ門、高碕達之助、白洲次郎・・・・・・。人間の縁と運は、偶然などではけっしてない。
17日朝、首相官邸において、第4回観光立国推進閣僚会議が開催され、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014」を決定しました。観光庁を所管する国交省がその推進力となるもので、全国を回りながら練り上げてきたものです。
我が国を訪れる外国人は、昨年史上初めて1000万人の大台を突破。今年になっても5月までの累計は、前年比28%増と、好調です。
今回策定されたアクションプログラムは、この流れを加速し、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に2000万人達成という目標を明記した意欲的なものとなりました。
アクションプログラムは、次の6本の柱で構成されます。
①「2020年オリンピック・パラリンピック」を見据えた観光振興
②インバウンドの飛躍的拡大に向けた取組
③ビザ要件の緩和など訪日旅行の容易化
④世界に通用する魅力ある観光地域づくり
⑤外国人旅行者の受入環境整備
⑥MICEの誘致・開催促進と外国人ビジネス客の取り込み
日本は四季折りおりの景観といい、観光客の求める「食べ物」「買い物」といい、日本人のやさしさ(おもてなしの心)や時間の正確さや技術水準の高さなど、きわめて大きなポテンシャルをもっています。「世界に通用する魅力ある観光地域づくり」は間違いなくできるし、可能性は大です。
また、ビザ要件の緩和については、インドネシア向けのビザを免除、フィリピン、ベトナム向けのビザの一層の緩和を決定しました。さらに、外国人向けの免税店の数を現在よりも倍増し、1万店規模とすることを盛り込んでいます。
2000万人達成へのエンジン役として、計画の実現を図ります。
「敗北を抱きしめて」のジョン・ダワーは「今日の諸問題に取り組むとき、私たちはいつも、第二次大戦における日本の降伏、次いで米国による対日占領、そして1951年から52年にかけてのサンフランシスコ講和および日米安保両条約に行き当たる」という。憲法、朝鮮戦争、そして領土・・・・・・。そして、両氏は「現在を理解するには、もっと長い目で物事を見る必要がある」「問題は、米中、日米、日中、日韓、日朝における緊張がどのように制御され、解決されるか、ということだ」という問題意識を共有する。ジョン・ダワーは、戦後日本を規定したサンフランシスコ体制の"負の遺産"として、「沖縄と"二つの日本"」「未解決の領土問題」「米軍基地」「再軍備」「歴史問題」など8項目を挙げ、"従属的独立"と手厳しくいう。歴史は、そうした"遺産"とそこに生ずる感情、力、経済、誇り、恥辱を含めて形成されて今をつくる。いずれにしても、大事な時にさしかかっている。