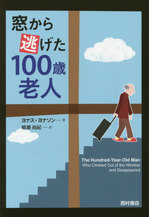100歳の誕生日に老人ホームから逃げ出した主人公、アラン・カールソンは、ひょんなことからギャング団の巨額の大金の入ったスーツケースを奪ってしまう。追手は増えていく。しかしアランは、出会う人間を次々と仲間に入れてしまう(近隣の鼻つまみ者ユーリウス・ヨンソンとか、ホットドッグ屋のベニー・ユングベリとか、その兄ボッセ・ユングベリとか、湖畔農場で暮らす赤毛女性ベッピンとか)。そればかりか、その大金をもっていた犯罪組織の親分や、象ソニアまでもだ。奇想天外、ハチャメチャ、デタラメな珍道中コメディだ。
しかもこの100歳のアランという男の人生がハチャメチャ。20世紀の歴史的事件に全部といっていいほどからんでいるという。その人生紹介が本書の3分の1位を占める。爆弾づくりの専門家として、フランコ将軍、トルーマン、スターリン、毛沢東、ド・ゴール、チャーチル、ジョンソン、ニクソン、フォード、ブレジネフ。たとえばSALTⅡなどもだ。
柳瀬さんは、「訳者あとがき」で「すばらしき出鱈目小説」と題し、「最も無駄になった一日は笑うことのなかった日である」という警句を紹介している。作者はスウェーデンの人。全世界で800万部を突破したという。
11月1日、奈良県に行き、大規模な土砂災害の防災対策、飛鳥・奈良時代の歴史・文化を活かしたまちづくりについて、視察、意見交換しました。
まず土砂災害。今年も広島などで多くの豪雨災害がありましたが、3年前の平成23年8月、紀伊半島を桁違いの豪雨が襲いました。台風12号により5日間降り続いた雨は、紀伊半島山間部の広い範囲で1000mmを超え(2000mmを超えたところもあります)、多くの山の斜面で深層崩壊(地盤の深い層から根こそぎ崩れる現象)が発生。大量の土砂が集落や川に襲いかかりました。その量たるや、なんと約1億m3。東京ドーム約80杯分で、戦後最大規模です。道路は至るところで寸断されて多くの集落が孤立。土砂が川や渓流を塞いだところでは、天然ダム(河道閉塞)が数多くできました。それが決壊すると下流で二次災害が起こるため、国交省が排水路や砂防堰堤を整備していますが、今でも雨が降ると土砂が流れ込み、その対策は難工事です。
この日は五條市長、十津川村長、野迫川(のせがわ)村長、天川(てんかわ)村長と意見交換。災害当時の生々しい被災状況やご苦労をお聞きし、復旧に向けた要請を受けました。「今も大雨のたびに災害が起きないか心配している」「土砂を取っても取っても次々と流れてくる」「森林を守るために地域に住み続けたい。国交省のこれまでの取組に感謝しており、引き続き復興を支援してほしい」「災害でも孤立しないよう"命の道"である国道168号の整備を」――砂防工事には時間がかかりますが、対策に全力を尽くします。
そして歴史まちづくりについて。明日香村では、森本晃司元建設大臣(地元でボランティアガイドとしてご活躍)や森川裕一村長に案内していただきました。明日香村は約1400~1300年前の西暦600年代に国の都が置かれたところ。聖徳太子や推古天皇、大化の改新や壬申の乱など、数々の歴史の舞台となり、万葉集にも歌われた自然と景観が残っています。その"日本人の心のふるさと"とも言うべき歴史的風土を守るため、昭和55年に制定された明日香特別措置法で村全体の開発が制限されています。
その効果を示すように、実際に村に入るなり景観は一変。懐かしい田園風景が広がり、建物も低く抑えられ、屋根の形や瓦の色も統一されています。村に一つあるセブンイレブンもグレーの瓦屋根で、落ち着いた雰囲気です。古代のロマンを守るために続けられてきた努力が、まちづくりに結実していることを実感しました。
その後、奈良市へ移動。車中からも荒井正吾知事から道路整備やまちづくり、観光などの要望を受け、さらに復元が進められている奈良時代の都、平常宮跡や大極殿等を視察しました。
古代の歴史と文化の魅力を生み出すよう努力していることを実感。観光庁や公園整備を担当している私にとって有意義な視察となりました。
現場の声を大事にし、「ジャーナリズムは権力を批判するのが仕事だ」という鈴木さんが、安倍政権と政党に歯に衣着せぬ批評を展開する。フランスの哲学者ベルクソンは「問題は正しく提起されたときにそれ自体が解決である」といったが、何事も論議がまともに行われて熟度のある問題提起がされることが大切だ。そのためには視野は360度にわたることともに、三次元、四次元の論議ということだろう。
本書は「安倍政権の5大問題」「世界から見た安倍外交」「安倍政権の未来」の三章からなるが、あえて問題をぶつけようと、インコースへシュート、アウトコースへスライダーと多彩な球を投げているように思う。その厳しい攻めを受けてキチッと打つのが政権というものだろう。
「安倍総理はリアリスト」などの人物評も随所に出てくるが、鈴木さんの人間への温かさを私は感ずる。
10月29日、この日は世界の水循環、水災害を考える上で大きな一日となりました。
午後は、皇太子殿下をお迎えして行われた国連「水と衛生に関する諮問委員会」に出席して私も発言。また夜は皇居で、来日しているオランダのアレキサンダー国王を歓迎する宮中晩餐会に出席しました。国王は昨年5月までの皇太子時代、「水と衛生委員会」の第2代議長を務められ、世界の水問題解決に深く関わってきておられます。晩餐会でも、明治時代よりデ・レイケなどの土木技術者がオランダから日本に来て、我が国の河川工学に寄与した実績について、天皇陛下と国王からご発言がありました。
国連「水と衛生委員会」は各国の閣僚経験者や有識者がメンバーとなって、安全な飲み水確保など世界の水資源問題解決に向けた提言を行うためのもので、皇太子殿下が名誉総裁を務められています。この日の会議には20か国から約40人が参加。皇太子殿下のお言葉の後、私が挨拶し、「我が国は今年、水循環基本法を制定して世界に先駆けた取り組みを始めた。治水や利水の大切さを世界で共有し、健全な水循環の確保に向けて行動を起こしていきたい」と述べました。
その後の討論では、アイト議長(元ドイツ経済協力開発省副大臣)が日本の支援と貢献に感謝を表明。ハン・スンス国連事務総長特使(元韓国首相)、シンソン・フィリピン公共事業道路大臣をはじめ、オランダ、コロンビア、ブルガリアの代表者から、「世界で起きている災害の教訓を学んで備えをしていくことが大事」「水循環のガバナンスが重要」など意見表明が続きました。討論の締め括りとして私から、防災の情報を避難に結びつけることの重要性や、今年からタイムラインの取り組みを始めたことなど、我が国の防災対策の考え方と現状を説明しました。
世界の水災害や水循環の問題を共に考えるとともに、我が国の取り組みを示すいい機会となりました。
「建設業で働く女性を"けんせつ小町"に」――10月28日、建設業の現場で活躍する11名の女性が国土交通大臣室に来られました。建設業で働く女性の愛称を決定したので広めていきたいとのことです。
これまでは"ドボジョ"(土木女子)の愛称が普及していますが、土木だけでなく建築や設備、機械など幅広い職種を指す言葉として選ばれたものです。たいへん親しみやすいネーミングで、建設業界で女性が活き活きと活躍できるということをアピールできます。
私はこれまでも、建設業で働く女性たちとの対談や、女性活用のモデルケースである東京外環の建設現場視察など、取り組みを行ってきました。男の職場というイメージが強い建設業でも、女性がもっと活躍できるようにするための動きが着々と広がってきています。
女性が活躍する社会の実現に向けてしっかり取り組みます。