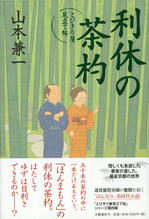11月13日、建設産業専門団体連合会(建専連)の全国大会に出席しました。「現場が大事」「ものづくり人材が大事」「現場の担い手こそ日本の力」と思っている私にとって、大事な大会となりました。
この団体は、鉄筋、型枠、管工事など建設業の現場を支えるさまざまな専門工事業の団体で構成されています。
インフラの整備や維持管理を進めるためには、何といっても現場の担い手が大事。しかしこの10年ほど、公共事業の削減やダンピングの横行などで処遇が悪化し、現場の担い手が職から離れていったり、若者の入職が減るという厳しい状況が続いていました。これに対し私は、16年ぶりの労務単価の大幅引き上げや、いわゆる「担い手3法」(建設業法、入札契約適正化法、公共工事品質確保法)の改正などで、担い手の処遇改善に力を入れてきました。昨年7月には静岡県の富士教育訓練センターに行き、建設業を目指して実習する若者を激励しました(写真)。
大会で私は、「現場の技能労働者の賃金や休暇など処遇を改善し、誇りや将来への見通しが持てる仕事になるように取り組んできた。今その流れが作られつつある。さらなる環境整備を進めたい」と挨拶。建専連の才賀清二郎会長をはじめ多くの方から、「賃金がずっと下がり続けてきた状況が変わり、明るい展望が開けてきた」「社会保険加入促進や元請・下請関係の改善などに、さらに力を貸してほしい」とお礼と期待が述べられました。
現場で技術をもって働く担い手の処遇改善、確保・育成に全力をあげて取り組みます。
11月は児童虐待防止月間。私もそのシンボルマークであるオレンジリボンを付けて閣議と記者会見に臨みました。
「所在不明の子どもが全国で141名」――厚生労働省が13日に発表した調査結果がマスコミでも大きく取り上げられました。
子どもへの暴力は我が国でも深刻な状況です。2013年度の児童相談所での虐待相談件数は約7万3765件と過去最高。その要因は、公明党の主導で成立した児童虐待防止法が成果を上げている面と、虐待そのものが増えている面の両面が考えられます。
虐待の原因は、望まない妊娠や経済的困窮、産後うつなどさまざま。その解決のためには妊娠から出産、子育てまで切れ目なく支援することが必要です。妊婦や母親が一人で悩みを抱えたままにならないよう、産後ケア体制の拡充など出産直後の母親の心身をサポートする取り組みが必要です。また虐待にとどまらず、しつけや体罰名目の暴力もなくしていかなければなりません。
公明党は11月に全国各地でオレンジリボン街頭演説会を開催しています。国会議員と地方議員、女性議員と男性議員が連携して、現場の声を聞き、児童虐待防止を推進します。私もしっかり取り組む決意です。
11月8日、地元の岩淵水門で進められている耐震工事を北区議の皆さんとともに視察しました。
岩淵水門は、私の地元北区にあり、荒川と隅田川の分岐点に位置します。荒川上流から来た水がこの水門で荒川と隅田川に分かれ、大雨で増水すればゲートを閉めて隅田川へ流れるのを防ぎます。ひとたび洪水が埼玉など荒川上流で起きれば、岩淵水門が首都東京を洪水から守る「水害対策の要」としての役割を担い、まさに命綱とも言うべき極めて重要な水門です。
実は、岩淵水門から下流の荒川は、明治43年の洪水をきっかけに新たに掘られた放水路。大正13年に放水路と水門が完成して今年で90年になります。今の岩淵水門(通称「青水門」)は、昭和57年に完成した2代目(初代は「赤水門」として隣に現存)ですが、現在耐震工事が進行中。これは、首都直下地震など巨大地震が発生した場合に柱が座屈してゲートが閉まらなくなるおそれがあるため、鉄筋を増やして強度を増す工事です。
首都直下地震の発生が台風など荒川上流の増水と重なれば、ゼロメートル地帯や地下鉄、地下街が多い東京の下町は複合災害で壊滅的な被害となる恐れがあります。それを防ぐための耐震化工事は、地元だけでなく、首都東京の安全・安心にとって極めて重要です。
近年は雨の降り方が変わってきて、局地化、集中化、激甚化しています。「想定外」の結果を起こさないよう、あらゆる事態を想定しながら、命を守る防災・減災対策に万全の対策を打っていきます。
山本兼一さんの「とびきり屋見立て怗」のシリーズ第4弾。「ええもんひとつ」など幕末の京都の町の空気を見事に表現していたが、遺作ともなったこの「利休の茶杓」もとても良い。
真之介とゆずが三条木屋町に開いた道具屋の「とびきり屋」。薩摩・会津両藩が、宮中クーデターを起こし、尊攘派を排撃した1863年(文久3年)の8月18日の政変、三条実美らの7卿落(それが一年後の禁門の変、蛤御門の変へと連なる)。そんな騒がしい京都の町で、桂小五郎や芹沢鴨、近藤勇らとも日常的に接する庶民のたくましさ、暖かさ、人情、夫婦の愛、日常の幸せ感・・・・・・。
「利休にたずねよ」をはじめとして、いい作品を書かれた山本兼一さん。今年2月、逝去された。

11月12日、土砂災害防止法の改正が参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。
この法律は、今年8月20日に広島市で発生した集中豪雨災害を受けて、急きょこの臨時国会に提出したものです。私は災害直後の8月21日、被災した広島市安佐南区八木と安佐北区可部東の現場に入り(写真)、それ以降対策に取り組んできました。
今回の改正内容は、ソフト対策を中心にしたものです。その柱は3点。住民に土砂災害の危険性を早期に伝えるために基礎調査の結果公表を義務づけること、避難勧告の発令が遅れないよう土砂災害警戒情報を法律上位置付けること、土砂災害に対する安全な避難場所の確保など避難体制を強化することです。これで調査が進み、土砂災害警戒区域や特別警戒区域の指定が促進され、きめ細かな避難計画が作られることになります(写真は11月5日の参議院本会議)。

12日には、広島県の湯崎英彦知事が国交大臣室に来られ、法律の早期制定のお礼と、調査の促進や砂防堰堤整備への支援要請がありました。
雨の降り方が集中化、局地化、激甚化している中、命を守るための防災・減災に危機感を持って取り組まなければなりません。砂防堰堤などのハード対策だけでなく、避難のためのソフト対策も組み合わせて、安全・安心のために全力で取り組みます。